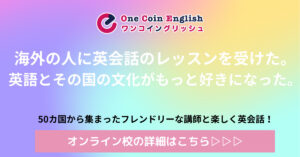【アメリカの文化を学ぶ!】アメリカの食文化の日本との違い5選 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

グローバル化が進む現代社会では、異なる食文化を理解することも大切なコミュニケーションの一つになっています。「食」は文化の重要な一部であり、その国の歴史や価値観を映し出す鏡でもあります。日本人にとって当たり前の食習慣が、アメリカではまったく異なることも少なくありません。
本記事では、日本在住のアメリカ人にインタビューを行い、アメリカの食文化と日本の食文化の違いについて詳しく聞いてみました。留学や長期滞在、移住を考えている方はもちろん、旅行者の方にも参考になる情報をお届けします。
アメリカってどんな国? 日本からのイメージ
ファストフード、肉料理、大きなポーションサイズ、多様な食文化…皆さんはアメリカの食文化と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
アメリカ合衆国は、50の州からなる広大な国で、各地域によって気候や歴史的背景が異なるため、食文化も多様です。東海岸のシーフード料理、南部のソウルフード、テキサスのバーベキュー、カリフォルニアのフュージョン料理など、地域ごとに特色ある食文化が発展しています。
また、アメリカは「移民の国」でもあるため、イタリアン、メキシカン、中華、タイ、インドなど、世界各国の料理が独自の進化を遂げているのも特徴です。多様性と融合が生み出す独特の食文化は、アメリカを理解する上での重要な鍵となるでしょう。
アメリカで暮らす/アメリカに行くメリットについて
メリット1:食の多様性
世界中のあらゆる料理が一つの国で楽しめます。イタリアン、メキシカン、中華、タイ、インド、エチオピアン…地域によっては本場顔負けの本格的な味を提供するレストランも。また、これらの食文化が融合した独自の「アメリカ料理」も魅力的です。
メリット2:食のアクセシビリティ
24時間営業のレストランやデリバリーサービスの充実など、いつでもどこでも食事ができる便利さがあります。また、様々な食事制限(ベジタリアン、ヴィーガン、グルテンフリーなど)に対応したメニューが一般的で、食のニーズに合わせた選択肢が豊富です。
メリット3:フードカルチャーの革新性
常に新しい食のトレンドが生まれる活気ある文化です。フードトラック、ファーマーズマーケット、クラフトビール、特産コーヒーなど、食を通じた新しい体験や発見が待っています。また、「ファーム・トゥ・テーブル」のような持続可能な食のムーブメントも盛んです。
メリット4:食を通じたコミュニティ体験
バーベキュー、テールゲートパーティー、ポットラックディナーなど、食を囲んで人々が集まる独自の文化があります。これらのイベントを通じて地元の人々と交流し、本当のアメリカ文化を体験できる機会が豊富にあります。
① アメリカの食文化の日本との違い(食事)
―アメリカの食事で、日本と一番違うなって思うのはどんなところ?
何と言っても「量」ですね!レストランの一人前のサイズが日本の倍以上あることも珍しくないんです。特にチェーン店では、最初に出されるポーションで「これで一人前?」と驚くことになるでしょう。でも地元の人は当たり前のように食べきれなかった分を「doggy bag(持ち帰り容器)」に入れて持ち帰ります。日本だと恥ずかしいと思われるかもしれませんが、アメリカでは食べ物を無駄にしないという意味でも普通のことなんです。
あとは「食事の時間帯」も結構違います。朝食は7時頃、ランチは12時頃までに済ませて、夕食は早い人だと17時、遅くても19時頃には食べ始めます。日本の感覚だと「まだ夕方じゃない?」と思うような時間に夕食を食べるのが普通なんです。これは9時〜17時の勤務形態が一般的で、通勤時間も比較的短いことが関係しているかもしれません。
「朝食文化」も日本とは大きく異なります。日本ではご飯や味噌汁、焼き魚などの和食や、パンと卵料理といった軽めの食事が主流ですが、アメリカの朝食はかなりしっかりしています。パンケーキやワッフル、フレンチトースト、卵とベーコン、ハッシュブラウン(ジャガイモのハッシュ)など、日本の感覚では「ブランチ」のようなボリュームです。特に週末の朝食は家族や友人と楽しむ大切な時間になっています。
「食事のペース」も違います。日本では「ゆっくり食べる」のが一般的ですが、アメリカでは比較的早く食べる傾向があります。ランチタイムは特に短く、30分程度で済ませることも珍しくありません。その代わり、食事中の会話は活発で、口に食べ物を入れながら話すことも失礼とは見なされない文化です。
「飲み物の消費量」も驚きの違いです。アメリカのレストランではまず最初に水やドリンクが出され、食事中も頻繁におかわりされます。特に氷入りの冷たい飲み物が好まれ、コップ一杯の氷に飲み物が注がれるスタイルが一般的。また、ソーダ(炭酸飲料)のサイズも驚くほど大きく、一人で1リットル近く飲むこともあります。お代わり自由のレストランも多いですよ。
―外食の時のマナーとか、日本と違うものってある?
「チップ文化」はアメリカならではですね。レストランでは一般的に請求額の15〜20%をチップとして支払います。これはサービス料ではなく、ウェイターやウェイトレスへの報酬の一部という位置づけです。質の高いサービスには20%以上、普通なら15〜18%程度が目安です。チップを払わないのは、よほどひどいサービスを受けた時だけで、基本的には必ず払うものと考えてください。
「水へのこだわり」も違います。日本では当たり前に出される無料のお水ですが、アメリカでは「tap water(水道水)」と明確に注文する必要があることも。そうしないと、ボトルウォーターを出されて料金を取られることがあります。また、多くのレストランでは最初から氷水のピッチャーをテーブルに置くスタイルで、常に水が飲める状態になっています。
「席への案内方法」も異なります。日本では店員が席まで案内してくれることが多いですが、アメリカのカジュアルなレストランでは「Seat yourself(好きな席に座ってください)」というスタイルも一般的。入口に「Please wait to be seated」の表示がなければ、空いている席を自分で選んで座ることができます。
「食事の順番」も違います。日本では前菜、メイン、デザートと順番に出されることが多いですが、アメリカではアペタイザー(前菜)がメインの少し前に出され、しばしば全員でシェアします。また、サラダがメインの前に別皿で出されるのも特徴的です。デザートは基本的に別オーダーで、食後にメニューを見て決めるスタイルです。
「食事の席での立ち振る舞い」も異なります。日本ではなるべく静かに、周りに迷惑をかけないように食事をするのがマナーですが、アメリカではもっとカジュアルで賑やかな食事風景が一般的です。笑い声や会話が大きくても気にされることは少なく、むしろ楽しく食事をしている雰囲気が好まれます。
② アメリカの食文化の日本との違い(会話)
―アメリカでは、食事のときに何について話すことが多いの?
「仕事や学校の出来事」は定番の話題です。日本では「仕事の話は食事の席で避ける」という考え方もありますが、アメリカでは逆に「今日あった面白いこと」や「現在取り組んでいるプロジェクト」などを積極的に共有することが多いです。特に家族の食事では、子供の学校での出来事や親の仕事の様子を話すのが一般的です。
「スポーツ」も大きな話題です。特に野球(MLB)やアメリカンフットボール(NFL)、バスケットボール(NBA)などのプロスポーツの話題は食事の席でもよく出ます。地元チームの試合結果や選手の移籍、プレイオフの展望など、スポーツに詳しくなくても会話に入れるような話題が選ばれることが多いです。
「テレビ番組や映画」の話題も人気です。「昨日見たテレビ番組」や「最近観た映画」について感想を共有したり、おすすめを紹介し合ったりします。Netflixなどのストリーミングサービスの普及で、「今ハマっているドラマシリーズ」の話で盛り上がることも多いです。
「政治や時事問題」については、親しい間柄なら話すこともあります。日本では食事の席での政治話はタブー視されがちですが、アメリカではより一般的です。ただし、初対面の人や職場の同僚との食事では、政治的な意見の相違による対立を避けるため、あまり深入りしない配慮も見られます。
「食べ物そのもの」についての会話も多いです。「このステーキ、どう調理してるんだろう?」「このソースの材料は何だろう?」など、目の前の料理について話すのはもちろん、「最近見つけた美味しいレストラン」や「家で作った料理のレシピ」などを共有することも。食の話題は比較的中立で、誰でも参加しやすい会話です。
―食事中に話さない方がいい話題とかってある?
「ダイエットや体重」の話は避けた方が無難です。特に誰かが食事を楽しんでいる最中に「カロリーが高そう」とか「太りそう」などのコメントをするのは、相手の食欲を削いでしまう可能性があります。健康的な食事への関心が高まっているとはいえ、食事中はあまり触れない方が良い話題とされています。
「政治や宗教」は親しくない間柄では注意が必要です。特に意見が分かれやすいホットトピックスは、食事を楽しむ雰囲気を壊してしまうことも。アメリカは政治的に二極化している面があり、特に初対面の人との食事では避けた方が無難な話題です。
「健康上の問題や病気」も、食事中にはあまり適さない話題とされています。特に生々しい症状や手術の詳細などは、食欲をなくす可能性があります。ただし、アレルギーや食事制限については安全のために伝える必要があり、これは例外です。
「否定的な噂話」も避けるべき話題です。誰かの陰口や悪口は、食事の雰囲気を悪くするだけでなく、話し手の印象も下げてしまいます。アメリカでは「If you don’t have anything nice to say, don’t say anything at all(良いことが言えないなら、何も言わない方がいい)」という格言もあります。
「お金」の話も直接的すぎると避けられる傾向があります。特に「年収」や「資産状況」などのプライベートな金銭事情は、親しい間柄でも食事の席では避けられることが多いです。ただし、「投資」や「節約術」などの一般的な金銭話題は、カジュアルな会話として受け入れられることもあります。]
③ アメリカの食文化の日本との違い(記念日/祝日)
―アメリカでは、クリスマスや新年はどんな料理を食べるの?
「クリスマスディナー」は家族の大切な食事です。七面鳥やハムのロースト、マッシュポテト、グレービーソース、スタッフィング(パンの詰め物)、様々な野菜の付け合わせ、そしてデザートにはパンプキンパイやアップルパイが定番です。感謝祭のメニューと似ていますが、クリスマスではより凝ったデザートやアルコール飲料が加わることも。家族によっては特別なレシピがあり、「うちのクリスマスディナーと言えばこれ」という伝統料理を大切にしています。
「新年」は日本のように特定の料理がある訳ではありません。むしろ、「パーティーフード」が中心です。新年のカウントダウンパーティーでは、指で食べられる小さなアペタイザーや軽食(フィンガーフード)が人気で、チップス&ディップ、ウィングス(手羽先の唐揚げ)、ミートボール、チーズプレートなどが出されることが多いです。お酒も重要な要素で、シャンパンやカクテルで新年を祝います。
「新年の朝食」には、「黒豆」を食べると幸運が訪れるという南部の伝統があります。これは「Hoppin’ John」と呼ばれる黒豆と米の料理で、新年の日に食べると一年中お金に困らないと言われています。他にも、南部では「コラードグリーン(緑の葉野菜)」を食べるとお金が増えるという言い伝えもあります。
新年に関しては、地域や家族の出身によって様々な食習慣があるのも特徴です。例えば、ドイツ系の家庭では「ポークとザワークラウト」、イタリア系の家庭では「レンズ豆」、スペイン系の家庭では「12粒のぶどう」を食べる習慣があったりします。アメリカは移民の国なので、先祖の国の伝統が家族の中で受け継がれていることが多いんです。
―アメリカでは、日本にはない休日はある? そのときに食べる特別な料理は?
「感謝祭(Thanksgiving)」は最もアメリカらしい休日で、11月の第4木曜日に祝われます。この日の食事は最も重要な伝統で、七面鳥の丸焼きがメインディッシュ。付け合わせにマッシュポテト、グレービーソース、クランベリーソース、スタッフィング(パンの詰め物)、グリーンビーンキャセロール、スイートポテトキャセロールなどが定番です。デザートはパンプキンパイやピーカンパイ。アメリカ人にとっては、この組み合わせが「感謝祭の食事」の象徴です。
「独立記念日(Fourth of July)」は7月4日に祝われ、アウトドアでのバーベキューが定番です。ハンバーガーやホットドッグ、コーンオンザコブ(トウモロコシの蒸し焼き)、ポテトサラダ、コールスローなどをグリルで調理して食べます。デザートには、アメリカ国旗をモチーフにした赤・白・青のケーキやパイ、アイスクリームなど。この日は家族や友人と外で過ごすことが多く、食事もカジュアルなスタイルが特徴です。
「スーパーボウルサンデー」は2月上旬の日曜日に行われるアメリカンフットボールの決勝戦の日です。正式な休日ではありませんが、多くのアメリカ人にとって重要な日で、友人を招いてパーティーを開くのが一般的。バッファローウィング(手羽先の唐揚げ)、ナチョス、ディップ各種(ワカモレ、サルサ、チーズディップなど)、ピザ、スライダー(ミニハンバーガー)などのフィンガーフードが定番です。この日はビールの消費量も多く、アメリカ全体で一大イベントになっています。
「セント・パトリックスデー」は3月17日に祝われるアイルランド系アメリカ人の祝日ですが、今では民族的背景に関わらず多くのアメリカ人が祝います。この日はコーンビーフとキャベツの煮込み料理が定番で、アイリッシュソーダブレッドと一緒に食べます。ビールに緑色の着色料を入れた「グリーンビール」を飲む習慣もあります。パレードや音楽イベントも開催され、緑色の服を着ることが一般的です。
「メモリアルデー」は5月最終月曜日に祝われる戦没者を追悼する日で、この日は夏のシーズン開始の合図ともされています。バーベキューやピクニックが定番で、ハンバーガー、ホットドッグ、バーベキューリブ、チキン、各種サラダ(ポテトサラダ、マカロニサラダなど)、スイカなどの夏らしい食事を楽しみます。この週末は多くの人が湖や海辺でレジャーを楽しむので、アウトドア料理が中心です。
④ アメリカの食文化の日本との違い(おふくろの味)
―アメリカで、お袋の味と言えば?日本の味噌汁やおにぎりみたいな存在は?
「マカロニ&チーズ」はまさにアメリカ版の「お袋の味」です。市販の箱入り商品もありますが、多くの家庭では自家製レシピがあり、「ママのマック&チーズが一番」と言う人が多いんです。チーズの配合やパン粉をのせるかどうか、追加する具材など、家庭ごとに違いがあります。子供の頃に風邪をひいた時や落ち込んでいる時にママが作ってくれた思い出の味として、多くのアメリカ人の心に刻まれています。
「チキンスープ」も「具合が悪い時の定番」として日本のおかゆに近い存在です。特に「チキンヌードルスープ」は風邪をひいた時に母親が作ってくれる定番の料理で、「体調を崩した時に食べると元気が出る」と言われています。市販のキャンベルスープもありますが、家庭によってはじっくり煮込んだ鶏ガラスープに野菜や麺を入れた自家製レシピがあることも。
「ミートローフ」も懐かしの家庭料理の定番です。挽肉に玉ねぎやニンジン、パン粉、卵などを混ぜて焼いた料理で、家庭によって使う肉の種類や調味料、ソースが違います。ケチャップをかけたり、グレービーソースを添えたり、マッシュポテトと一緒に出したり。「ママのミートローフが最高」と言う人も多いですね。この料理は準備は手間がかかりますが、一度に大量に作れて経済的なこともあり、働くお母さんの知恵が詰まった料理でもあります。
地域によって「お袋の味」は異なります。南部では「フライドチキン」が家庭料理の王様で、秘伝のスパイスミックスや揚げ方に家庭の味があります。中西部では「キャセロール」(具材を混ぜて焼いた料理)が一般的で、特に「ツナキャセロール」や「グリーンビーンキャセロール」などは定番の家庭料理です。イタリア系アメリカ人の多い地域では「サンデーグレービー」と呼ばれるミートソースのパスタが日曜の定番料理になっています。
「コンフォートフード」(心が温まる食べ物)という言葉もよく使われます。これらは必ずしも複雑な料理ではなく、「グリルドチーズサンドイッチ」(チーズを挟んで焼いたホットサンド)や「PB&J」(ピーナッツバターとジャムのサンドイッチ)のような簡単な料理も含まれます。大切なのは「母親が作ってくれた」という記憶と結びついていることで、忙しい日常の中で心の安らぎを与えてくれる存在なんです。
―アメリカで大人も子供も好きな定番の家庭料理って何?
「スパゲッティ&ミートボール」は世代を超えて愛される定番メニューです。トマトソースとミートボールを絡めたパスタで、ガーリックブレッドと一緒に食べることが多いです。イタリア料理がアメリカナイズされた代表的な料理で、子供から大人まで好きな人が多い、まさに「みんなの好物」です。市販のパスタソースを使う家庭もありますが、じっくり煮込んだ自家製ソースを自慢にしている家庭も多いです。
「チキンポットパイ」もアメリカの定番家庭料理です。鶏肉と野菜をクリーム系のソースで煮込み、パイ生地で覆って焼いた料理で、外はサクサク、中はクリーミーな食感が特徴です。冬の寒い日に食べると体が温まる料理として人気があり、余った鶏肉を活用できる経済的な一品でもあります。冷凍食品も多く販売されていますが、家庭の手作りレシピを持つ家族も多いです。
「タコス」や「エンチラーダ」などのメキシカン料理もアメリカの家庭料理として定着しています。特に「タコチューズデー(Taco Tuesday)」という火曜日にタコスを食べる習慣は多くの家庭で親しまれています。子供は野菜や肉を自分で好きなように包めるインタラクティブな料理として楽しみ、大人は仕事帰りの簡単な夕食として重宝しています。
「ラザニア」も特別な日の定番料理です。肉やチーズ、トマトソースを層にしたイタリアン風の料理で、一度に大量に作れることから、大家族の集まりやパーティーによく登場します。作り置きができる便利さもあり、忙しい週末の準備としてあらかじめ作っておくこともあります。子供も大人も満足できる味わい深い料理として人気です。
「マッシュポテト付きのローストチキン」も日曜の定番ディナーとして多くの家庭で親しまれています。ハーブをまぶした鶏肉をオーブンでじっくり焼き、マッシュポテトとグレービーソース、野菜の付け合わせを添えた料理です。残ったチキンは翌日のランチやサンドイッチの具材として活用される、無駄のない実用的な料理でもあります。ハードワークな一週間を終えた日曜の夕食として、家族が集まる時間を象徴する料理でもあります。
⑤ 知っておきたいアメリカの文化(その他)
―アメリカの食事で、日本人が知っておいた方がいい豆知識ってある?
「水とアイス」の文化は知っておくといいですね。アメリカのレストランでは、水に大量の氷が入っていることが当たり前です。「no ice(氷なし)」と頼まないと、グラスの半分以上が氷で埋まっていることも。また、水のおかわりは基本的に無料で、ウェイターが気づくと勝手に注ぎに来てくれます。「water with lemon(レモン入りの水)」を頼むのも一般的です。
「フリーリフィル」の文化も知っておくと便利です。多くのカジュアルレストランでは、コーヒー、紅茶、ソーダ(炭酸飲料)などが「おかわり自由」になっています。一度注文すれば何度でもおかわりできる仕組みで、空になったカップをテーブルの端に置いておくと、ウェイターが気づいて補充してくれることも多いです。
「フードアレルギーへの対応」は徹底しています。アメリカではフードアレルギーを持つ人が多く、レストランもそれに対応する体制が整っています。メニューにはアレルゲン情報が記載されていることが多く、特別なリクエスト(グルテンフリー、乳製品抜き、ナッツフリーなど)にも柔軟に対応してくれます。アレルギーがある場合は遠慮せずに伝えることが大切です。
「食事のスピード感」も日本と異なります。アメリカのレストランでは、料理が準備できた順に提供されることが一般的です。つまり、同じテーブルの人でも料理が出てくるタイミングにずれがあることもあります。また、メインディッシュを食べ終わるとすぐにデザートメニューを持ってくることも多く、全体的にテンポが速いのが特徴です。日本のように「ゆっくり食事を楽しむ」という概念よりも、「効率的に食事を済ませる」という感覚が強いかもしれません。
「カスタマイズ文化」も特徴的です。アメリカでは料理を自分好みにカスタマイズするのが当たり前です。「ドレッシングは別添えで」「パンの代わりにサラダに変更」「ソースを追加」など、細かいリクエストをすることが一般的で、レストラン側もそれに対応する体制が整っています。日本では「メニュー通りに提供される」ことが多いですが、アメリカでは「自分の好みに合わせる」ことが重視されています。
まとめ
アメリカの食文化を知ることで、「多様性」「実用性」「効率」を重んじるアメリカ社会の価値観が見えてきます。大量のポーションサイズ、持ち帰り文化、早めの夕食時間、食事の高速回転など、一見すると「食を楽しむ」というよりも「効率的に栄養を摂る」感覚が強いように思えます。
しかし同時に、感謝祭やクリスマスなどの行事食には強いこだわりがあり、家族の伝統レシピが大切に受け継がれています。「マック&チーズ」や「チキンスープ」といった「お袋の味」も、アメリカ人の心の拠り所となっています。また、週末のブランチや友人とのバーベキューなど、食を通じたコミュニケーションの場も大切にされています。
日本の食文化が「繊細さ」「見た目の美しさ」「季節感」を重視するのに対し、アメリカの食文化は「ボリューム」「実用性」「多様性」「自己表現(カスタマイズ)」を重視する傾向があります。どちらが優れているということではなく、それぞれの文化的背景や価値観を反映した食文化として、相互理解を深めることが大切ではないでしょうか。
アメリカの食文化の特徴を知っておくことで、実際に訪れた際のカルチャーショックも軽減されますし、現地の人々との食事を通じたコミュニケーションもより楽しめるようになるでしょう。ぜひ、この記事で紹介した「アメリカの食文化の日本との違い」を参考に、アメリカでの食の体験を満喫してください。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。