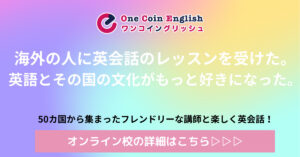【フィリピンの文化を学ぶ!】フィリピンの食文化の日本との違い5選 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

フィリピンってどんな国? 日本からのイメージ
フィリピンといえば、多くの日本人が思い浮かべるのは美しい白砂のビーチ、透明度の高い海、そして陽気でフレンドリーな人々ではないでしょうか。セブ島やボラカイ島などのリゾート地は日本人観光客にも人気の高い旅行先です。
また、英語留学先としてのイメージも定着しており、比較的リーズナブルな費用で英語を学べる環境として選ばれています。近年では日本企業の進出や経済連携の強化により、フィリピン人労働者の受け入れも増加し、日常的に接する機会も増えてきました。
しかし、7,641もの島々からなるこの国の文化や生活は、観光で訪れただけでは知ることができない豊かな多様性を持っています。スペイン、アメリカ、そして日本など様々な国の影響を受けながらも、独自の文化を育んできたフィリピンの魅力は、少し掘り下げるとより一層深く理解できるでしょう。
フィリピンで暮らす/フィリピンに行くメリットについて
フィリピンに滞在するメリットは数多くあります。まず、生活コストの安さは大きな魅力です。食事、住居、交通費など基本的な生活費は、日本に比べると格段に安く済ませることができます。特に地方都市では、なおさら生活費を抑えることが可能です。
また、英語が公用語の一つであるため、言語の壁が比較的低いことも大きなメリットです。日常生活やビジネスで英語が広く使われているため、英語さえある程度できれば、生活に困ることはほとんどありません。また、滞在しながら自然と英語力も向上するという好循環も期待できます。
気候も一年中温暖で、常夏の環境を楽しめます。特に寒さが苦手な方には、冬の厳しい寒さがない環境は魅力的でしょう。
さらに、フィリピン人の温かい人柄や家族を大切にする文化に触れることで、日本では失われつつある人とのつながりの大切さを再認識する機会にもなります。物質的な豊かさだけでなく、心の豊かさを感じられる環境がそこにはあります。
それでは、フィリピンの食文化について、日本との違いを詳しく見ていきましょう。

① フィリピンの食文化の日本との違い(食事)
フィリピンで驚いた食事ってある?
フィリピン料理で最初に驚くのは、甘さと酸っぱさ、そして塩気が同時に楽しめる独特の味付けですね。例えば「アドボ」という代表的な料理は、肉や魚を酢、醤油、砂糖などで煮込んだもので、一見矛盾するような味が見事に調和しています。日本料理は繊細で個々の味を大切にする傾向がありますが、フィリピン料理は大胆な味の組み合わせが特徴です。
また、「バロット」という発育途中のアヒルの卵を茹でたものは、見た目のインパクトが強く、多くの日本人を驚かせます。現地では栄養価が高いおやつとして親しまれていて、特に夕方になると「バロット!バロット!」と売り歩く声が街に響きます。勇気を出して食べてみると、卵黄の濃厚さと独特の風味があり、意外と美味しいと感じる方も多いですよ。
食事の時間帯も日本とは大きく異なります。朝食は6時頃から、昼食は12時から13時の間、そして夕食は比較的遅く、18時から20時頃に食べるのが一般的です。また、「メリエンダ」という間食の習慣があり、午前10時頃と午後3時頃に軽食を取ります。この習慣はスペインの影響で、小腹が空いたときに何か食べるという文化が根付いています。
食べ方にも違いがあります。フィリピンでは「カマヤン」と呼ばれる素手で食べる文化があり、特にレチョン(豚の丸焼き)などは手で直接食べるのが一般的です。もちろんフォークとスプーンを使うこともありますが、ナイフはあまり使いません。代わりにスプーンの端を使って食べ物を切る独特のスタイルがあります。
フィリピンで買い物の仕方や買ったもので驚いたことってある?
フィリピンでの食材の買い物は、日本とはかなり異なる体験になります。まず、「ウェットマーケット」と呼ばれる市場では、魚や肉が氷なしで売られていることがあり、最初は衛生面で心配になる日本人も多いですね。しかし地元の人々は新鮮さを見極める目を持っていて、朝早く行けば最も新鮮な食材を手に入れることができます。
また、「サリサリストア」と呼ばれる小さな個人商店が町のあちこちにあり、調味料や缶詰などの食品が小分けにして売られています。例えば、シャンプーやコンディショナー、醤油や酢なども小さなビニール袋に入れて販売されているのが特徴的です。これは、日々の収入で生活する人々が必要な分だけ購入できるようにという配慮からきています。
フルーツの種類と安さには驚かされます。マンゴー、バナナ、パパイヤなどの熱帯フルーツが非常に安価で手に入り、日本では見かけない「ランソネス」「ランブータン」「ドラゴンフルーツ」などの珍しいフルーツも日常的に食べられています。特にマンゴーの甘さと香りは格別で、日本で食べるものとは比較にならないほど美味しいと感じる方が多いです。
スーパーマーケットでは加工食品の甘さに驚くことも。フィリピン人は甘いものが好きで、スパゲッティソースやパンなど、日本人の感覚では「これはデザートでは?」と思うほど甘い味付けのものが多いです。特に「ジョリビー」というファストフードチェーンのスパゲッティは、甘いトマトソースにホットドッグが入った独特の味わいで、フィリピン人に大人気です。
②フィリピンの食文化の日本との違い(会話)
フィリピンでは、食事のときに何について話すことが多い?
フィリピン人の食卓では、会話が絶えることはありません。まず、食べている料理についての会話が多いですね。「この料理美味しいね」「このソースには何が入っているの?」といった食べ物自体についての話題から自然と会話が広がります。日本では「食事中はあまり話さない」という文化もありますが、フィリピンでは食事と会話は切っても切れない関係なんです。
家族や親戚の近況についての話題も定番です。誰が結婚したとか、誰が赤ちゃんを産んだとか、誰が新しい仕事を始めたといった話が飛び交います。フィリピン人は家族の絆を非常に大切にするので、親戚の細かい情報まで把握していることが多いんです。
また、テレビドラマの最新話やセレブのゴシップ話も人気の話題です。フィリピンではテレノベラ(連続ドラマ)が非常に人気で、その展開について熱く議論することも。政治の話も意外と多く、特に選挙の時期になると白熱した議論が交わされることもあります。
面白いのは、まだ目の前の食事を楽しんでいる最中なのに、「次の休みには〇〇を食べに行こう」など、次の食事の計画についても話し合うことです。フィリピン人の「食」への情熱を感じる瞬間ですね。
日本との食事中のマナーの違いってある?
フィリピンと日本の食事マナーには興味深い違いがたくさんあります。まず、フィリピンではキリスト教の影響から、食事の前に「祈り」を捧げる家庭が多いです。これは特に家族の集まりや特別な日の食事の際に行われ、食べ物に感謝する意味があります。
また、フィリピンでは食事中の会話が賑やかなことが良いとされるのに対し、日本では「静かに食べる」「食事中は大声で話さない」といったマナーがありますよね。フィリピンの食卓は笑い声が絶えず、時には大きな声で意見を交わすこともあります。
食事の順番にも違いがあります。日本では「いただきます」と言って全員同時に食べ始めますが、フィリピンでは目上の人や来客が最初に食べ始め、その後他の人も食べるという順序があります。また「どうぞお召し上がりください」と何度も勧められるまで食べ始めないのも礼儀とされています。
食事の早さも異なります。日本では「食事は丁寧に、でもあまり時間をかけすぎない」という感覚がありますが、フィリピンの食事は社交の場でもあるため、ゆっくりと時間をかけて楽しみます。1〜2時間かけて食事をすることも珍しくなく、特に休日の昼食などはその後のお昼寝(シエスタ)につながることも多いです。
もてなしの文化も特徴的です。フィリピンではゲストに「もっと食べて」と何度も勧め、断られても繰り返し勧めることがマナーとされています。これは「パキキサマ」という相手を思いやる概念から来ています。日本では相手の意思を尊重して「いいです」と言われたら勧めるのをやめることが多いので、この違いに戸惑う方も多いですね。
③ フィリピンの食文化の日本との違い(記念日/祝日)
フィリピンでは、クリスマスや新年はどう過ごす?
フィリピンのクリスマスは世界一長いと言われるほど大切な行事です。なんと9月から装飾が始まり、クリスマスソングが流れ始めるんですよ。カトリック国であるフィリピンでは、12月16日から24日までの9日間、「シンバン・ガビ」という早朝ミサが行われ、多くの人が参加します。
クリスマスイブの夜には「ノチェブエナ」と呼ばれる特別な夕食を家族で楽しみます。定番メニューはハモン(ハム)、ケソ・デ・ボラ(赤いワックスで覆われたチーズ)、そしてさまざまなフィリピン料理です。特に「レチョン」(豚の丸焼き)がお祝いの食卓の中心となることが多いです。また、デザートとして「ビビンカ」や「プト・ブンボン」といった伝統的な米菓子も欠かせません。
午前0時になると家族で贈り物を交換し、子供たちはゴッドペアレント(洗礼の際の代父母)を訪ねて「アギナルド」というクリスマスプレゼントをもらいます。家族や親戚だけでなく、友人や近所の人たちと集まってパーティーを開くこともあり、食べ物と飲み物を分かち合いながら夜通し楽しむこともあります。
新年(バゴン・タオン)には独特の風習があります。丸い形の果物を12種類用意したり(一年の円満と繁栄を願って)、ポケットに小銭を入れて飛び跳ねたり(お金が増えるように)、派手な音を立てて悪霊を追い払ったりします。食べ物としては「メディアノチェ」(真夜中の食事)で「パンシット」(長寿を象徴する長い麺料理)を食べる習慣があります。
日本のお節料理のように特別なメニューが決まっているわけではありませんが、家族で集まって豪華な食事を楽しむという点では共通していますね。ただ、フィリピンの新年はクリスマスほど大々的には祝われず、むしろクリスマスシーズンの延長という感覚です。
フィリピンでは、日本にはない休日はある?そのときに何をする?
フィリピンには日本にはない独特の祝日がいくつかあります。まず「ホーリーウィーク」(聖週間)は、イースター(復活祭)前の一週間で、特に木曜日から土曜日は「タナン・バイエルネス」(聖金曜日)を中心に多くの企業や学校が休みになります。この期間は宗教的な意味が強く、信仰深い人々は肉を食べず、魚や野菜を中心とした質素な食事をします。特別な料理としては「ビニンラグ」(小麦粉のスープ)や「プルサ」(いろいろな豆とバナナの入った甘いスープ)などがあります。
また、「ウンダス」(万霊節・11月1日と2日)も重要な休日です。この日には故人を偲び、家族で墓地を訪れます。一見悲しい行事に思えますが、実際は家族の再会の機会でもあり、墓地で食事を共にし、故人の思い出話に花を咲かせます。この日には特に「ビビンカ」「プト・ブンボン」といった伝統的なお菓子やスナックを持参することが多いです。
地域ごとの「フィエスタ」も重要な休日です。町や村の守護聖人を祝うこのお祭りでは、家々が食べ物を用意し、訪問者をもてなす「オープンハウス」の習慣があります。見知らぬ人でも招き入れて食事を振る舞うのがフィエスタの特徴で、「レチョン」(豚の丸焼き)や「パンシット」(焼きそば)、「ルンピア」(春巻き)などのごちそうが並びます。
「シヌログ・フェスティバル」(セブ)や「アティ・アティハン」(カリボ)といった地方ごとの祭りも豪華な食事と踊りで彩られます。参加者はお互いの家を訪問し合い、用意された料理を楽しみながら交流を深めます。
フィリピンで記念日に食べる特別な食事ってある?
フィリピンには様々な記念日や祝日があり、それぞれに特別な料理があります。まず誕生日には「パンシット」(フィリピン風焼きそば)が欠かせません。長い麺は長寿のシンボルとされ、お祝いの席には必ず登場します。特に子供の誕生日には「スパゲッティ」も人気ですが、フィリピン風スパゲッティは甘いソースとホットドッグが入った独特の味わいです。
結婚式では「レチョン」(豚の丸焼き)が主役です。丸ごと一頭の豚を串刺しにして回転させながら炭火で焼き上げるこの料理は、特別な日のごちそうとして欠かせません。また、「アドボ」(肉や魚を酢とニンニクで煮込んだ料理)、「カレカレ」(牛肉とピーナッツソースの煮込み)、「メヌード」(豚肉と野菜のスープ)なども祝いの席の定番料理です。
洗礼式(バプティズム)では、「ビビンカ」(ココナッツミルクと米粉で作るケーキ)や「プト・ブンボン」(蒸した米のケーキ)などの伝統的なお菓子が振る舞われます。
「フィエスタ」(町の守護聖人を祝う祭り)では、各家庭が料理を用意し、訪問者をもてなします。この時には特に豪華な食事が用意され、普段はあまり食べられない高価な食材を使った料理が並びます。
また、「カエサルサラド・デイ」といった地域特有のお祭りもあります。これはバンガシナン州バウアンでの祭りで、世界最大のシーザーサラダを作ることでギネス記録を達成したことから始まりました。このように食べ物にまつわるお祭りも数多くあり、フィリピンの食文化の豊かさを表しています。
④ フィリピンの食文化の日本との違い(おふくろの味)
フィリピンで、お袋の味と言えば?
フィリピンの「お袋の味」として最も代表的なのは「シニガン」でしょう。タマリンドの酸味が特徴的なスープで、魚や豚肉、さまざまな野菜が入った料理です。各家庭によって酸味の強さや具材の組み合わせが異なり、まさに「母の味」として親しまれています。風邪を引いた時などに母親が作ってくれた思い出がある人も多いですね。
また、「アドボ」も定番の家庭料理です。肉や魚を酢、醤油、ニンニクで煮込んだ料理で、冷蔵庫のない時代に保存食として発展しました。シンプルな調味料ながらも深い味わいがあり、各家庭独自のレシピがあります。「母のアドボは特別」と言うフィリピン人は本当に多いですよ。
「カレカレ」も伝統的な家庭料理で、牛や豚のスネ肉をピーナッツソースで煮込んだ料理です。長時間煮込むため手間がかかりますが、その分愛情が感じられる一品です。祖母から母へ、母から娘へと受け継がれるレシピも多く、家族の歴史が詰まった料理とも言えます。
「ティノラ」(チキンスープ)も多くの家庭で作られる定番料理です。鶏肉と青パパイヤを煮込んだシンプルなスープですが、風邪をひいた時や体調が優れない時に母親が作ってくれる料理として特別な意味を持っています。
また、「シニガンサ・ミソ」(味噌を入れた酸っぱいスープ)など、地域や家庭ごとの特色ある料理もあります。これらの料理は、単なる食べ物以上の意味を持ち、家族の絆や母親の愛情を象徴する重要な文化的要素となっています。
日本とフィリピンの家庭料理の共通点や違いは?
日本とフィリピンの家庭料理には興味深い共通点と違いがあります。まず共通点として、どちらも米を主食としていることが挙げられます。毎日の食卓に欠かせない存在であり、料理と一緒に米を食べる習慣は両国で共通しています。ただ、フィリピンのお米は日本のものより少し粘り気が少なく、パラッとしています。
また、魚や海産物を多く使う点も共通しています。島国である両国は豊かな海の幸に恵まれており、それを活かした料理が発達しました。しかし調理法には違いがあり、日本では生で食べることも多いのに対し、フィリピンではほとんど加熱調理します。
大きな違いとしては味付けの考え方があります。日本料理は素材本来の味を活かすことを重視し、繊細で控えめな味付けが特徴です。一方、フィリピン料理は味の主張が強く、特に甘さ、酸味、塩気のバランスが独特です。例えば日本の焼き魚が塩だけのシンプルな味付けなのに対し、フィリピンの「イナサル・ナ・イスダ」(魚のグリル)は酢やカラマンシー(柑橘類)、醤油などを使った複雑な味わいになります。
調理器具も異なります。日本では包丁の種類が多く、料理ごとに適した包丁を使い分けますが、フィリピンでは「ボロ」と呼ばれる多目的な大きなナイフが一般的です。また、日本は炊飯器が普及していますが、フィリピンでは昔ながらの「パラヤン」(土鍋)で米を炊く家庭もまだ多いです。
もう一つの違いは「もてなし」の文化です。日本では「おもてなし」として見た目の美しさ、繊細さを重視しますが、フィリピンでは量の多さ、味の濃さで歓迎の気持ちを表します。ゲストには常に「もっと食べて」と勧め、食べ物が余るほど用意するのがマナーとされています。
⑤ 知っておきたいフィリピンの文化(その他)
フィリピン人に人気の観光地はどこ?
フィリピン人に人気の国内観光地で、外国人観光客があまり訪れないスポットとしてまず挙げられるのは「バタネス」です。台湾との間に位置する最北端の島々で、独特の石造りの家屋や牧歌的な風景が魅力です。強風に耐えるため厚い石壁で建てられた家々は「イヴァタン様式」と呼ばれ、フィリピン国内でも独特の建築文化として注目されています。ここでは、羊と緑の草原が広がる風景を見たり、地元の料理「ウヴド」(フライドフィッシュボール)や「ビヤヨス」(バタネス特有の小型魚の干物)を味わったりできます。
「アンティケ州」も地元民に人気のスポットです。特に「マラライソン島」は「小さなボラカイ」とも呼ばれる美しい島で、まだ商業的な開発が進んでいないため、静かで自然豊かな環境を楽しめます。島では新鮮なシーフードバーベキューを楽しんだり、地元の漁師から直接購入した魚で作る「キニラウ」(シーバスのセビチェ)を味わったりすることができます。
「ソルソゴン州」にある「ドンソル」も地元民のお気に入りスポットです。ここではジンベイザメとのスイミングが体験でき、比較的リーズナブルな価格で世界的にも貴重な体験ができます。地元で人気の料理としては「ラプランピア」(エビのスプリングロール)や「キニュノブ・ナ・プソ」(ココナッツミルクで煮込んだカタツムリ)などがあります。
また、「ビコル地方」は「ラグスピ」や「レガスピ」の町を中心に、完璧な円錐形のマヨン山の絶景や温泉を楽しめるスポットとして人気です。ここでは「ビコル・エクスプレス」という地元料理が有名で、チリで激辛に味付けした料理です。辛いものが好きな方にはたまらない一品ですよ。
フィリピン人に人気のレストランってどんなところ?
フィリピン人に人気のレストランは、外国人観光客があまり知らないような地元の人々のお気に入りの場所が多いです。まず「カリンデリア」と呼ばれる大衆食堂が日常的な食事に利用されています。ガラスケースに色とりどりの料理が並び、好きなおかずを選んでご飯と一緒に食べるスタイルです。特に「ジョリーノン」や「テレシータズ」といった老舗の店は地元の人々で連日賑わいます。ここでは「パーク・シニガン」(豚肉の酸っぱいスープ)や「モンゴ」(緑豆のスープ)など家庭的な味を楽しめます。
「イナサル」専門店も地元で人気です。「イナサル」とは肉や魚を特製のマリネ液に漬け込んでグリルした料理で、特にイナサル・ナ・マノク(グリルチキン)は多くのフィリピン人が大好きな料理です。バコロド市の「マノク・カントリー」やイロイロ市の「アフリタダ」などは地元の人々の間で評判のイナサル店です。
シーフードレストランも人気があります。特にパラワン島のプエルト・プリンセサにある「バジャク・シーフード」や、セブ島の「ラントー・ン・バルボン」では、新鮮な海の幸をリーズナブルな価格で楽しめます。「キニラウ」(生の魚をお酢とスパイスで和えた料理)や「シニガン・ナ・ヒポン」(エビの酸っぱいスープ)など、地元ならではのシーフード料理が味わえます。
また、スペイン統治時代の影響を受けた「スパニッシュ・フィリピン料理」を提供するレストランも人気です。マニラの「アリパタ」やダバオの「クララスキッチン」では、「カルデレータ」(トマトベースのシチュー)や「メヌード」(臓物入りのスープ)など、スペインとフィリピンの味が融合した料理を楽しめます。
さらに、伝統的なフィリピン料理を現代的にアレンジした「モダン・フィリピン料理」のレストランも最近人気を集めています。マニラの「センスム」やマカティの「ロカル」などでは、伝統的な味を大切にしながらも、洗練された盛り付けや新しい調理法を取り入れた料理を提供しています。「アドボ・サ・ギャータ」(ココナッツミルクで煮込んだアドボ)や「カレカレ・コロケッテ」(ピーナッツソースの牛肉料理をコロッケにアレンジ)など、創造的な一品が楽しめます。
これらのレストランに共通するのは、観光客向けに味を調整せず、フィリピン人好みの本格的な味を提供していることです。地元の人々に混じって食事をすることで、より本物のフィリピン食文化を体験できるでしょう。
まとめ
フィリピンの食文化は、その歴史と多様な文化的影響を反映した豊かなものです。スペイン、中国、アメリカ、そして日本など様々な国の影響を受けながらも、独自の発展を遂げてきました。日本との大きな違いは、味の組み合わせの大胆さ、食事を通じたコミュニケーションの重視、そして家族や地域社会との絆を深める手段としての食事の位置づけにあるでしょう。
フィリピン料理を味わうことは、単に異国の味を体験するだけでなく、フィリピンの人々の価値観や生活様式を理解する窓口となります。特に家庭料理には、母から娘へと受け継がれる知恵と愛情が詰まっており、その国の本当の姿を映し出すものとなっています。
また、記念日や祝日の特別な料理を通じて、フィリピン人がどのような瞬間を大切にし、どのように祝うかを知ることができます。クリスマスや地域のフィエスタなどの祝祭は、食を通じて人々が集い、絆を深める重要な機会となっています。
フィリピンへの留学や旅行を考えている方は、ぜひ観光地だけでなく地元の人々が通うレストランや市場を訪れ、本物のフィリピン食文化を体験してみてください。言葉の壁を超えて、食を通じた交流は、より深い異文化理解につながるでしょう。
食べ物に対するオープンな気持ちと少しの冒険心さえあれば、フィリピンの食文化は皆さんに新しい発見と喜びをもたらしてくれるはずです。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。