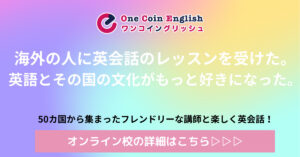【日本在住イタリア人に聞いた!】知っておきたいイタリアの文化 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

【日本在住イタリア人に聞いた!】知っておきたいイタリアの文化 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~
グローバル化が進む現代社会では、異なる文化への理解が私たちの視野を広げ、新たな価値観との出会いをもたらしてくれます。日本人にとって当たり前のことが、海外では全く違う意味を持つように、イタリアの文化や習慣は私たち日本人に新しい発見を与えてくれるでしょう。
本記事では、日本在住のイタリア人にインタビューを行い、イタリアの文化や習慣について詳しく聞いてみました。留学や長期滞在、移住を考えている方はもちろん、旅行者の方にも参考になる情報をお届けします。
イタリアってどんな国? 日本からのイメージ
ピザ、パスタ、ジェラート、エスプレッソ、フェラーリ、ヴェネツィア、コロッセオ…皆さんはイタリアと聞いて、どんなイメージを持ちますか?
イタリアは南ヨーロッパに位置する「長靴の形」の国で、地中海性気候に恵まれた温暖な環境が特徴です。北部のアルプス山脈から南部のシチリア島まで、地形も文化も多様性に富んでいます。国土は日本の約8割程度ですが、世界遺産の数は世界最多を誇り、古代ローマ帝国からルネサンス期の芸術、現代のファッションやデザインまで、世界の文化に計り知れない影響を与えてきました。
現代のイタリアは20の州(レジオーネ)から構成される共和国で、それぞれが固有の伝統や特色を持ちます。北部は経済的に発展した工業地帯、中部はローマやフィレンツェなど歴史的・文化的中心地、南部は農業が盛んな地域と、地域によって特徴が大きく異なります。
イタリア人は「ドルチェ・ヴィータ(甘い生活)」という言葉に象徴されるように、生活の質や喜びを重視する文化を持っています。家族との絆を大切にし、食事や会話を楽しみ、情熱的で表現力豊かなコミュニケーションが特徴です。実用性や効率よりも美しさや味わいを優先する価値観は、現代のスピード社会に生きる私たちに新しい視点を与えてくれるかもしれません。
イタリアで暮らす/イタリアに行くメリットについて
メリット1:食文化の豊かさ
イタリアでは「食」が単なる栄養摂取ではなく、生活文化の中心です。地域ごとに異なる郷土料理があり、新鮮な地元産の食材を使った料理からワイン、チーズ、オリーブオイルまで、味覚の宝庫と言えます。また、食事の時間は家族や友人との交流の場でもあり、ゆっくりと会話を楽しみながら食べる文化があります。「スローフード運動」が生まれた国として、食の品質や伝統を大切にする姿勢は、現代の加工食品や「時短」優先の食生活に対するアンチテーゼとなっています。食に関する季節のイベントやフェスティバルも多く、一年を通して様々な味覚体験が可能です。
メリット2:芸術と歴史に囲まれた生活
イタリアでは日常的に芸術や歴史的建造物に触れることができます。街を歩けばルネサンス期の教会やバロック様式の噴水、エトルリア時代の遺跡など、様々な時代の文化遺産を目にします。世界的に有名な美術館や博物館だけでなく、小さな町にある教会の中にも素晴らしいフレスコ画が眠っていることも少なくありません。このような環境で過ごすことは、自然と美的感覚や歴史への理解を深めることにつながります。また、古いものと新しいものが共存する街並みは、時間の流れの中で文化がどのように発展していくかを実感させてくれます。
メリット3:生活のリズムとバランス
イタリアでは「仕事のために生きるのではなく、生きるために働く」という価値観が根づいています。昼休みが長く取られ「リポーゾ(休息)」の時間が尊重されることや、家族との食事の時間が確保されていることは、ワークライフバランスの良さを示しています。また、気候が良いこともあり、カフェのテラスでエスプレッソを飲んだり、広場でのんびり過ごしたりと、屋外での活動や社交の機会が多いのも特徴です。スローなライフスタイルは時に「非効率」と思われることもありますが、ストレスや疲労の少ない持続可能な生活リズムとも言えるでしょう。
メリット4:表現力豊かなコミュニケーション
イタリア人は感情表現が豊かで、言葉だけでなく身振り手振りを交えて会話する文化があります。この開放的でダイレクトなコミュニケーションスタイルは、人間関係の構築に役立ちます。初対面でも気さくに話しかけてくる人が多く、すぐに打ち解けられる環境です。また、議論や意見交換が日常的に行われ、異なる視点を交換し合うことが文化的に価値あるものとされています。このようなコミュニケーション文化は、特に日本人のような控えめな自己表現に慣れた人にとって、新たな自己発見や表現力の向上につながるかもしれません。
① 知っておきたいイタリアの文化(歴史)
―日本人が知らずにびっくりされたイタリアの歴史ってある?
イタリアという「国」が誕生したのは意外と新しくて、1861年なんです。それまではいくつもの小さな国や都市国家に分かれていたんですよ。「リソルジメント(統一運動)」と呼ばれる国民統一の動きがあって、ようやく一つの国になりました。イタリア人ですら「イタリア人」というアイデンティティを持つようになったのは比較的最近のことで、それまでは「フィレンツェ人」「ナポリ人」「ヴェネツィア人」というように、自分の生まれた都市や地域への帰属意識の方が強かったんです。今でもイタリア各地域の文化や方言の違いが大きいのは、こうした歴史的背景があるからなんですね。
古代ローマ帝国の広がりにも驚かれることが多いです。ローマ帝国の全盛期には、現在のイタリアだけでなく、イギリス、フランス、スペイン、北アフリカ、中東の一部まで支配下にありました。今でもこれらの地域には「凱旋門」や「コロッセオ」のような古代ローマ建築が残っています。例えばフランスのアルル、トルコのエフェソス、チュニジアのエル・ジェムなど、イタリア以外の場所にも立派なローマ時代の遺跡があるんです。ローマ帝国は単に領土を広げただけでなく、法制度、道路網、水道システム、建築技術など、現代社会の基礎となる多くのものを生み出しました。例えば「コンクリート」はローマ人が発明したものですし、「カレンダー」の原型も作りました。
「ルネサンス」に関する誤解も多いですね。多くの人が「ルネサンス」を芸術運動と考えていますが、実際にはもっと包括的な文化革命でした。「ウマネジモ(人文主義)」と呼ばれる思想運動があり、人間の可能性や個性を重視する考え方が生まれました。フィレンツェのメディチ家のような裕福な商人や銀行家たちがパトロンとなり、学問や芸術を支援したことも大きな要因です。ルネサンスの時代には芸術だけでなく、科学、文学、哲学、建築など様々な分野で革新的な発展がありました。ダ・ヴィンチやガリレオのような人物は芸術家であると同時に科学者でもあったんです。この時代の「万能人」(ウオモ・ウニヴェルサーレ)という理想は、専門分野を細分化する現代の考え方とは大きく異なりますね。
イタリアの「都市計画」の歴史も興味深いです。ローマやフィレンツェ、シエナなどの歴史的な都市は、何世紀にもわたって計画的に発展してきました。例えば、多くの都市の中心にある「ピアッツァ(広場)」は、単なる空間ではなく、社会生活の中心として機能するように設計されています。宗教的な建物(教会や大聖堂)、政治的な建物(市庁舎)、経済活動の場(市場)が広場を囲むように配置され、市民が集まり、交流するための場所となっています。この「人間中心」の都市設計の考え方は、現代の都市計画にも影響を与えています。日本の都市が交通や効率を中心に発展してきたのとは対照的に、イタリアの都市は「人間の活動や交流」を中心に発展してきたという違いがあるんです。
―日本人にびっくりされたイタリアの習慣はある?
「挨拶のキス」の文化には多くの日本人が驚きます。イタリアでは友人や家族、時には初対面の人とも頬にキスをして挨拶することが一般的です。通常は左頬、右頬の順に軽く頬を触れ合わせるだけですが、地域によっては片方だけ、あるいは3回キスする場所もあります。これは決して親密な行為ではなく、普通の社交の一部なんです。日本のようにお辞儀をする文化からすると身体的な距離感が近すぎると感じるかもしれませんが、イタリア人にとっては自然なコミュニケーションの形です。同性同士でも行うので、初めて経験する日本人男性は特に戸惑うことが多いようですね。
「ジェスチャー」の豊富さと重要性も特徴的です。イタリア人の会話では、手や顔の表情を使った身振り手振りが言葉と同じくらい、時にはそれ以上に重要な意味を持ちます。例えば、指先を集めて上に向け「マ・ケ・ヴォイ?(一体何を言ってるの?)」というジェスチャーや、指で頬をこすりながら「ブオーノ!(美味しい!)」と表現するジェスチャーなど、数十種類もの特徴的な動作があります。これらは単なる装飾ではなく、言葉の意味を強調したり、時には言葉を置き換えたりする重要なコミュニケーションツールです。実際、離れた距離でもジェスチャーだけでやりとりをしているイタリア人を見かけることもあります。この表現の豊かさは、感情や考えをより鮮明に伝える手段として機能しています。
「リポーゾ(昼休み)」の文化も日本人には新鮮です。特に小さな町や南部では、午後1時から4時頃までの間、多くの店やオフィスが閉まり、人々は昼食を食べて休息する時間を取ります。この時間帯は気温が高くなる夏場には特に重要で、涼しい室内で休むことで体力を温存します。都市部や観光地では徐々に変化してきていますが、この「昼休みの習慣」は今でもイタリア人の生活リズムの重要な一部です。日本のように昼食を短時間で済ませて仕事に戻るのではなく、ゆっくりと食事をして、場合によっては短い昼寝(ピソリーノ)をとることもあります。この習慣は「生産性」や「効率」よりも、人間の自然なリズムや生活の質を重視する価値観の表れと言えるでしょう。
「パッセジャータ(散歩)」の習慣も独特です。特に週末の夕方になると、人々はドレスアップして町の中心部や海辺のプロムナードを歩きます。これは単なる運動ではなく、社交の機会でもあります。友人や知人に会えば立ち止まっておしゃべりをし、カフェに寄ってコーヒーを飲んだり、ジェラートを食べたりします。若者にとっては異性と知り合う機会にもなります。この習慣は特に小さな町で強く残っており、「コルソ」と呼ばれるメインストリートが社交の中心になることも多いです。スマートフォンやSNSが普及した現代でも、この「顔と顔を合わせる」直接的な交流の場が大切にされています。
「カフェ文化」も日本との大きな違いです。イタリアでは朝食を家で取らず、近所の「バール」に立ち寄ってカウンターでエスプレッソとコーナ(クロワッサン)を素早く食べるのが一般的です。また、一日に何度も短時間バールに立ち寄り、エスプレッソを立ったまま飲む習慣があります。日本のカフェのように長時間座ってくつろぐ場所ではなく、短時間の「社交と活力補給」の場というのが伝統的なイタリアのバールの使い方です。「カフェ・アル・バンコ(カウンターでのコーヒー)」と「カフェ・アル・タヴォロ(テーブルでのコーヒー)」では価格が異なり、座る場合は立って飲むよりも高い料金を払うのが一般的です。この文化は忙しい毎日の中で短い社交の時間を大切にする知恵とも言えるでしょう。
② 知っておきたいイタリアの文化(コミュニケーション)
―イタリア人のコミュニケーションで、日本と違うなーと思うポイントは?
「声の大きさと表現力」がまず目立つ違いです。イタリア人は通常、日本人よりもずっと大きな声で話し、感情を声のトーンや抑揚に乗せて表現します。日本人からすると「怒っている」「興奮している」ように聞こえることもありますが、イタリア人にとっては普通の会話の一部です。特に複数人での会話では、全員が同時に話し、声を張り上げてでも自分の意見を通そうとすることも珍しくありません。この「カオスに見える会話」も、実はイタリア人は上手く聞き分けています。静かに順番を待って話す日本のコミュニケーションスタイルとは対照的ですね。この表現の豊かさは単に「うるさい」というわけではなく、感情や考えをありのままに表現する文化的特徴なんです。
「議論を楽しむ文化」も特徴的です。イタリア人は政治、サッカー、食べ物など様々なトピックについて活発に意見を述べ、議論することを好みます。これは単なる「言い争い」ではなく、「社交的な知的活動」と捉えられています。異なる意見を持つことは問題ではなく、むしろ会話を豊かにする要素と考えられています。日本の「和を大切にする」文化とは対照的に、意見の衝突を恐れず、むしろそれを楽しむ傾向があります。ただし、この「議論」はあくまで友好的なもので、相手の人格を否定するものではありません。議論の後でも変わらず友情を保てるのがイタリア人のコミュニケーションの特徴です。
「率直さ」もイタリア人コミュニケーションの特徴です。日本人が「空気を読む」ことや「建前と本音」を使い分けることに対し、イタリア人は比較的ストレートに自分の意見や感情を表現します。例えば料理が口に合わなければはっきり言いますし、ファッションについての率直な感想も述べます。これは失礼にあたるのではなく、むしろ「正直であること」が相手への敬意と考えられています。もちろん攻撃的な言い方はせず、ユーモアを交えたり、状況に応じた表現を選んだりする繊細さもありますが、基本的には「思ったことをそのまま言う」文化です。この率直さは時に日本人には厳しく感じられることもありますが、関係性が明確になり誤解が少ないというメリットもあります。
「プライベートな質問」への態度も異なります。イタリア人は初対面でも比較的個人的な質問(結婚しているか、子供がいるか、収入はどれくらいかなど)をすることがあります。これは単なる好奇心からではなく、相手をよく知りたいという親しみの表れでもあります。日本では失礼に当たると考えられる質問でも、イタリアではむしろ「関心を示している」と肯定的に捉えられることが多いです。もちろん、答えたくない質問には答えなくても良いのですが、イタリア人の「オープンさ」は人間関係を早く築くのに役立つことも多いです。
「身体的距離感」も大きく異なります。イタリア人は会話する時の距離が日本人よりも近く、相手の腕に触れたり、肩を抱いたりといった身体的接触も自然に行います。これは親しみを表現する方法で、決して無礼や不適切な行為ではありません。電車やバスでも、日本のように「できるだけ距離を取る」という発想はなく、むしろ知らない人同士でも会話が始まることも珍しくありません。公共の場が潜在的な社交の場にもなっているのです。こうした近い距離感は、イタリア人がコミュニケーションの中で「人間的な温かさ」を重視していることの表れと言えるでしょう。
―イタリア人が日本人の行動で驚くことってある?
「遠慮がちな態度」には多くのイタリア人が戸惑います。日本人がはっきりと意見を言わなかったり、「いいえ」と直接言わず婉曲的な表現を使ったりすることは、イタリア人には理解しづらいことが多いです。例えば、日本人が「ちょっと難しいかもしれません」と言った場合、イタリア人は「難しいけどやってみる」と解釈してしまうことがありますが、実際は「できません」という意味だったりします。また、レストランで料理に不満があっても何も言わない日本人の姿は、イタリア人には不思議に映ります。イタリア文化では「正直に自分の意見を述べる」ことが相手への敬意であり、遠慮は時に「本当のことを言っていない」「本音を隠している」という印象を与えてしまうこともあるのです。
「感情表現の抑制」も驚きの対象です。喜びや怒り、驚きなどの感情を外に表さない日本人の姿勢は、感情を豊かに表現するイタリア文化からすると「読みにくい」と感じられることがあります。例えば、プレゼントを贈っても大げさに喜ばない、素晴らしい景色を見ても控えめな反応しか示さないといった場面で、「喜んでいないのかな?」と誤解されることもあります。イタリア人にとって感情表現は社交の重要な一部で、「本当に感じていることを表に出す」ことが自然で健全なコミュニケーションと考えられているのです。
「個人的な質問への反応」も異なります。イタリアでは「結婚しているの?」「子供はいるの?」「何歳?」といった質問は普通の会話の一部ですが、日本人はこうした質問に戸惑うことが多いようです。特に年齢や結婚状況を聞かれることを不快に感じる日本人もいますが、イタリア人からするとこれは単に「あなたのことをもっと知りたい」という親しみの表れなのです。同様に、イタリア人は自分の家族の写真を見せたり、個人的な話をしたりすることで親近感を示しますが、日本人がそれに応じないと「壁を作っている」と感じることもあります。
「グループ行動」への傾向も驚きの対象です。日本人が職場や学校のグループで行動し、個人ではなく集団の決定に従う傾向は、個人主義的なイタリア文化からすると不思議に映ります。例えば、一人だけ違う意見でも、多数派に合わせてしまう日本人の姿を見て「なぜ自分の意見を言わないの?」と思うイタリア人は少なくありません。また、休暇の計画や食事の選択など、個人の好みが強く影響する決断でも集団に従う傾向があることに驚くことがあります。イタリア文化では「個性」や「自分らしさ」が重視され、たとえ多数派と違っても自分の意見や好みを大切にする傾向があるのです。
「仕事とプライベートの境界」に関する考え方も異なります。日本では仕事終わりに同僚と飲みに行ったり、休日でも仕事のメールに返信したりすることが一般的ですが、イタリアでは仕事とプライベートの区別が明確です。勤務時間外や休日の仕事関連の連絡は基本的に避けられますし、同僚との関係も職場内にとどめることが多いです。この「オンとオフの切り替え」は、イタリア人にとって健全な生活バランスを保つために重要なことです。日本人の「仕事中心」の生活スタイルや、プライベートの時間を犠牲にしてまで仕事に取り組む姿勢は、イタリア人からすると「なぜそこまで?」と思われることもあるのです。
③ 知っておきたいイタリアの文化(プレゼント)
―イタリアでは、友人・家族にどんなプレゼントをあげる?
「食べ物や飲み物」は最も一般的で喜ばれるプレゼントです。特に地元の特産品や季節の食材、高品質のワインやオリーブオイル、手作りの菓子などが人気です。イタリアでは食事を大切にする文化があるため、食に関するギフトは「相手の生活を豊かにする」贈り物として高く評価されます。例えば、トスカーナ地方の人を訪ねる際には良質のキャンティワイン、ナポリの人にはリモンチェッロ(レモンのリキュール)、シチリアの人には「カンノーリ」(リコッタチーズ入りのお菓子)など、地域の特産品が喜ばれます。友人の家に招かれた際のちょっとした手土産としては、ケーキや高級チョコレート、花束などが一般的です。
「家庭用品や装飾品」も定番のギフトです。イタリア人は「家」を大切にする傾向があるため、インテリア小物や食器、タオル、クッションカバーなどの実用的でありながらデザイン性の高いアイテムが喜ばれます。特に新居祝いには「家の温かみを象徴するもの」として、ランプやキャンドル、観葉植物などが贈られることも多いです。イタリアはデザインやクラフトマンシップの国として知られているため、地元の職人による手作りの陶器や木工品、ガラス製品なども良い贈り物とされています。例えば、ムラーノ島のガラス製品やデルータの陶器などは、芸術性と実用性を兼ね備えた贈り物として人気があります。
「パーソナルケア製品」も人気のギフトです。イタリアは香水やスキンケア製品などの美容アイテムも充実していて、特に女性へのプレゼントとして高級石鹸や香水、ボディローションなどがよく選ばれます。「アクア・ディ・パルマ」のような伝統的な香水ブランドや、「サンタ・マリア・ノヴェッラ」のような歴史あるフレグランスハウスの製品は特別な贈り物として喜ばれます。また、男性へのギフトとしても、高品質のシェービングセットや香水などがあります。これらのアイテムは「自己ケアの時間を大切にして欲しい」という気持ちを込めた贈り物でもあります。
「経験」を贈ることも増えています。特に若い世代を中心に、モノではなく「体験」を大切にする傾向が高まっており、コンサートや劇場のチケット、レストランでのディナー、ワイナリーツアーやクッキングクラスなどの体験型ギフトが人気です。こうした贈り物は「一緒に時間を過ごす」という意味合いも含まれており、関係性を深める機会にもなります。例えば誕生日プレゼントとして、高級レストランでのディナーに招待したり、週末の小旅行を計画したりすることは、特別な思い出を作る素敵な贈り物になります。イタリア人は「生活の質」を重視する傾向があるため、「良い体験」を贈ることは非常に評価されるのです。
「書籍や音楽」も意味のある贈り物とされています。イタリアには強い文学的伝統があり、良書は知的な贈り物として歓迎されます。特に相手の興味や専門分野に関連した本や、芸術書、写真集などは、「あなたの興味や知性を尊重している」というメッセージも込められた贈り物です。同様に、クラシック音楽のCDやオペラのDVDなども文化的な価値のある贈り物として喜ばれます。イタリアでは知的な会話や文化的な知識が重視される傾向があるため、こうした「心を豊かにする」贈り物は関係性の深さを示すものとなります。
―クリスマスや誕生日の他に、プレゼントを贈る機会ってある?
「La Befana(ラ・ベファーナ)」は1月6日の公現祭(Epifania)に祝われる伝統行事で、魔女のような姿をした老婆「ベファーナ」が子供たちに贈り物を持ってくるとされています。良い子には飴やお菓子を、悪い子には石炭(実際には黒砂糖のお菓子)をプレゼントするという言い伝えがあります。北部ではクリスマスにサンタクロース(バッボ・ナターレ)が、中南部ではこのベファーナが主な贈り物の担い手となっています。この日は冬の祝祭シーズンの最後を飾る日で、子供たちにとっては再び贈り物をもらえる楽しみな機会です。小さな靴下や靴を暖炉のそばに置いておくと、夜の間にベファーナがプレゼントを入れていくという習慣があります。
「Pasqua(復活祭)」はイタリアで重要な宗教的祝日であり、特に子供たちには大きなチョコレートの卵「uovo di Pasqua」がプレゼントされます。これらの卵は中に小さなおもちゃやサプライズギフトが入っているのが特徴で、開けるときの楽しみも含めた贈り物です。また、大人同士でも「colomba pasquale」(鳩の形をしたケーキ)などの特別なお菓子を贈り合う習慣があります。復活祭の月曜日「Pasquetta」には、家族や友人と郊外に出かけてピクニックを楽しむことも多く、この機会に食べ物や飲み物を持ち寄ることも一種の贈り物交換と言えるでしょう。
「Festa della Mamma(母の日)」と「Festa del Papà(父の日)」もイタリアで大切にされています。母の日は5月第2日曜日に祝われ、花束やパーソナライズされたギフト、家族での食事などが一般的です。父の日は3月19日の聖ヨセフの日に祝われることが多く、ネクタイやお酒、趣味に関連したアイテムなどがプレゼントされます。これらの日は「Zeppole di San Giuseppe」(聖ヨセフのゼッポレ)という特別なドーナツのようなお菓子を食べる習慣もあります。子供たちは学校で手作りのカードや小さな工作を作って親にプレゼントすることも多く、家族の絆を確認する大切な機会となっています。
「Onomastico(守護聖人の日)」は、イタリアの伝統的なお祝いで、自分の名前と同じ聖人の祝日を祝います。例えば、フランチェスコという名前の人は10月4日の聖フランチェスコの日、マリアという名前の人は8月15日の聖母被昇天祭などに祝福されます。この日には小さなプレゼントやカード、花などが贈られ、「誕生日」と同じくらい重要な個人的なお祝いとして扱われることもあります。特に古い世代や南部では、この習慣がまだ強く残っていて、名前の由来となった聖人を称える意味も含まれています。カトリックの伝統が強いイタリアならではの習慣と言えるでしょう。
「Laurea(大学卒業)」はイタリアで大きなお祝いの機会となります。学位論文の口頭試問に合格した学生は、友人や家族から「corona d’alloro」(月桂樹の冠)を受け取り、記念撮影や祝賀会が行われます。この達成を祝うプレゼントとしては、腕時計や万年筆などの高級文房具、旅行や経験ギフト、時には車や特別な旅行などが贈られることもあります。イタリアでは大学卒業が大きな節目と考えられており、将来のキャリアに向けた新たなスタートを象徴するプレゼントが選ばれることが多いです。この祝賀は通常、家族や親しい友人が集まってのディナーや小さなパーティーの形で行われ、達成を共に祝う機会となります。
④ 知っておきたいイタリアの文化(食文化)
―イタリアで、お袋の味と言えば?
「ラグー(Ragù)」は多くのイタリア人にとって「マンマの味」の代表格です。これは肉のソースで、地域によって作り方が大きく異なります。有名なのはボローニャの「ラグー・アッラ・ボロニェーゼ」で、牛肉と豚肉をトマト、香味野菜と一緒にじっくり煮込んだソースです。実はこれ、日本でいう「ミートソース」とは本来違うものなんです。ボローニャでは通常、このソースはスパゲッティではなく「タリアテッレ」という平たい卵入りパスタと合わせます。ナポリのラグーはまた違って、大きな肉の塊をトマトソースでゆっくり煮込み、その肉を「セコンド(メインディッシュ)」として、ソースをパスタに絡めて「プリモ(第一の皿)」として食べる二段階の料理になります。どちらにしても、これは「日曜日の料理」としてよく作られ、マンマが大家族のために何時間もかけて調理する愛情たっぷりの料理です。
「ラザニア(Lasagna)」も家庭料理の代表格です。層状になったパスタシートの間にラグーとベシャメルソース、パルミジャーノチーズを重ねて焼いた料理で、これも地域や家庭によってバリエーションがあります。ボローニャではミートソース、ナポリではリコッタチーズや小さなミートボールを入れることもあります。この料理は特別な日の食事として準備され、複数の工程があるため通常は休日に作られます。「母が作るラザニア」は多くのイタリア人にとって帰省したときの楽しみであり、家族の思い出と深く結びついています。このレシピは代々受け継がれることも多く、祖母から母へ、母から娘へと伝えられる家族の遺産とも言えるものです。
「ミネストローネ(Minestrone)」は野菜たっぷりのスープで、これも地方や季節、そして家庭によって様々なバリエーションがあります。基本的には、その時期に手に入る野菜を使った具沢山のスープで、豆類や時にはパスタやお米も加えます。北部では米を入れることが多く、南部ではパスタを加えることが一般的です。これは「何もないときでも作れる料理」として、戦時中や貧しい時代にも家族を養うために作られてきた歴史があります。そのため、「無駄をしない知恵」や「少ない材料でも栄養価の高い食事を作る工夫」が詰まった料理と言えます。夏は冷たく、冬は温かく提供されることもあり、一年を通して愛される家庭料理です。
「ポレンタ(Polenta)」は北イタリア、特にロンバルディアやヴェネト地方の伝統的な家庭料理です。トウモロコシの粉を水で煮込んだもので、かつては「貧者の食べ物」として知られていましたが、今では郷土料理として大切にされています。家庭によって粒子の粗さや調理時間が異なり、柔らかいクリーミーなタイプから、固めて切り分けるタイプまで様々です。典型的には肉の煮込みやチーズ、キノコなどと一緒に食べられます。この料理を作るときの「鍋をかき混ぜ続ける」という行為は、多くのイタリア人にとって祖母や母の思い出と結びついていて、「愛情と忍耐」の象徴とも言えるでしょう。家族の集まりで大きな鍋いっぱいのポレンタを木製のまな板に広げ、糸で切り分ける光景は、北イタリアの家庭的な食卓の象徴的な風景です。
地域によって「お袋の味」は大きく異なります。シチリアでは「カポナータ」(茄子のトマト煮)や「パスタ・アッラ・ノルマ」(茄子とリコッタチーズのパスタ)、ローマでは「カチョ・エ・ペペ」(チーズと黒コショウのパスタ)や「サルティンボッカ・アッラ・ロマーナ」(子牛肉の一種)、トスカーナでは「パッパ・アル・ポモドーロ」(パンとトマトのスープ)など、それぞれの地域に独自の家庭料理があります。これらの料理は「クチーナ・ポーヴェラ」(貧しい料理)と呼ばれることもありますが、これは決して見下した表現ではなく、「シンプルな材料でも工夫と愛情で美味しくする料理」という意味合いがあります。どの地域でも共通しているのは、これらの料理が家族の歴史や思い出と深く結びついていることです。
―イタリアで大人も子供も好きな定番の家庭料理って何?
「パスタ・アル・ポモドーロ(トマトソースのパスタ)」はイタリア中で愛される最も基本的な家庭料理です。新鮮なトマト(または良質なカンニングトマト)、バジル、ニンニク、オリーブオイルという非常にシンプルな材料で作られますが、それゆえに材料の質と調理のタイミングが重要になります。多くのイタリア人にとってこれは「コンフォートフード」であり、忙しい平日の夕食としても頻繁に登場します。子供から大人まで好まれる味で、地域や家庭によって少しずつアレンジが異なるのも特徴です。北部では玉ねぎやニンジンを加えることもあれば、南部ではより多くのニンニクや唐辛子を使うこともあります。シンプルな料理ですが、マンマの作るポモドーロソースの味は家庭ごとに異なり、そこに家族の記憶が宿ります。
「リゾット」も大人も子供も好む定番料理です。特に北部で人気があり、地域によって様々なバリエーションがあります。ミラノの「リゾット・アッロ・ザッフェラーノ」(サフランリゾット)、ヴェネツィアの「リゾット・アル・ネーロ・ディ・セッピア」(イカ墨リゾット)、ピエモンテの「リゾット・アイ・フンギ」(キノコのリゾット)など、地元の食材を活かした様々な種類があります。リゾットは調理過程で常にかき混ぜる必要があるため、「愛情と時間をかけた料理」というイメージがあります。クリーミーで食べやすい食感は子供にも人気で、野菜を細かく刻んで入れることで栄養価も高められるため、家庭料理としても重宝されています。
「フリッタータ(イタリアン・オムレツ)」も家庭料理の定番です。卵に様々な具材を混ぜ、フライパンで両面を焼いた料理で、スペインのトルティージャに似ていますが、具材のバリエーションが非常に多いのが特徴です。冷蔵庫に残っている野菜や前日の残り物を活用できるため、「アンチスプレーコ(食品廃棄削減)」の精神にも合致しています。ジャガイモやズッキーニ、タマネギ、チーズなどの定番具材から、パスタの残りを入れた「フリッタータ・ディ・パスタ」まで、家庭ごとに特色があります。冷めても美味しいため、ピクニックやお弁当、軽食にも適しており、多目的に活用される便利な料理です。
「サルティンボッカ・アッラ・ロマーナ」はローマの伝統料理ですが、今では全国的に愛されています。子牛肉の薄切りにプロシュート(生ハム)とセージを重ね、白ワインで軽く煮込んだシンプルながら風味豊かな料理です。「サルティンボッカ」は「口の中で跳ねる」という意味で、その名の通り口の中で跳ねるほど美味しいと言われています。調理時間が短く、特別な技術も必要ないため、忙しい家庭でも作りやすい料理です。そのままでも美味しいですが、マッシュポテトやポレンタなどの付け合わせと一緒に食べることも多く、「ちょっと特別な日の夕食」として重宝されています。
「スイーツ」も家庭料理の重要な部分です。「ティラミス」はおそらく最も有名なイタリアのデザートで、マスカルポーネチーズとコーヒーを染み込ませたビスケットを層にしたデザートです。家庭によってレシピが異なり、本来のレシピに卵黄を使用しないバージョンや、コーヒーの代わりにイチゴやレモンなどの風味を使うバリエーションもあります。また、「パンナコッタ」(クリームプリン)や「コルネッティ」(クロワッサンに似たパン)など、子供から大人まで幅広く愛されるお菓子も多く、日曜日の朝食や特別な日のデザートとして手作りされることが多いです。
⑤ 知っておきたいイタリアの文化(その他)
―イタリアで人気のスポーツとか、エンターテイメントって何?
「カルチョ(サッカー)」は断然イタリアで最も人気のあるスポーツです。ユヴェントス、ACミラン、インテル・ミラノ、ASローマなどの有名クラブがあり、週末になるとスタジアムは熱狂的なファンで埋め尽くされます。イタリア人にとってサッカーチームへの忠誠心は非常に強く、しばしば地域のアイデンティティとも結びついています。「ティフォージ(サポーター)」の文化も特徴的で、応援歌や旗、色鮮やかな横断幕などで情熱的な応援を繰り広げます。日曜日の午後になると多くの男性(そして女性も)がバールに集まり、試合を観戦しながら活発に議論する姿は、イタリアの典型的な週末の光景です。サッカーは単なるスポーツを超えて、社会的な現象であり文化的なアイデンティティの一部と言えるでしょう。
「オペラ」はイタリア発祥の芸術形式で、今でも人気のあるエンターテイメントです。特にミラノの「ラ・スカラ座」、ナポリの「サン・カルロ劇場」、ヴェローナの「アレーナ・ディ・ヴェローナ」などの歴史的な劇場での公演は、地元の人々にとっても特別な文化イベントです。夏にはローマの「カラカラ浴場」やヴェローナの「アレーナ」など古代遺跡を舞台にした野外オペラも行われ、地元の人々だけでなく全国から観客が集まります。ヴェルディ、プッチーニ、ロッシーニなどのイタリア人作曲家のオペラは特に人気があり、「椿姫」「トスカ」「セビリアの理髪師」などの作品は現代でも頻繁に上演されています。イタリアでは、オペラは「高尚な芸術」というよりも、より幅広い層に親しまれている文化的エンターテイメントです。
「フェスティバル文化」もイタリアの重要な娯楽の一つです。年間を通じて様々な祭りやイベントが開催され、地域の伝統や季節の産物を祝います。例えば、シエナの「パリオ」(競馬祭り)、ヴェネツィアの「カーニバル」、イヴレアの「オレンジ投げ祭り」などは何世紀も続く伝統行事であり、地元のアイデンティティを強く反映しています。また、「サグラ」と呼ばれる食の祭りも各地で開催され、「サグラ・デル・タルトゥーフォ」(トリュフ祭り)や「サグラ・デッラ・ポルケッタ」(豚の丸焼き祭り)など、地域の特産品にちなんだお祭りが数多くあります。こうした祭りは地元の人々の重要な社交の場であると同時に、伝統を次世代に伝える役割も果たしています。
「カフェ文化」もイタリアの日常的なエンターテイメントの一つです。朝のエスプレッソから夕方の「アペリティーボ」(軽い飲み物と軽食)まで、バールは社交の中心となっています。特に夕方のアペリティーボの時間は、仕事帰りの人々がドリンクと軽食を楽しみながら友人と会話する重要な社交の時間です。多くのバールでは飲み物を注文すると小さなおつまみや軽食のビュッフェが提供されることも多く、これが夕食前の社交の場となっています。この習慣は特に北部の都市で発達していますが、今では全国に広がっています。「スプリッツ」(アペロールとプロセッコを混ぜたカクテル)や「ネグローニ」などの独特のカクテルと共に、リラックスした時間を過ごすのがイタリアンライフスタイルの特徴です。
「映画」もイタリアで長い歴史と人気を持つエンターテイメントです。イタリアは世界的に有名な映画監督や俳優を多数輩出し、「ネオレアリズモ」(新現実主義)や「スパゲッティ・ウェスタン」など独自の映画ジャンルも生み出してきました。フェデリコ・フェリーニ、ミケランジェロ・アントニオーニ、セルジオ・レオーネなどの監督は、世界の映画史に大きな影響を与えています。現代では「チネマ・パラディソ」のジュゼッペ・トルナトーレや「La grande bellezza(グレート・ビューティー)」のパオロ・ソレンティーノなどの監督が国際的に評価されています。イタリアでは夏になると「シネマ・アル・アペルト」(野外映画)が公園や広場で上映されることも多く、家族連れや若いカップルに人気のエンターテイメントとなっています。
―イタリア人に人気の観光地って、外国人があまり行かないところだと?
「マレンマ」はトスカーナ州南部からラツィオ州北部にかけての沿岸地域で、イタリア人にとっての穴場バケーションスポットとして知られています。この地域は美しい自然と中世の村々が点在し、特に夏はイタリア人家族の避暑地として人気です。「グロッセート」「ピティリアーノ」「ソラーノ」などの町は、エトルリア時代の遺跡や中世の雰囲気を楽しめる観光スポットですが、外国人観光客はあまり訪れません。また、海岸沿いには「カスティリオーネ・デッラ・ペスカイア」や「タラモーネ」などのビーチリゾートがあります。この地域は伝統的な料理も魅力で、「アクワコッタ」(パンのスープ)や「トルテッリ・マレンマーニ」(リコッタチーズ入りパスタ)などの郷土料理を楽しめます。また、このエリアはワイン産地としても知られ、「モレッリーノ・ディ・スカンサーノ」などの地元ワインが有名です。
「フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州」は北東部に位置し、オーストリアとスロベニアに国境を接する地域です。このエリアはアルプスの山々から美しいアドリア海の海岸まで様々な景観が楽しめ、イタリア人のバケーション先として人気がありますが、多くの外国人観光客はヴェネツィアに集中し、この地域まで足を延ばしません。州都の「トリエステ」はハプスブルク帝国時代の優雅な建物が残る港町で、歴史的なカフェや広場を散策できます。内陸部の「ウーディネ」や「チヴィダーレ・デル・フリウリ」は中世の雰囲気が残る美しい町で、「コッリオ」地区では素晴らしいワインを楽しむことができます。この地域はスラブやオーストリアの影響を受けた独特の文化と料理があり、「フリコ」(チーズのフリッター)や「グラース」(スロベニア風のシチュー)などの郷土料理も魅力です。
「チレント」はカンパニア州南部の沿岸地域で、人気の高いアマルフィ海岸やカプリ島に比べて外国人観光客は少ないものの、イタリア人の間では夏のバケーション先として非常に人気があります。「チレント・エ・ヴァッロ・ディ・ディアーノ国立公園」は美しい自然環境と海岸線が特徴で、「パエストゥム」という古代ギリシャ神殿の遺跡も見逃せません。「マリーナ・ディ・カメローラ」「アッチャローリ」「カステッラバーテ」などの海岸沿いの町には美しいビーチがあり、夏になるとイタリア人家族で賑わいます。この地域は「地中海式ダイエット」の発祥の地としても知られ、オリーブオイル、トマト、ブッファローモッツァレラなどの高品質な食材と料理が魅力です。特に「モッツァレラ・ディ・ブーファラ・カンパーナ」(水牛のミルクから作られるチーズ)は、この地域の特産品として有名です。
「モリーゼ州」はイタリアで最も小さく、最も知られていない州の一つですが、その未開発の魅力がイタリア人バケーショナーに少しずつ認識されるようになっています。アドリア海の美しい海岸線と内陸部の山岳地帯があり、「テルモリ」や「カンポマリーノ」などの海岸沿いの町や、「カンポバッソ」や「イゼルニア」などの中世の町が点在しています。この地域は古代サムニウム文明の遺跡や「トランスウマンツァ」(季節的な牧畜の移動)の伝統など、独自の文化遺産を持っています。また、「カヴァテッリ」(手打ちパスタ)や「パレ・エ・ミスク」(豆とトウモロコシのスープ)などの素朴な郷土料理も魅力です。観光インフラはまだ発展途上ですが、それゆえに「本物のイタリア」を体験できる場所として、探検心のあるイタリア人旅行者に人気が高まっています。
「バジリカータ州」の「マテーラ」は、岩に彫られた洞窟住居「サッシ」で知られる町です。最近ではユネスコ世界遺産に登録され、2019年には「ヨーロッパ文化首都」に選ばれたことで知名度が上がりつつありますが、まだ外国人観光客は比較的少ない穴場スポットです。何千年もの間人が住み続けてきたこの独特の町は、まるで絵本から飛び出してきたような風景で、特に夕暮れ時や夜のライトアップは幻想的です。この地域の伝統料理には「クラスタータ」(リコッタチーズとソーセージのパイ)や「ストラスキナーテ」(手打ちパスタ)などがあります。マテーラはその独特の景観から多くの映画のロケ地としても使われ、メル・ギブソン監督の「パッション」やジェームズ・ボンド映画「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」の撮影地としても知られています。
―イタリア人に人気のレストランって?外国人があまり行かないところだと?
「トラットリア」はイタリア人に最も愛されている食事処の一つです。これは家族経営の小さなレストランで、華美な内装はないものの、本格的な家庭料理を手頃な価格で楽しめる場所です。観光客向けのレストランとは異なり、地元の常連客で賑わうトラットリアでは、毎日変わる「メニュー・デル・ジョルノ」(本日のメニュー)が特徴で、季節の新鮮な食材を使った料理が提供されます。観光地の中心から少し離れた住宅街にあることが多く、外国人観光客はあまり訪れません。料理は地域色が強く、例えばローマのトラットリアでは「カチョ・エ・ペペ」(チーズと黒コショウのパスタ)や「コーダ・アッラ・ヴァチナーラ」(牛の尾の煮込み)、フィレンツェでは「リボッリータ」(パンと野菜のスープ)や「ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ」(Tボーンステーキ)などの地元料理が楽しめます。
「オステリア」も地元のイタリア人に人気のレストランタイプです。もともとは旅人に食事と宿を提供する場所でしたが、現在では家庭的な料理とカジュアルな雰囲気を楽しめるレストランとなっています。トラットリアよりもさらにシンプルで価格も手頃なことが多く、定番料理と地元のワインを楽しむのが一般的です。特に学生や若者に人気があり、賑やかで活気のある雰囲気が特徴です。メニューは限られていることが多く、その日に用意されたものから選ぶスタイルです。例えばボローニャの「オステリア・デル・オルサ」では「タリアテッレ・アル・ラグー」(ボロネーゼソースのパスタ)が、ローマの「オステリア・ダ・フォルトゥナータ」では「カチョ・エ・ペペ」などが人気です。こうした店は観光ガイドブックにはあまり載っておらず、地元の人との会話から知ることが多いです。
「アグリツーリズモ」は農家が経営する宿泊施設兼レストランで、「ファーム・トゥ・テーブル」を体験できる場所として近年イタリア人に人気が高まっています。自家製の野菜、果物、オリーブオイル、ワインなどを使った料理を提供し、「キロメートルゼロ」(地元産)の食材にこだわっています。郊外や田舎にあるため外国人観光客は少なく、週末に家族で訪れるイタリア人が中心です。建物は古い農家や邸宅を改装したもので、田舎の素朴な雰囲気を楽しめます。料理は「クチーナ・ポーヴェラ」(素朴な田舎料理)が中心で、地域の伝統的なレシピを守りながら提供されています。例えばトスカーナのアグリツーリズモでは「パッパ・アル・ポモドーロ」(パンとトマトのスープ)や「ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ」、シチリアでは「カポナータ」(茄子の煮込み)や「アランチーニ」(ライスコロッケ)などが味わえます。
「エノテカ」はワインバーと食事処を兼ねた場所で、イタリア人に人気の夜の社交場です。様々な地方の上質なワインと、それに合う軽い食事やおつまみを提供します。観光客向けのレストランよりもカジュアルな雰囲気で、地元の人々が仕事帰りに一杯飲みながら友人と歓談する場所として利用されています。特に最近は「アペリティーボ」の文化と結びつき、夕方から夜にかけて賑わいます。エノテカでは単にワインを飲むだけでなく、様々な地方の特産品を味わうことができ、例えば「タリアータ」(薄切りの牛肉ステーキ)や「ブルスケッタ」(トースト)、地元のチーズやサラミの盛り合わせなどが人気です。多くのエノテカでは、ワインの知識が豊富なスタッフがいて、料理に合うワインを提案してくれるのも魅力です。
「ピッツェリア・ア・タリオ」(ピザ切り売り店)も外国人観光客にはあまり知られていませんが、イタリア人の日常的な食事場所として人気です。長方形のピザを好きなサイズに切り分けて販売するスタイルで、様々な種類のピザを少しずつ試せるのが魅力です。テイクアウトが基本ですが、簡単なカウンター席があることも多く、立ち食いまたは座って食べることもできます。特に昼時には学生やオフィスワーカーでにぎわい、リーズナブルな価格で本格的なピザが楽しめます。伝統的なマルゲリータやマリナーラから、季節の野菜を使った創作ピザまで様々な種類があり、地元の人々の日常的な食事として親しまれています。観光地にもこうした店はありますが、住宅街やオフィス街にある地元向けの店は価格が安く、より本格的な味わいが楽しめることが多いです。
まとめ
イタリアの文化を知ることで、「生活の質」と「人間関係」を大切にする価値観に触れることができます。効率や生産性だけを追求するのではなく、食事や会話、芸術、自然などを楽しむ余裕を持つイタリア的なライフスタイルは、現代の忙しい社会に生きる私たちに新たな視点を与えてくれるでしょう。
特に印象的なのは、イタリア人の「情熱」と「表現力」です。感情を包み隠さず表現し、議論を楽しみ、食事に対しても妥協を許さない姿勢からは、「ただ生きる」のではなく「豊かに生きる」ことの意味を考えさせられます。また、地域ごとの多様性を尊重しながらも、食や芸術といった共通の価値観を持つ文化からは、「多様性の中の統一性」という現代社会にとって重要なテーマも見えてきます。
イタリアへの旅行や留学を考えている方は、有名な観光地だけでなく、地元の人々が集まるマルカートやトラットリア、地域のお祭りなどにも積極的に参加してみることをお勧めします。そこで出会う人々との交流や食べ物、何気ない日常の風景の中に、真のイタリア文化が息づいているからです。言葉が通じなくても、笑顔と身振り手振りで意外とコミュニケーションができるのも、表現豊かなイタリア文化の魅力と言えるでしょう。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。