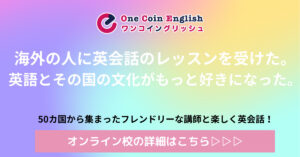【シンガポールの文化を学ぶ!】シンガポールの食文化の日本との違い5選 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

シンガポールってどんな国? 日本からのイメージ
東南アジアの小さな島国シンガポール。日本人にとって、マーライオン、高層ビル群、厳格な法律、そして「チキンライス」や「チリクラブ」などの料理が有名な国というイメージがあるかもしれません。また、「クリーンな都市国家」「多民族社会」「英語が通じる」といったイメージも強いでしょう。
実際のシンガポールは、面積わずか728平方キロメートル(東京23区とほぼ同じ)の都市国家ながら、世界有数の金融センターとして発展を遂げています。中華系(約74%)、マレー系(約13%)、インド系(約9%)などの多様な民族が共存し、英語、中国語(北京語)、マレー語、タミル語の4つが公用語として認められています。
この多様性がシンガポールの食文化にも大きな影響を与えており、様々な民族の料理が混ざり合い、独自の進化を遂げた「シンガポール料理」が生まれています。「フードパラダイス」と称されるほど、食への情熱が強い国としても知られており、地元の人々にとって「何を食べるか」は日常会話の重要なトピックとなっています。
シンガポールで暮らす/シンガポールに行くメリットについて
シンガポールを訪れる、あるいは暮らす大きな魅力の一つは、その豊かな食文化にあります。「フードパラダイス」の名に恥じない多彩な料理を、比較的リーズナブルな価格で楽しめることは、大きな魅力と言えるでしょう。
特に「ホーカーセンター」と呼ばれる屋台村では、数ドルから本格的な各国料理を味わうことができます。清潔で安全な環境で、多国籍の料理を気軽に試せるのは、シンガポールならではの体験です。また、水道水が飲めるなど衛生面でも安心感があり、初めての東南アジア旅行先としても人気があります。
多文化社会であるシンガポールでは、中華料理、マレー料理、インド料理、ペラナカン料理など様々な民族料理を本格的に楽しめるだけでなく、フュージョン料理も発達しています。一つの国の中で異なる食文化を体験できることは、食の冒険家にとっては天国のような環境でしょう。
また、シンガポールは地理的にも東南アジアの中心に位置するため、周辺国の食材や調味料が集まりやすく、本場の味を楽しめるのも魅力です。スーパーマーケットでは、アジア各国の調味料や食材が手に入りやすいため、長期滞在の場合は自宅でも本場の味を再現しやすい環境があります。
さらに、英語が公用語の一つであるため、レストランやホーカーセンターでの注文も比較的容易です。メニューの多くは英語表記があり、食の好みやアレルギーについての説明もしやすいでしょう。
① シンガポールの食文化の日本との違い(食事)
シンガポールと日本の食事文化には、いくつかの興味深い違いがあります。まず、食事の基本スタイルが大きく異なります。日本では一人一人に膳や食器が用意され、「一汁三菜」のように組み合わせられた料理を個別に食べることが多いですが、シンガポールでは大皿に盛られた料理を複数人で共有するスタイルが一般的です。
特に中華系シンガポール人の間では、丸いテーブルに回転台(ターンテーブル)が設置されており、皆で食事をシェアします。「家族式(Family Style)」と呼ばれるこのスタイルは、コミュニケーションを重視するシンガポールの食文化を象徴しています。日本ではしゃぶしゃぶや鍋料理以外では、他人の料理から取り分けることはあまりありませんが、シンガポールではそれが標準的な食べ方です。
また、食事の時間帯にも違いがあります。日本では昼食は12時頃、夕食は19時頃が一般的ですが、シンガポールでは夕食が18時頃から始まることが多く、早い時間に食べる傾向があります。さらに特徴的なのは「サバー(Supper)」と呼ばれる夜食の文化で、22時以降にホーカーセンターやレストランで食事をとることも珍しくありません。深夜0時を過ぎても営業している食堂が多いのは、日本との大きな違いでしょう。
食事のマナーにも違いがあります。シンガポールではインド料理を手で食べたり、中華料理をレンゲとお箸で食べたりと、料理の種類によって異なる食べ方をします。特に中華系の間では、テーブルに置かれた茶碗を手に持ち上げて食べるのではなく、お皿に顔を近づけて食べるスタイルが一般的です。また、日本では「いただきます」「ごちそうさま」と挨拶をしますが、シンガポールにはそのような習慣はなく、食べ始めるタイミングも各自の判断に任されています。
飲み物に関しても違いがあります。日本では食事と一緒にお茶を飲むことが多いですが、シンガポールでは「荼(Teh)」と呼ばれる甘いミルクティーや「コピ(Kopi)」と呼ばれる地元のコーヒー、またはアイスの砕いた飲み物「アイスカチャン」などが一般的です。また、食事中に氷水が無料で提供されることも多く、暑い気候に対応した飲み物の選択が一般的です。
価格帯についても違いがあります。日本では外食は比較的高価ですが、シンガポールのホーカーセンターでは5シンガポールドル(約500円)前後で満足のいく食事ができます。一方で、高級レストランはシンガポールの方が高い傾向にあり、特にアルコール飲料は高額です。
② シンガポールの食文化の日本との違い(会話)
食事の場での会話についても、シンガポールと日本では興味深い違いがあります。日本では「食事中のおしゃべりは控えめに」という文化がありますが、シンガポールでは食事の時間はコミュニケーションの重要な機会とされており、活発な会話が交わされます。
特徴的なのは、シンガポール人は食事の場で次の食事について話すことがよくあるという点です。「今日のランチは美味しかったね、明日の夕食は何を食べようか」といった会話は珍しくなく、食への関心の高さを表しています。日本人からすると「まだ今の食事を楽しんでいるのに」と驚くかもしれませんが、シンガポール人にとって「食べること」は単なる栄養摂取を超えた文化的な営みなのです。
言語の面でも独特の表現があります。「マカン(Makan)」はマレー語で「食べる」という意味で、「マカンラー(Makan lah)」は「さあ食べよう」という意味になります。「シオク(Shiok)」という言葉は「とても美味しい」や「最高だ」という感動を表す言葉で、美味しい料理を食べた時によく使われます。
また、シンガポール人は食事の質についての議論が大好きです。「このチキンライスはあそこのより美味しい」「この店のラクサはスープが薄い」など、食べ物の味や質について率直に意見を交わすのが一般的です。日本では「批判的な意見は控えめに」という文化がありますが、シンガポールでは食に関する率直な意見交換が食文化の一部となっています。
ホーカーセンターでの注文方法も日本のレストランとは異なります。日本ではウェイターを呼んで注文することが多いですが、シンガポールのホーカーセンターでは自分で屋台に行って注文し、番号札をもらって席で待つスタイルが一般的です。また、混雑時には知らない人と同じテーブルを共有する「シェアテーブル」の習慣があり、これは日本のフードコートでもあまり見られない光景です。
食事の支払い方法にも違いがあります。シンガポールでは友人同士の食事では一人が全額を支払い、次回は別の人が支払うという「交代制」が一般的です。日本のような「割り勘」はあまり一般的ではなく、特に年長者や目上の人が全額を支払うことが多いです。これは「面子(メンツ)」を重んじる文化の表れとも言えるでしょう。
③ シンガポールの食文化の日本との違い(記念日/祝日)
シンガポールと日本では、祝日や記念日に食べる料理や食事の習慣にも大きな違いがあります。多民族国家であるシンガポールでは、それぞれの民族の伝統的な祝日に独自の特別料理があり、それが国全体の食文化の一部となっています。
まず、中国系シンガポール人にとって最も重要な祝日である「春節(旧正月)」には、「ユーシェン(魚生)」と呼ばれる生魚のサラダを家族や友人と一緒に高く掲げて混ぜ合わせる習慣があります。これは「ロウヘイ(撈起)」と呼ばれる儀式で、「より高く掲げるほど幸運が訪れる」と信じられています。また、「ニエンガオ(年糕)」という餅菓子や、「タンユエン(湯圓)」という甘いお団子も定番です。日本のおせち料理のように縁起の良い意味を持つ料理を食べる点は共通していますが、その内容や食べ方は大きく異なります。
マレー系シンガポール人にとって重要な「ハリラヤ・プアサ(断食明け)」の祝日には、「ケトゥパッ(Ketupat)」と呼ばれるヤシの葉で包んだお米の料理や、「ルンダン(Rendang)」という牛肉のココナッツ煮込みが定番です。断食月「ラマダン」の後に家族や友人と集まって盛大に食事を共にする習慣があります。
インド系シンガポール人の「ディーパバリ(灯明祭)」では、「ムルク(Murukku)」という揚げ菓子や、「ラッドゥー(Laddu)」というお菓子が特徴的です。また、「ビリヤニ(Biryani)」というスパイスの効いた炊き込みご飯も祝いの席では欠かせません。
シンガポールでは、こうした民族ごとの祝日料理を互いに尊重し、異なる文化的背景を持つ友人宅を訪問して料理を共にする文化があります。これは「オープンハウス」と呼ばれ、家を開放して客を招き入れるもので、多文化共生社会を象徴する習慣と言えるでしょう。
一方、日本では正月におせち料理、ひな祭りにちらし寿司、子どもの日にかしわ餅など、日本固有の行事食があり、それが日本の文化的アイデンティティと結びついています。シンガポールと日本は共に行事と食が密接に結びついている点では共通していますが、シンガポールでは多民族の祝日と料理が国全体の文化として共有されている点が特徴的です。
クリスマスの過ごし方も異なります。日本ではケーキとフライドチキンが定番ですが、シンガポールでは多民族社会を反映して様々なスタイルがあります。西洋的なローストターキーやハムを楽しむ家庭もあれば、中華料理でお祝いする家庭もあります。また、クリスマス期間中はホテルのビュッフェが特に人気で、家族や友人と豪華な食事を楽しむのが一般的です。
④ シンガポールの食文化の日本との違い(おふくろの味)
「おふくろの味」や家庭料理の概念にも、シンガポールと日本では興味深い違いがあります。日本では「おふくろの味」は母親から受け継いだ伝統的なレシピや、家族の好みに合わせた独自のアレンジが加えられた料理を指すことが多いです。一方、シンガポールの家庭料理は民族的背景によって大きく異なり、さらに多文化社会の中で相互に影響し合っているという特徴があります。
中華系シンガポール人の家庭料理は、出身地域(福建、潮州、広東など)の影響を強く受けています。例えば福建系の家庭では「ポーピア(薄いクレープで野菜や肉を巻いた春巻き)」を家族で一緒に作る習慣があり、これは日本の餃子パーティーのような家族の絆を深める機会となっています。また、「コンジー(お粥)」に様々な具材を入れたり、「ブラックソース・チキン」などの比較的シンプルな料理も家庭料理として親しまれています。
マレー系の家庭では、「ナシレマッ(ココナッツミルクで炊いたご飯)」や「サンバル(唐辛子ベースのソース)」を使った料理、「アヤム・ゴレン(鶏肉の唐揚げ)」などが一般的です。イスラム教の教えに従い、豚肉を使わない、ハラール認証の食材を使うなどの特徴があります。
インド系の家庭では、「チャパティ(平たいパン)」や「ダール(豆のカレー)」、「ラッサム(酸味のあるスープ)」などが日常的に作られています。スパイスを効かせた料理が多く、家庭ごとのスパイス配合が「おふくろの味」となっています。
興味深いのは、シンガポールでは他民族の料理を自宅で作ることも珍しくない点です。例えば中華系の家庭でカレーを作ったり、インド系の家庭で中華風の炒め物を作ったりすることが一般的です。これは多文化社会における食の融合を示しています。
調理法にも違いがあります。日本の家庭料理は「出汁」の文化を中心に、素材の味を活かした繊細な調理が特徴ですが、シンガポールの家庭料理は香辛料や調味料をふんだんに使い、濃厚な味付けが多い傾向があります。また、炒める、揚げるなどの調理法が多く、日本のような「煮る」「蒸す」料理は比較的少ないです。
近年の傾向としては、シンガポールでも共働き家庭の増加により、伝統的な家庭料理を作る機会が減少しています。その代わりに、ホーカーセンターでのテイクアウトや宅配サービスの利用が増えており、「おふくろの味」の概念そのものが変化しつつあります。一方で、祝日や特別な日には家族のレシピで調理する伝統は維持されており、世代を超えた料理の伝承は重要視されています。
⑤ シンガポールの食文化の日本との違い(その他)
シンガポールと日本の食文化には、上記以外にもいくつかの興味深い違いがあります。ここでは、特に注目すべき違いをいくつか紹介します。
まず、食の場所と形態に大きな違いがあります。日本では家庭での食事が基本ですが、シンガポールでは外食の頻度が非常に高いのが特徴です。これは、ホーカーセンターなどで安価に美味しい食事が楽しめること、住宅が比較的狭く調理スペースが限られていること、また高温多湿の気候で調理が負担になることなどが理由として挙げられます。週に5日以上外食するシンガポール人も珍しくなく、これは日本との大きな違いと言えるでしょう。
配膳の違いも興味深いです。日本の食事は「一汁三菜」のように同時に複数の料理が並びますが、シンガポールでは料理が準備できた順に次々と運ばれてくる「アドホック・サービス」スタイルが一般的です。これは「熱々の料理を最高の状態で楽しむ」という考え方に基づいています。そのため、同じテーブルの人でも別々のタイミングで食事を始めることも珍しくありません。
調味料の使い方にも違いがあります。日本では醤油やわさびなど、料理によって適切な調味料が決まっていることが多いですが、シンガポールでは食卓に様々な調味料(チリソース、ソイソース、ホワイトペッパーなど)が並び、各自が好みに応じて自由に味を調整するのが一般的です。特に「サンバル・チリ」と呼ばれる唐辛子ソースは多くの料理に添えられ、辛さの調整に使われます。
また、シンガポールには「ケンチン(Ketchup)」という概念があります。これは食事中に食器がぶつかり音を立てないよう気をつけるという日本の食事マナーとは反対に、大勢で賑やかに食事をする中で食器が触れ合い音を立てること自体を楽しむ文化です。「音が多いほど賑やかで楽しい食事」という考え方は、日本の「静かに食事を楽しむ」という美学とは対照的です。
食事の速度についても違いがあります。日本では「ゆっくり味わう」ことが推奨されますが、シンガポールでは比較的速いペースで食事を済ませることが一般的です。これは「食事後の会話を楽しむ時間を確保する」という考え方や、混雑するホーカーセンターでのテーブル回転を考慮した文化とも言えるでしょう。
また、日本では「もったいない」精神から食べ残しを嫌う傾向がありますが、シンガポールでは特に宴会の場では「豊かさの象徴」として少し多めに注文し、食べきれないことも珍しくありません。ただし、近年は食品廃棄の問題意識が高まり、この習慣も少しずつ変化しつつあります。
最後に、デザートの位置づけも異なります。日本では食後のデザートとしてフルーツや和菓子を楽しむことが多いですが、シンガポールでは「デザート」は食事とは別の機会に楽しむものという概念があります。例えば、夕食の後にデザート専門店に行き、「チェンドル」や「アイスカチャン」などの甘味を楽しむのが一般的です。「デザートスポット巡り」は若者の間で人気のアクティビティとなっています。
まとめ
シンガポールと日本の食文化には、歴史的背景や地理的条件、さらには民族的多様性から生まれた様々な違いがあります。シンガポールの食文化は「共有」と「コミュニケーション」を重視し、多様な民族料理が融合した独自の発展を遂げている一方、日本の食文化は「個」と「季節感」を大切にする傾向があります。
食事のスタイルでは、シンガポールは大皿を共有し活発に会話を楽しむのに対し、日本は個別の器で静かに食事を味わうという違いがあります。祝日や記念日の食事も、多民族国家シンガポールでは多彩な伝統料理が共存し、互いの文化を尊重し合う「オープンハウス」の習慣がある一方、日本は日本固有の行事食が深く根付いています。
「おふくろの味」の概念も、シンガポールでは民族的背景によって多種多様であり、また他民族の料理の影響も受けやすいという特徴があります。調味料の使い方や食事のペース、外食の頻度など、日常的な食習慣においても両国には興味深い違いが見られます。
こうした違いを理解することは、シンガポールを訪れる際や、シンガポール人と交流する際に、より深く食文化を楽しむための鍵となるでしょう。また、違いを知ることで自国の食文化を客観的に見つめ直す良い機会にもなります。
シンガポールの多様でダイナミックな食文化は、異なる文化的背景を持つ人々が共存する社会の象徴とも言えます。次回シンガポールを訪れる際には、こうした食文化の違いを意識しながら、現地の食を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。