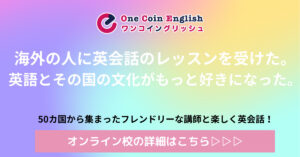【ニュージーランドってどんな国?】ニュージーランドの食文化の日本との違い5選 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

ニュージーランドってどんな国? 日本からのイメージ
日本人にとって、ニュージーランドといえば「美しい自然」「羊がたくさんいる国」「『ロード・オブ・ザ・リング』の撮影地」「ラグビーのオールブラックス」などのイメージが強いのではないでしょうか。実際、ニュージーランドは雄大な山々、美しい湖、そして広大な緑の大地が広がる自然豊かな国です。
南太平洋に位置するこの島国は、北島と南島という2つの主要な島からなり、人口は約500万人。日本の約7割の国土に日本の約25分の1の人口が住んでいるため、非常にゆとりのある空間が特徴です。また、南半球に位置するため、季節は日本と逆になります。12月〜2月が夏で、6月〜8月が冬です。このため、クリスマスは真夏に祝うという日本人には新鮮な光景が見られます。
現代のニュージーランドは多文化社会で、先住民マオリの文化を尊重しながら、ヨーロッパ系(主にイギリス系)、アジア系、太平洋諸島系など様々なバックグラウンドを持つ人々が共存しています。また、1893年に世界で初めて女性参政権を認めた国としても知られ、環境保護や社会福祉など、先進的な政策を打ち出す国としても国際的に評価されています。
ニュージーランドで暮らす/ニュージーランドに行くメリットについて
豊かな食材と食文化
ニュージーランドの最大の魅力の一つは、新鮮で質の高い食材が豊富なことです。広大な牧草地で育てられた羊や牛の肉、清浄な海域で獲れる魚介類、肥沃な大地で育つ野菜や果物など、素材の質の高さは世界的にも評価されています。特に乳製品は有名で、バター、チーズ、アイスクリームなどの品質は非常に高いです。
また、多様な文化的背景を持つ人々が共存する社会であるため、様々な国の料理を本格的に楽しむことができます。特に大都市では、アジア料理や地中海料理、中東料理など多様な食文化に触れることができます。
カフェ文化と質の高いコーヒー
ニュージーランドはカフェ文化が非常に発達しており、特に「フラットホワイト」などのエスプレッソベースのコーヒーは世界的にも評価が高いです。休日の朝、カフェでブランチ(朝食と昼食の間の食事)を楽しむという文化は、日本ではなかなか経験できない魅力です。
ワインの産地
マールボロ、ホークスベイ、セントラルオタゴなど世界的に有名なワイン産地があり、特にソーヴィニヨン・ブランやピノ・ノワールは国際的に高い評価を受けています。ワイン好きにはたまらない環境です。
リラックスした食事の時間
「ワーク・ライフ・バランス」を重視するニュージーランドでは、食事の時間もリラックスして楽しむことが一般的です。特に週末のブランチや家族でのディナーなど、ゆったりと食事を楽しむ文化があります。日本の「せかせかと食べる」文化とは対照的で、食事を通じた交流を重視する傾向があります。
環境に配慮した食
ニュージーランドは環境への意識が高く、オーガニック食品や地産地消の動きが活発です。また、食品添加物の使用も比較的少なく、自然に近い形での食品生産が行われています。健康や環境に配慮した食生活を送りたい方にとっては魅力的な環境と言えるでしょう。
① ニュージーランドの食文化の日本との違い(食事)
食事のスタイルと内容
日本の食事は「一汁三菜」に代表されるように、主食(ご飯)を中心に様々なおかずが少しずつ並ぶスタイルが一般的です。一方、ニュージーランドの食事は「一皿完結型」が多く、肉や魚をメインにした一皿に野菜やデンプン質(ジャガイモ、パスタなど)を添える西洋式の構成が一般的です。
特に夕食では、肉料理(特に牛肉、羊肉、豚肉、鶏肉)が中心となることが多く、その量も日本と比べると格段に多いです。例えば、ステーキ一人前のサイズは250g〜400gと、日本の2〜3倍のボリュームがあります。
また、日本では「薄味」「素材の味を活かす」調理法が好まれるのに対し、ニュージーランドでは「しっかりとした味付け」「ハーブやスパイスを効かせる」調理法が多いのも特徴です。
食事の時間帯とリズム
日本と大きく異なるのは食事の時間帯です。一般的に朝食は7時〜9時、昼食は12時〜14時、夕食は17時30分〜19時頃と、特に夕食が日本よりも早い時間に取られます。レストランも日本のように深夜まで営業しているところはほとんどなく、多くは21時頃には閉店します。
また、ニュージーランドでは「ブランチ」という文化が非常に発達しており、特に週末は朝食と昼食をまとめた11時頃の食事を友人や家族と一緒にカフェで楽しむことが一般的です。エッグベネディクト、パンケーキ、アボカドトーストなどの充実したブランチメニューが楽しめるカフェが多くあります。
自炊と外食の位置づけ
日本では「毎日のように外食する」という生活スタイルも珍しくありませんが、ニュージーランドでは外食は比較的高額であるため、日常的には自炊が基本となります。特に夕食は家で家族と一緒に食べるのが一般的です。
一方で、カフェでのブランチや友人との食事会など、「特別な機会」としての外食文化は発達しています。また、テイクアウトも普及しており、「フィッシュ・アンド・チップス」(揚げた魚とポテト)などは新聞紙に包まれて持ち帰り、ビーチや公園で楽しむというスタイルも人気です。
食器と食べ方
日本では箸を使い、丼や茶碗を持ち上げて食べるのが一般的ですが、ニュージーランドではナイフとフォークを使い、皿は持ち上げずに食べるのが基本です。スープにはスプーンを使い、麺料理(パスタなど)を食べる際もフォークを使います。
また、日本では「音を立てて食べない」ことがマナーとされますが、ニュージーランドではそれほど厳格ではなく、むしろ「美味しい」という感想を言葉で表現することが好まれます。
② ニュージーランドの食文化の日本との違い(会話)
食事中の会話のスタイル
日本では「食事中はあまりおしゃべりしない」「口に食べ物を入れている時は会話しない」といった文化がある一方、ニュージーランドでは食事の場はコミュニケーションの重要な機会とみなされています。特に家族の食事では一日の出来事について話したり、様々なトピックについて会話したりすることが一般的です。
レストランでの食事も比較的長時間(1〜2時間)かけて楽しむことが多く、料理を介した会話が食文化の重要な部分を占めています。日本のように「黙々と食べる」スタイルよりも、「食べながら話す」スタイルが一般的です。
食事への感想と表現
日本では料理に対する感想は控えめに表現することが多いですが、ニュージーランドでは料理が気に入った場合は、はっきりと「This is delicious!(美味しい!)」「Compliments to the chef!(シェフに称賛を!)」などと声に出して伝えます。家庭料理でも「素晴らしい料理だね」と感想を述べるのが一般的で、これは料理を作った人への敬意の表れとされています。
また、日本では「たくさん食べる」ことが料理人への感謝や料理の美味しさを示す一方、ニュージーランドでは「言葉で感謝や満足を表現する」ことが重視されます。
もてなしと断り方
日本では客をもてなす際に「遠慮しないで」と何度も勧めることがありますが、ニュージーランドでは一度断った場合は基本的にそれを尊重します。「No, thank you.」と言えば、それ以上勧められることはあまりないでしょう。
また、食べられない物や好みでない物についても、日本では遠慮して黙って少し食べることもありますが、ニュージーランドではより直接的に「I don’t eat pork(豚肉は食べません)」「I’m allergic to shellfish(貝類にアレルギーがあります)」などと伝えることが一般的です。これは失礼にはあたらず、むしろ正直に伝えることが相手への敬意とみなされます。
食事のマナーと期待
日本では「いただきます」「ごちそうさま」という挨拶で食事を始め、終えますが、ニュージーランドにはそのような決まった挨拶はありません。ただし、フォーマルな食事の場では「Bon appétit(召し上がれ)」と言うこともあります。
また、ニュージーランドではチップの文化はありませんが、特に良いサービスを受けた場合には少額のチップを置くことはあります。メニューに表示されている金額には既に税金(GST:物品サービス税)が含まれているので、支払い金額が変わることはありません。
③ ニュージーランドの食文化の日本との違い(記念日/祝日)
クリスマスの食事
日本のクリスマスはケーキとフライドチキンが定番ですが、ニュージーランドのクリスマスは夏の時期(12月)となるため、異なる食文化があります。伝統的なローストターキーやハムなどの料理もありますが、それに加えて海辺でのバーベキューや冷たい料理も人気です。
特に「パブロバ(Pavlova)」というメレンゲをベースにしたケーキの上に生クリームとフルーツをのせたデザートは、クリスマスの定番で、夏の季節に合った軽やかな甘さが特徴です。
日本のようにクリスマスイブが重視されるのではなく、クリスマス当日(12月25日)に家族や親族が集まって食事を楽しむのが一般的です。
イースター
日本ではあまり馴染みのない「イースター(復活祭)」は、ニュージーランドでは重要な祝日です。この時期(3月または4月)には特別な食べ物として「ホット・クロス・バン(Hot Cross Buns)」と呼ばれるスパイスの効いた甘いパンを食べる習慣があります。また、チョコレートの卵やウサギの形をしたお菓子も子どもたちに人気です。
アンザック・デー
4月25日の「アンザック・デー(ANZAC Day)」は、第一次世界大戦でのオーストラリア・ニュージーランド軍団(ANZAC)の兵士たちを追悼する重要な日です。この日には「アンザック・ビスケット(ANZAC biscuits)」というオーツ麦、ココナッツ、シロップなどを使ったクッキーを食べる習慣があります。これは戦時中に前線の兵士に送られていた保存の利く食べ物に由来しています。
日本にはこのような「戦争追悼」と直接結びついた食習慣はあまりなく、独特の文化と言えるでしょう。
マオリの祝日と食文化
2月6日の「ワイタンギの日(Waitangi Day)」はニュージーランド建国の日とも言える重要な祝日で、マオリの伝統料理が注目される機会でもあります。「ハンギ(Hangi)」と呼ばれる地面に掘った穴で熱した石の上に食材を置き、蒸し焼きにする伝統的な調理法で料理が作られることもあります。
日本の祝日が季節の変わり目やアジアの伝統に基づくものが多いのに対し、ニュージーランドの祝日は歴史的な出来事や国の成り立ちに関連するものが多いのが特徴です。
季節を祝う食文化
日本には季節の変わり目を祝う食文化(桜餅、柏餅、土用の丑の日のうなぎなど)が豊かにありますが、ニュージーランドではそのような細かな季節の区切りに基づく食文化は少ないです。ただし、季節の食材を楽しむという点では共通しており、夏にはベリー類やマンゴー、冬にはカボチャや根菜類など、旬の食材を取り入れた料理が楽しまれます。
④ ニュージーランドの食文化の日本との違い(おふくろの味)
家庭料理の定義と位置づけ
日本では「おふくろの味」といえば、母から娘へと受け継がれる伝統的なレシピや、家族の好みに合わせた独自のアレンジが加えられた料理を指すことが多いですが、ニュージーランドの家庭料理は地域や家族のルーツによって大きく異なります。
ニュージーランドは移民の国であるため、「定番の家庭料理」も家族のバックグラウンド(イギリス系、マオリ系、アジア系など)によって様々です。イギリス系の家庭ではローストディナーやパイ、アジア系の家庭では自国の伝統料理など、文化的背景によって「おふくろの味」の定義が異なるのが特徴です。
代表的な家庭料理
伝統的なニュージーランドの家庭料理としては、「シェパーズパイ」(ひき肉とマッシュポテトのグラタン)、「ミートパイ」(肉の入ったパイ)、「ラム肉のロースト」などがあります。これらはイギリスの食文化の影響を強く受けています。
日本の家庭料理が野菜や魚を多く使った健康的な食事が多いのに対し、ニュージーランドの伝統的な家庭料理は肉がメインとなることが多いです。ただし、近年は健康志向の高まりから、野菜を多く取り入れた食事や世界各国の料理を取り入れる家庭も増えています。
料理の伝承方法
日本では「母から娘へ」という形で家庭料理のレシピが伝えられることが多いですが、ニュージーランドでは料理本やインターネット、最近ではクッキングショーやYouTubeなどからレシピを取り入れることが一般的です。
ニュージーランドではより柔軟に「自分なりにアレンジする」傾向があり、明確な「正しいレシピ」という概念が日本ほど強くない印象があります。これは「DIY(Do It Yourself)」精神が根付いた国民性の表れかもしれません。
家族の食事に対する考え方
日本では「家族揃って同じものを食べる」という考え方が一般的ですが、ニュージーランドでは個人の好みや食事制限に合わせた別メニューを用意することも珍しくありません。例えば、ベジタリアンの家族メンバーがいれば、その人用に肉を使わない料理を用意するといった柔軟性があります。
また、日本では「母親が家族のために料理を作る」という伝統的な役割分担がまだ残っている部分がありますが、ニュージーランドでは性別に関わらず料理を担当する、あるいは家族全員で料理を分担することが一般的です。特に「バーベキュー」などは男性が中心となることも多いです。
⑤ ニュージーランドの食文化の日本との違い(その他)
飲み物の文化
日本では食事と一緒にお茶(緑茶)を飲むことが一般的ですが、ニュージーランドでは水が基本的な飲み物です。また、コーヒー文化が非常に発達しており、特に「フラットホワイト」「ロングブラック」などのエスプレッソベースのコーヒーが人気です。日本のように緑茶が日常的に飲まれることはありません。
アルコール飲料に関しては、ビールやワインが食事と一緒に楽しまれることが多く、特にニュージーランド産のワイン(ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・ノワールなど)は国際的にも評価が高いです。日本酒や焼酎のように蒸留酒を食事と共に飲む文化はあまり見られません。
食品ロスとリサイクルへの意識
ニュージーランドは環境意識が高く、食品ロスの削減やリサイクルへの取り組みが進んでいます。多くの家庭では生ごみのコンポスト(堆肥化)を行い、庭の肥料として利用する習慣があります。また、スーパーマーケットでも食品ロス削減のための取り組み(値引き販売、フードバンクへの寄付など)が行われています。
日本も食品ロス削減への意識は高まっていますが、ニュージーランドでは特に個人レベルでの取り組みが日常生活に根付いている印象があります。
食の多様性と寛容性
多文化社会であるニュージーランドでは、様々な食文化に対する寛容性が高いのが特徴です。ベジタリアン、ビーガン、グルテンフリー、ハラールなど、様々な食の制限や選択に対応したメニューが一般的なレストランでも提供されています。
日本では特定の食の制限がある場合、外食が難しいケースもありますが、ニュージーランドではそれらに対する理解と対応が進んでいます。これは異なる文化的背景を持つ人々が共存する社会であるからこそ発展した特徴と言えるでしょう。
「フードマイル」への意識
ニュージーランドでは「フードマイル」(食べ物が生産されてから消費者の口に入るまでに移動した距離)への意識が高く、地産地消を推進する動きが活発です。ファーマーズマーケットも各地で開催され、地元の食材を直接生産者から購入することが一般的です。
日本でも地産地消の考え方はありますが、ニュージーランドでは特に環境への配慮という観点からより強く意識されている印象があります。
まとめ
ニュージーランドと日本の食文化には、それぞれの歴史的背景や地理的条件、文化的価値観を反映した興味深い違いがあります。日本の食文化が繊細さ、季節感、伝統の継承を重視するのに対し、ニュージーランドの食文化は多様性、カジュアルさ、実用性を特徴としています。
食事のスタイルでは、日本の「一汁三菜」に対してニュージーランドは「一皿完結型」が中心で、特に肉料理のボリュームに大きな違いがあります。また、食事中の会話の量や内容、感想の伝え方にも文化的な違いが見られます。
祝日や記念日の食習慣も、各国の歴史や気候を反映しており、ニュージーランドの夏のクリスマスや、マオリの伝統を取り入れた食文化は日本とは大きく異なります。家庭料理(「おふくろの味」)の概念も、多文化社会ならではの多様性があります。
これらの違いを知ることで、ニュージーランドでの生活や旅行がより豊かな経験となることでしょう。異なる食文化を尊重し、新しい味や習慣に挑戦することで、視野を広げ、新たな発見が得られるはずです。
ニュージーランドの食文化は、その多様性と寛容性、環境への配慮といった特徴から、現代社会における食のあり方について考えるヒントも与えてくれます。「おいしく、楽しく、持続可能に」食を楽しむニュージーランドの姿勢は、これからの食文化のあり方を考える上で参考になるのではないでしょうか。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。