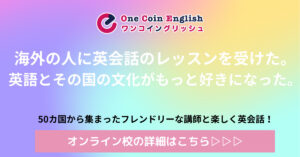【イタリアの文化を学ぶ!】知っておきたいイタリア生活のリアル ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

グローバル化が進む中、異文化を理解することは、私たちの視野を広げ、新しい発見をもたらしてくれます。日本人にとっての当たり前が、海外では違って見えるように、イタリアの日常は私たち日本人に新鮮な気づきを与えてくれるはずです。
本記事では、日本在住のイタリア人にインタビューを行い、イタリアの文化や生活について詳しく解説します。留学や長期滞在、移住を考えている方はもちろん、旅行者の方にも参考になる情報が満載です。
イタリアってどんな国? 日本からのイメージ
ピザ、パスタ、ジェラート、ファッション、美術、歴史的建造物…皆さんはイタリアと聞いて、どんなイメージを持ちますか?
イタリアは南ヨーロッパに位置する長靴の形をした国で、地中海性気候に恵まれ、北部のアルプス山脈から南部のシチリア島まで、多様な風景を楽しめます。古代ローマ帝国の遺産が今なお残り、ルネサンス発祥の地として芸術や文化が栄えてきた歴史があります。
現代のイタリアは、20の州(レジョーネ)からなる共和国で、それぞれの地域が独自の伝統、方言、料理を持っています。北部は工業が発達し、経済的に豊かな地域である一方、南部は農業が中心の素朴な生活が残っているなど、同じ国内でも地域による違いが大きいのが特徴です。
イタリア人は「生活を楽しむ」ことを大切にし、食事や家族との時間、美しいものを愛でる感性を持っています。同時に、情熱的で表現力豊かなコミュニケーションスタイルも特徴的です。「ドルチェ・ヴィータ(甘い生活)」という言葉に象徴されるように、生活の質を重視する文化があります。
イタリアで暮らすメリットについて
メリット1:食文化の豊かさ
イタリアの食は単なる栄養摂取ではなく、生活文化の中心です。新鮮な地元産の食材を使った料理、朝のエスプレッソから始まる一日、地域ごとに異なる郷土料理の多様性など、食の楽しみが日常に溢れています。特に、市場で生産者から直接購入する新鮮な食材の質の高さは特筆すべきです。また、スローフード運動発祥の国として、食事の時間を大切にし、家族や友人と会話を楽しみながら食べる文化があります。これは日本の忙しい生活とは対照的に、人間関係を深める機会となっています。
メリット2:芸術と歴史に囲まれた生活
イタリアでは日常的に芸術や歴史的建造物に触れる機会があります。世界遺産の数が最も多い国のひとつで、街を歩くだけでルネサンス期の建築や古代ローマの遺跡に出会えます。多くの美術館や博物館、教会には世界的に有名なアーティストの作品が展示されており、文化的な刺激に溢れた環境で生活できます。また、地域ごとのお祭りや伝統行事も頻繁に開催され、生きた文化を体験できる機会が豊富です。
メリット3:温暖な気候と自然環境
イタリアの多くの地域は地中海性気候に恵まれ、温暖で過ごしやすい気候が特徴です。特に中部から南部にかけては日照時間が長く、屋外での活動を楽しむ機会が多いです。アルプス山脈、トスカーナの丘陵地帯、アマルフィ海岸など変化に富んだ自然環境があり、四季折々の美しい風景を楽しめます。この気候は心身の健康にも良い影響を与え、特に冬季うつが少ないという研究結果もあります。また、気候を活かした屋外カフェでの時間や、ビーチでのリラックスした休日も生活の質を高めています。
メリット4:ライフスタイルのバランス
イタリアでは「仕事をするために生きるのではなく、生きるために仕事をする」という価値観が根付いています。昼休みが長く取られ、家族と食事をする時間が確保されていることや、休暇を十分に取得する文化は、ワークライフバランスの良さを示しています。また、パッシオーネ(情熱)を持って仕事に取り組む姿勢と、プライベートを大切にするメリハリのある生活スタイルが特徴です。地元のコミュニティの繋がりが強く、特に小さな町では近所付き合いや地域のイベントを通じた社会的な絆が生活の支えになっています。
① 知っておきたいイタリア生活のリアル(買い物)
―日本と違う!と思った買い物の仕方とか、買ったものってある?
マルカート(市場)文化が今でも生きているのが大きな違いですね。イタリアの多くの町では週に何日か、広場や決まった場所で市場が開かれます。新鮮な野菜や果物、チーズ、オリーブオイル、パンなどが並び、地元の生産者から直接買えるのが魅力です。スーパーマーケットも利用しますが、やはり品質や鮮度にこだわる人は市場に行きます。特に野菜や果物は季節によって品揃えが変わり、旬のものを買うことが一般的です。市場では売り手と会話しながら選ぶことも楽しいですし、常連になると少しおまけしてくれたりする関係性も生まれます。
営業時間の独特なリズムにも驚くかもしれません。多くの店は午後1時から4時頃まで「リポーゾ(休憩)」と呼ばれる昼休みで閉まります。特に小さな街では厳格で、この時間は本当に何も買えません。その代わり、夕方から夜は遅くまで開いていることが多いです。また、日曜日は基本的にお店が閉まっていて、家族で過ごす日という考え方が今でも強いです。最近は大型ショッピングモールなどは日曜営業していますが、伝統的な商店街は閉まっていることが多いので、買い物の計画はしっかり立てておく必要があります。
「ファルマチア(薬局)」の役割も日本とは少し違います。薬局は街の中で緑の十字のマークですぐに見つけられます。処方箋薬だけでなく、一般的な風邪薬やサプリメント、化粧品、ベビー用品なども扱っています。イタリアでは薬剤師の社会的な信頼が高く、軽い症状なら病院に行く前に薬局で相談するという文化があります。薬剤師が症状を聞いて市販薬をすすめてくれたり、必要なら医師への受診を勧めてくれたりします。24時間営業や当番制の薬局もあり、緊急時には助かります。
支払い方法にも違いがあります。最近はクレジットカードやデビットカードの利用が増えていますが、まだ現金主義の店も多いです。特に小さな商店や市場では現金のみという場合もあります。また、「スコントリーノ(レシート)」は必ず受け取って持っていることが重要です。イタリアでは税金対策のため、店を出てすぐに財務警察がレシートの提示を求めることがあります。もし持っていないと、客である自分も罰金を払わなければならない場合があるので注意が必要です。
買い物のコミュニケーションも異なります。店に入ったら「ボンジョルノ(こんにちは)」と挨拶するのが基本マナーです。質問があれば積極的に話しかけるのが当たり前で、黙って商品を見ているだけだと「何か手伝いが必要?」と声をかけられることも多いです。特に衣料品店では店員がかなり接客してくるので、「見ているだけ」という場合でも丁寧に伝える必要があります。また、市場では値段交渉ができることもあり、特に観光地では最初から高めの価格設定になっていることもあるので、少し交渉するのも楽しみの一つです。
② 知っておきたいイタリア生活のリアル(食事)
―イタリアの食事で、え!って思ったことある?
まず、食事の時間帯が日本とかなり違います。朝食(コラツィオーネ)は軽めで、通常はエスプレッソやカプチーノと甘いペストリーやビスケットだけというシンプルさです。昼食(プランゾ)は12時半から2時頃までで、これが一日で最も重要な食事とされています。そして夕食(チェーナ)は早くても7時半から、多くは8時や9時頃に始まることも珍しくありません。特に夏は涼しくなる夜にゆっくり食事をする習慣があります。観光客向けのレストランを除き、6時頃に夕食を食べようとすると「まだ準備ができていません」と言われることもあります。
「食事の順番」も独特です。イタリアの食事はコースで進みます。通常、前菜(アンティパスト)、第一の皿(プリモ・ピアット)としてパスタやリゾット、第二の皿(セコンド・ピアット)として肉や魚のメインディッシュ、そして付け合わせ(コントルノ)、最後にデザート(ドルチェ)とエスプレッソ、時にはディジェスティーボと呼ばれる食後酒が出されます。ただし、日常の食事ではこれらすべてを食べるわけではなく、プリモとセコンドのどちらかだけというのも普通です。特別な日やレストランでの食事の際にはフルコースで楽しみます。
イタリア人がパスタについて持つ「ルール」の厳格さには驚くかもしれません。例えば、パスタとソースの組み合わせは非常に重要で、間違えると真剣に指摘されることがあります。スパゲッティにボロネーゼソースを合わせるのは「あり得ない」とされ、本来はタリアテッレなどの平たいパスタに合わせるべきだと言われます。また、パスタを食べる時にスプーンを使うのはイタリア人には子供っぽく見えます。さらに、パスタを切るのは絶対NGで、フォークでくるくると巻いて食べるのが正しい作法です。
コーヒー文化にも厳格なルールがあります。カプチーノは朝の飲み物であり、食後や午後に飲むのはイタリア人には考えられないことです。特に食事の後にカプチーノを注文すると奇妙な目で見られることがあります。昼食や夕食の後は「カフェ」(エスプレッソ)が一般的です。また、コーヒーを飲む時間もユニークで、多くのイタリア人は朝食時、午前中のブレイク、昼食後、午後のブレイク、そして夕食後と、一日に何度もエスプレッソを飲む習慣があります。ただし、一杯のエスプレッソは小さく、立ったままバールで数分で飲み干すのが一般的です。
イタリアの地域による食文化の違いも特筆すべきです。「イタリア料理」と一括りにされがちですが、実際には20の州それぞれに特徴的な料理があります。北部のピエモンテでは豊かなバターとリゾット、中部のトスカーナでは素朴なパンとオリーブオイル、南部のナポリではピッツァやトマトベースの料理、シチリアではアラブの影響を受けた甘いデザートなど、それぞれの地域が独自の食文化を誇りにしています。地域間のライバル意識もあり、「本物のカルボナーラはローマのもの」などと主張されることもあります。
―家で料理するときは、どんなものを作るの?
イタリアの家庭料理はシンプルさが基本です。「クチーナ・ポーヴェラ(貧しい料理)」という言葉がありますが、これは決して否定的な意味ではなく、シンプルな食材を最大限に活かした知恵のある料理という意味です。例えば「パスタ・アル・ポモドーロ」は基本中の基本で、良質なトマト、オリーブオイル、ニンニク、バジルだけで作る素朴ながら奥深いパスタです。家庭料理で大切なのは食材の質で、多くの家庭では週に何度か市場に行って新鮮な野菜や果物、肉、魚を買います。
「フリッタータ」も家庭の定番料理です。これは残り物の野菜や肉、チーズなどを入れて作る卵料理で、日本のだし巻き卵のようなものですが、具がたっぷり入っています。冷蔵庫にある食材で手軽に作れるため、忙しい平日の夕食としても人気です。また、パンがパリパリになってきたら「パンツァネッラ」というサラダにしたり、古くなったパンを使って「リボリータ」というスープを作ったりと、食材を無駄にしない工夫も伝統的な家庭料理の知恵です。
日曜日は特別な食事の日で、多くの家庭では時間をかけて調理します。典型的な日曜のメニューとしては、前菜にサラミやチーズの盛り合わせ、第一の皿にラザニアやミートソースのパスタ、第二の皿に「アッロスト」と呼ばれるローストチキンやビーフ、付け合わせにロースト野菜やサラダ、そしてデザートにティラミスやパンナコッタなどが登場します。こうした豪華な日曜の食事には、しばしば祖父母や親戚も招かれ、長時間かけて楽しむ大切な家族の時間となっています。
地域や家庭の伝統レシピも大切にされています。例えば、クリスマスには「パネットーネ」や「トローネ」などの伝統的なお菓子、カーニバルには「フラッペ」というお菓子、イースターには「コロンバ」というケーキを作る家庭が多いです。こうした特別な日の料理は、母から娘へと代々受け継がれることが多く、家族の遺産とも言える大切なレシピです。また、「ノンナ(おばあちゃん)のレシピ」は特別な価値を持ち、「ノンナの味」はどんな高級レストランの料理よりも優れているというプライドがあります。
平日の夕食は比較的シンプルになります。「パスタ・アル・トンノ」(ツナのパスタ)や「リゾット・アッラ・ミラネーゼ」(サフランリゾット)、「スカロッピーネ」(薄切り肉のソテー)など、準備が簡単でありながら美味しい料理が一般的です。また、前の日の残り物をアレンジすることも多く、例えばリゾットが余れば翌日は「スッピリ」(ライスコロッケ)にするといった工夫もされています。南部では特に「ミネストローネ」などの野菜たっぷりのスープも定番で、夏でも冬でも一年中楽しまれています。
③ 知っておきたいイタリア生活のリアル(休日)
―休日ってどんな感じで過ごすの?
イタリアの休日の過ごし方は「家族中心」が特徴です。特に日曜日は伝統的に家族の日とされ、午前中にミサ(教会の礼拝)に行く人もいますが、その後は大家族で集まって長い昼食を楽しむのが一般的です。この昼食は単なる食事というより社交イベントで、祖父母、叔父叔母、いとこなども含めた拡大家族が集まり、最新のニュースや家族の出来事について話し合います。食事は2〜3時間かけてゆっくり楽しみ、その後はくつろいだり、サッカーの試合を見たり、近所を散歩したりして過ごします。
週末や祝日には「パッセジャータ」(散歩)の習慣があります。特に夕方から夜にかけて、家族や友人と町の中心部を歩きながらおしゃべりを楽しむのです。この時間帯は「パッセジャータ」をする人々で町が賑わい、特に小さな町では地元の人々がほぼ全員参加するような社交の場になります。また、カフェに座ってエスプレッソやアペリティーボ(軽食付きの飲み物)を楽しみながら人々の往来を観察するのも休日の楽しみ方です。この「何もせずにただ時間を過ごす」という余暇の楽しみ方は、イタリア人の「ドルチェ・ファル・ニエンテ」(甘い何もしない時間)という生活哲学の表れです。
夏の休暇は特に重要で、多くのイタリア人は8月に2〜4週間の長期休暇を取ります。この時期、特に8月中旬のフェラゴスト(聖母被昇天祭)の前後は、都市部は閑散とし、多くの店やレストランが閉まります。イタリア人の多くは海辺のリゾートや山の別荘、田舎の実家などに長期滞在します。海岸では「バニョ」と呼ばれるビーチクラブでパラソルとサンベッドをレンタルし、一日中海水浴や日光浴を楽しみます。夕方には「アペリティーボ」、夜には海辺のレストランでシーフードを楽しむというのが典型的な夏休みの過ごし方です。
イタリア人の休日は「季節感」を大切にします。春は花見やピクニック、夏は前述のように海や山での避暑、秋はワイン祭りやトリュフ狩り、冬はスキーやクリスマスマーケットなど、季節ごとの楽しみがあります。また、各地方や町には守護聖人の祝日があり、この日は地元の祭りとなって屋台や音楽、花火などで賑わいます。特に南部では、こうした宗教的な祭りが今でも社会生活の重要な部分となっています。
休日の過ごし方にも地域差があります。北部ではアウトドア活動やスポーツを楽しむことが多く、トレッキングやサイクリング、スキーなどが人気です。一方、南部ではより伝統的な家族との時間やゆったりとした社交の時間を重視する傾向があります。また、大都市と小さな町でも休日の過ごし方は異なり、ローマやミラノなどの大都市ではカフェ文化や美術館・博物館巡り、ショッピングなどの都会的な楽しみ方がある一方、小さな町では地域のイベントやコミュニティとの交流がより重要な位置を占めています。
④ 知っておきたいイタリア生活のリアル(家族)
―家族との過ごし方って、日本とどう違うの?
イタリアにおける家族の概念は非常に広く、「ファミリア」には両親、兄弟姉妹だけでなく、祖父母、叔父叔母、いとこ、そして時には親族ではない親しい友人までもが含まれることがあります。こうした拡大家族との絆は非常に強く、定期的に集まって食事をしたり、お互いの生活に関わったりすることが一般的です。実際、多くのイタリア人にとって、週に1〜2回は親戚と集まる機会があり、特に日曜日の昼食は家族の集いの場となっています。こうした強い家族の絆は社会的なセーフティネットとしても機能し、経済的な困難や健康問題など、人生の様々な局面で家族の助けを求めることが自然と受け入れられています。
親と子の関係も特徴的です。イタリアでは「マンマ(お母さん)」の役割が特に重要で、「マンマイズモ」という言葉があるほど母親との絆が強調されます。子供が成人後も親と同居したり、近くに住んだりすることも珍しくなく、特に未婚の若者は30代になっても実家に住んでいることがあります。これには住宅費の高さという経済的な理由もありますが、文化的に「巣立ち」を急ぐ必要がないという考え方も強いです。「マンマ(お母さん)」は食事の準備から洗濯、家事全般を担うことが多く、子供(特に息子)の日常生活のサポートをすることが当たり前と考えられていることもあります。
祖父母(ノンノ、ノンナ)も家族の中で重要な役割を果たします。イタリアでは共働き家庭が増えている中、祖父母が孫の世話を担うことが一般的です。特に南部や小さな町では、祖父母が日中孫の面倒を見たり、学校の送り迎えをしたりする光景が日常的に見られます。こうした祖父母の存在は、単なる「子守役」としてだけでなく、伝統や文化、価値観を次世代に伝える重要な役割も担っています。また、高齢者が社会から孤立することが少なく、家族の一員として活発に生活に参加している点も特徴的です。
食事は家族の絆を深める最も重要な時間です。イタリアの食卓では、単に食べるだけでなく、会話を楽しみ、一日の出来事を共有し、時には熱い議論を交わす場となります。特に日曜日の昼食は「サクロサンタ(神聖な)」とも言われるほど重要で、この時間は家族が必ず集まるべきものとされています。食事の準備も家族の協力で行われることが多く、小さな子供も年齢に応じて手伝いに参加することで、料理の知識や技術、家族の伝統レシピを自然と学んでいきます。
家族の関係においては「感情表現の豊かさ」も特徴です。イタリア人は喜びも怒りも全て包み隠さず表現する傾向があり、家族間での言い合いや感情的な議論も珍しくありません。しかし、こうした言い合いも「愛情表現の一形態」と捉えられており、感情を抑制するよりもオープンに表現する方が健全だという考え方があります。「クアレル(言い争い)」の後にすぐに仲直りして、何事もなかったかのように和やかな会話に戻るのもイタリア的です。この感情表現の豊かさは、家族間の強い絆と信頼関係があってこそ成り立つものと言えるでしょう。
―イタリアでは、クリスマスや新年はどう過ごす?
「ナターレ(クリスマス)」はイタリアで最も重要な祝祭の一つで、家族が集まる特別な機会です。クリスマスの準備は12月8日の「無原罪の御宿り」から始まり、この日に多くの家庭でクリスマスツリーを飾り、「プレセーペ(キリスト生誕場面)」と呼ばれるキリスト誕生の情景を再現した飾りを設置します。クリスマス・イブ(12月24日)の夜には「チェナ・デッラ・ヴィジリア(見張りの夕食)」という特別な夕食を家族で楽しみます。地域によって献立は異なりますが、魚料理が中心となることが多く、特に「バッカラ(塩漬けタラ)」や「キャピトーネ(ウナギ)」が伝統的に食べられます。
クリスマス当日(12月25日)は「プランゾ・ディ・ナターレ(クリスマスの昼食)」が最も重要な行事で、拡大家族全員が集まって豪華な食事を楽しみます。この食事は地域によって異なりますが、北部では詰め物をした七面鳥や「ボッリート・ミスト(煮込み肉の盛り合わせ)」、中部では「トルテッリーニ・イン・ブロード(スープに入ったトルテッリーニ)」、南部では「ストルッフォリ(蜂蜜をかけた小さな揚げ菓子)」などが定番です。また、全国的に「パネットーネ」や「パンドーロ」といった特別なクリスマスケーキも欠かせません。子供たちへのプレゼントは、北部では「バッボ・ナターレ(サンタクロース)」が、中部や南部では1月6日に「ベファーナ(魔女)」が届けるという地域差もあります。
「カポダンノ(新年)」もイタリアでは盛大に祝われます。大晦日の夜には「チェノーネ・ディ・サン・シルヴェストロ(聖シルヴェストロの大晩餐)」と呼ばれる豪華な晩餐を家族や友人と楽しみます。この日の食事には縁起物として「レンティッキエ(レンズ豆)」が必ず含まれ、その形がコインに似ていることから一年の幸運と富をもたらすと信じられています。また、「ザンポーネ」や「コテキーノ」と呼ばれる特別なソーセージもこの日の定番です。真夜中にはシャンパンで乾杯し、南部では「幸運を呼ぶ」という意味で古い物を窓から投げ捨てる習慣もあります(現在はほとんど行われませんが)。
新年の日(1月1日)は家族で過ごすことが多く、昼食で再び集まります。そして1月6日の「エピファニア(公現祭)」で祝祭シーズンは締めくくられます。この日は「ベファーナ」と呼ばれる良い子に贈り物、悪い子に石炭(実際は黒砂糖のお菓子)を届ける魔女の伝説と結びついており、子供たちにとって再びプレゼントをもらえる楽しい日となっています。
イタリアではクリスマスや新年を通じて「家族との時間」と「食事」が最も重視されています。特に南部では宗教的な要素がより強く残っており、クリスマス・イブにはミサに参加する家族も多いです。一方、都市部では宗教的な側面は薄れつつあり、家族の集いと贈り物を交換する社交的な祝祭という面が強くなっています。いずれにせよ、イタリア人にとってこの時期は一年で最も大切な家族の時間であり、伝統を受け継ぎ次世代に伝える重要な機会となっています。
―イタリアでは、日本にはない休日はある? そのときにすることは?
「フェラゴスト(Ferragosto)」は8月15日の「聖母被昇天祭」に由来する夏の重要な祝日です。現在では宗教的な意味合いよりも、「夏のバカンス」の象徴として知られています。この時期、多くのイタリア人は2〜4週間の休暇を取り、海辺や山の避暑地に出かけます。都市部は閑散とし、多くの店やレストランが閉まります。伝統的にはビーチでのピクニックや家族での食事を楽しむ日で、海水浴や日光浴、夜には花火や音楽イベントなどが開催されることも多いです。フェラゴストの起源はローマ帝国時代にまで遡り、皇帝アウグストゥスが制定した夏の休暇「フェリアエ・アウグスティ(アウグストゥスの休日)」に由来しています。
「カーネヴァーレ(謝肉祭)」はキリスト教の四旬節(復活祭前の40日間の断食期間)が始まる前の祝祭で、2月頃に催されます。期間は地域によって異なりますが、最終日の「マルテディ・グラッソ(脂肪の火曜日)」で終わります。この祭りでは仮装や山車のパレード、仮面舞踏会などが行われ、特にヴェネツィア、ヴィアレッジョ、イヴレアなどの町では盛大に祝われます。子供たちは仮装して学校に行き、「コリアンドリ(紙吹雪)」や「ステッレ・フィランティ(スパークラー)」で遊びます。また、「フラッペ」や「キアッキエレ」といった揚げ菓子も、この時期の定番です。カーネヴァーレは「肉よ、さようなら」という意味で、断食期間前に肉や脂肪たっぷりの食事を楽しむ最後の機会とされています。
「パスクア(復活祭)」は日本では大きなイベントではありませんが、イタリアではクリスマスと並ぶ重要な宗教的祝日です。春の訪れを祝う行事でもあり、日曜日の「パスクア」本日と翌月曜日の「パスクエッタ(小さな復活祭)」は国民の祝日となっています。復活祭には「コロンバ・パスクアーレ」と呼ばれる鳩の形のケーキや、大きなチョコレートの卵「ウォーヴォ・ディ・パスクア」を食べる習慣があります。このチョコレート卵は中に小さなプレゼントが入っているのが特徴で、子供たちに人気です。復活祭の月曜日は家族や友人と郊外に出かけてピクニックをする日で、この日には「トルタ・パスクアリーナ(イースターパイ)」などの特別な料理を楽しみます。
「サント・パトローノ(守護聖人の祝日)」はイタリアの各都市や町が独自に祝う特別な日です。例えば、ローマでは6月29日の「サン・ピエトロとサン・パオロの日」、ミラノでは12月7日の「サンタンブロージョの日」、ナポリでは9月19日の「サン・ジェンナーロの日」などがあります。この日はその地域だけの地方祝日となり、学校や多くの職場が休みになります。守護聖人を祝うパレードや宗教的な行事、市場、コンサート、花火などが開催され、地元の人々にとって一年で最も重要なお祭りとなっています。各地域の守護聖人の祝日には、その土地ならではの特別な食べ物や伝統があり、地域のアイデンティティを強く反映しています。
「レプッブリカ(共和制記念日)」は6月2日に祝われる国民の祝日で、1946年のイタリア共和国成立を記念しています。この日には首都ローマで軍事パレードが行われ、大統領が参列します。全国の主要都市でも式典やイベントが開催され、多くの建物にイタリア国旗が掲げられます。比較的新しい祝日ですが、イタリア人のナショナル・アイデンティティを確認する重要な日となっています。家族や友人と集まってピクニックやバーベキューを楽しんだり、長い週末を利用して小旅行に出かけたりする人も多いです。この日は政治的な性格も持ちますが、多くのイタリア人にとっては単に「初夏の休日」として、屋外での活動や食事を楽しむ機会となっています。
⑤ 知っておきたいイタリア生活のリアル(その他)
―イタリア人に人気のスポーツとか、エンターテイメントって何?
「カルチョ(サッカー)」はイタリアで断トツの人気を誇る国民的スポーツです。イタリア人の多くは地元のチームのサポーターであり、特にセリエA(イタリアのトップリーグ)の試合がある日曜日は、友人や家族と集まってテレビ観戦したり、スタジアムに足を運んだりします。ユヴェントス、ACミラン、インテル、ローマ、ナポリなどの大クラブは熱狂的なファンを持ち、チーム間のライバル意識も非常に強いです。サッカーはただのスポーツを超えて、社会的アイデンティティや地域の誇りと結びついており、試合の結果は翌日の会話の中心話題になります。イタリア代表チーム「アッズーリ」の国際試合ともなれば、国中が一体となって応援する大イベントです。
「バー文化」もイタリアのエンターテイメントの重要な部分です。特に夕方から始まる「アペリティーボ」の時間は、仕事帰りに友人と待ち合わせて軽い飲み物と軽食を楽しむ社交の場となっています。多くのバーでは飲み物を注文すると小さなおつまみが無料で提供されたり、ビュッフェ形式の軽食が用意されていたりします。この習慣はミラノなどの北部都市で特に発達していますが、今では全国に広がっています。アペリティーボの定番ドリンクには「スプリッツ」「ネグローニ」「カンパリソーダ」などがあり、夕食前の軽い一杯としてだけでなく、友人との会話を楽しむ社交の場として重要な役割を果たしています。
「パッセジャータ(散歩)」もイタリア人の大好きな余暇の過ごし方です。特に週末の夕方になると、町の中心部や海辺のプロムナードは散歩をする人々で賑わいます。ドレスアップして出かけ、知人に会えば立ち止まっておしゃべりを楽しみ、カフェに寄ってエスプレッソやジェラートを味わう…これが典型的なイタリア式の散歩です。特に小さな町では「コルソ」と呼ばれるメインストリートが社交の中心となり、若者は異性との出会いの場としても活用します。この習慣は特に南部で強く残っており、家族全員で夕涼みを兼ねた散歩を楽しむ光景がよく見られます。
「オペラ」や「クラシック音楽」もイタリアの重要な文化的エンターテイメントです。ミラノの「ラ・スカラ座」やナポリの「サン・カルロ劇場」などの歴史的な劇場では、世界的に有名な作品が上演されています。ヴェルディやプッチーニなどのイタリア人作曲家のオペラは特に人気があり、「椿姫」「アイーダ」「トスカ」などは定番のレパートリーです。夏には「アレーナ・ディ・ヴェローナ」のような野外劇場でのオペラフェスティバルも開催され、地元の人々だけでなく観光客も多く訪れます。イタリア人は音楽への造詣が深く、クラシック音楽のコンサートに出かけることも一般的な娯楽の一つです。
「食のイベント」もイタリア中で人気のエンターテイメントです。「サグラ」と呼ばれる地元の食材や料理を祝うお祭りが年間を通じて各地で開催されます。例えば「サグラ・デル・タルトゥーフォ(トリュフ祭り)」や「サグラ・デッラ・ポルケッタ(子豚の丸焼き祭り)」など、地域の特産品に焦点を当てたイベントが数多くあります。また、ワインの新酒ができる秋には「ヴィンデンミア(ブドウの収穫)」のお祭りが各ワイン産地で開かれ、地元の人々だけでなく近隣の町からも多くの人が訪れます。こうした食のイベントでは、地元の料理を味わいながら伝統音楽やダンスを楽しむことができ、イタリア人の「食べることへの情熱」と「お祭り好き」が見事に融合しています。
―イタリア人に人気の観光地って、外国人があまり行かないところだと?
「マレンマ」はトスカーナ州南部からラツィオ州北部にかけての沿岸地域で、イタリア人の休暇先として人気がありますが、外国人観光客にはあまり知られていません。かつては湿地帯でマラリアの影響もあり「不毛の地」と呼ばれていましたが、現在は美しい自然と豊かな農業地帯に変わっています。この地域には中世の村々、エトルリア文明の遺跡、温泉、そして手つかずの美しいビーチがあります。特に「カポディモンテ」「カスティリオーネ・デッラ・ペスカイア」「オルベテッロ」などの町は、夏になるとイタリア人家族の避暑地となります。地元の料理も魅力的で、猪肉の煮込み「チンギアーレ」や手打ちパスタ「ピーチ」などが楽しめます。
「チレント地方」はカンパニア州南部の沿岸地域で、美しい海岸線と国立公園で知られていますが、同じ州のアマルフィ海岸やカプリ島などに比べると外国人観光客は少ないです。「パエストゥム」にあるギリシャ神殿や「チェルトーザ・ディ・パドゥーラ」といった文化的な見どころに加え、「マリーナ・ディ・カメローラ」や「アッチャローリ」などのビーチリゾートも人気です。特に「チレント式地中海ダイエット」の発祥地でもあり、オリーブオイル、トマト、モッツァレラチーズなどを使ったシンプルで健康的な料理が楽しめます。また、「モッツァレラ・ディ・ブーファラ」の本場でもあり、地元でこの新鮮なチーズを味わえることも魅力です。
「フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア」は北東部に位置する州で、スロベニアとオーストリアに国境を接しています。この地域は「プロセッコ」などのワインで有名ですが、外国人観光客の多くはベネチアなどの有名都市にとどまり、この地域まで足を延ばしません。州都の「トリエステ」は中央ヨーロッパの雰囲気を持つエレガントな港町で、歴史的なカフェや広場、ハプスブルク帝国時代の建築が楽しめます。内陸部には「チヴィダーレ・デル・フリウーリ」などの中世の町や、「コッリオ」などのワイン産地があり、美しい丘陵地帯の風景が広がります。この地域の料理はスラブやオーストリアの影響を受けたユニークなもので、「グラース」と呼ばれるスロベニア風のスパイシーシチューや「フリコ」というチーズのフリッターなどが特徴です。
「プーリア州」のガルガーノ半島は、「イタリアの拍車」と呼ばれる半島部分で、美しい海岸線と透明度の高い海が魅力です。「ヴィエステ」や「ペスキチ」などの町には白い砂浜のビーチがあり、夏にはイタリア人家族の避暑地となります。内陸部には「フォレスタ・ウンブラ」という原生林があり、トレッキングを楽しむこともできます。また、「サン・ジョヴァンニ・ロトンド」は聖パードレ・ピオの聖地として多くの巡礼者が訪れる場所でもあります。この地域の名物料理には「オレキエッテ・コン・チーマ・ディ・ラーパ」(耳の形をしたパスタと葉野菜の炒め物)や新鮮なシーフードがあります。
「バジリカータ州」の「マテーラ」は、最近ユネスコ世界遺産に登録され注目を集めていますが、まだ外国人観光客は比較的少ない穴場スポットです。「サッシ」と呼ばれる洞窟住居群は紀元前から人が住み続けてきた歴史的な居住区で、まるで絵本の中の世界のような景観です。2019年に「ヨーロッパ文化首都」に選ばれたこともあり、芸術や文化のイベントも増えています。この地域の伝統料理には「クラスタータ」というパイや「ストラスキナーテ」という手打ちパスタなどがあります。マテーラはその独特の景観から映画のロケ地としても使われ、メル・ギブソン監督の「パッション」やジェームズ・ボンド映画「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」の撮影地としても知られています。
―イタリア人に人気のレストランは?外国人があまり行かないところだと?
「トラットリア」は地元のイタリア人に最も愛されている食事処です。これは家族経営の小さなレストランで、華やかな内装や高級な雰囲気はないものの、本格的な家庭料理を手頃な価格で楽しめる場所です。多くの場合、毎日変わる「メニュー・デル・ジョルノ」(本日のメニュー)があり、地元の季節の食材を使った料理が提供されます。大きな観光地から少し離れた住宅街にあることが多く、外国人観光客はあまり訪れません。特に昼時になると地元の労働者や家族連れで賑わい、活気ある雰囲気の中で食事ができます。メニューは地方色が強く、例えばローマの「トラットリア・ダ・ジジ」では「カチョ・エ・ペペ」(チーズと黒コショウのパスタ)が、フィレンツェの「トラットリア・マリオ」では「ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ」(フィレンツェ風Tボーンステーキ)が名物です。
「エノテカ」はワインバーと食事処を兼ねた場所で、イタリア人に人気の夜の社交場です。様々な地方の上質なワインと、それに合う軽い食事やおつまみを提供します。観光客向けのレストランよりもカジュアルな雰囲気で、地元の人々が仕事帰りに一杯飲みながら友人と歓談する場所として利用されています。特に最近は「アペリティーボ」の文化と結びつき、夕方から夜にかけて賑わいます。エノテカでは単にワインを飲むだけでなく、様々な地方の特産品を味わうことができ、例えば「タリアータ」(薄切りの牛肉ステーキ)や「ブルスケッタ」(トースト)、地元のチーズやサラミの盛り合わせなどが人気です。多くのエノテカでは、ワインの知識が豊富なスタッフがいて、料理に合うワインを提案してくれるのも魅力です。
「アグリツーリズモ」は農家が経営する宿泊施設兼レストランで、地産地消を体験できる場所です。自家製の野菜、果物、オリーブオイル、ワインなどを使った料理を提供し、本当の意味での「キロメートルゼロ」(地元産)の食事が楽しめます。郊外や田舎にあるため観光客は少なく、地元のイタリア人が週末に家族で訪れる場所です。多くの場合、建物は古い農家や邸宅を改装したもので、素朴でありながら居心地の良い空間になっています。料理は「クチーナ・ポーヴェラ」(素朴な田舎料理)が中心で、例えばウンブリアのアグリツーリズモでは「ストロッツァプレーティ」(手打ちパスタ)や「ポルケッタ」(豚の丸焼き)、シチリアでは「カポナータ」(茄子の煮込み)や「スパゲッティ・アッラ・ノルマ」(茄子とリコッタチーズのパスタ)など、その地域ならではの料理が味わえます。
「メルカート・コペルト」(屋内市場)の中にある食堂も、地元の人々に人気の食事スポットです。例えばフィレンツェの「メルカート・チェントラーレ」やローマの「メルカート・テスタッチョ」などの市場内には、新鮮な食材を使った料理を提供する小さな店が並んでいます。朝早くから夕方まで営業していることが多く、市場で働く人や近隣のオフィスワーカーが利用しています。観光客も訪れることはありますが、主に地元の人々の日常的な食事の場になっています。こうした市場内の食堂では、例えば「パニーノ・コン・ラ・ポルケッタ」(豚の丸焼きサンドイッチ)や「トリッパ・アッラ・フィオレンティーナ」(フィレンツェ風ハチノス煮込み)など、地元の伝統的なストリートフードが楽しめます。
「オステリア」も地元のイタリア人に人気のレストランタイプです。もともとは旅人に食事と宿を提供する場所でしたが、現在では家庭的な料理とカジュアルな雰囲気を楽しめるレストランとなっています。トラットリアよりもさらにシンプルで価格も手頃なことが多く、定番料理と地元のワインを楽しむのが一般的です。特に学生や若者に人気があり、賑やかで活気のある雰囲気が特徴です。メニューは限られていることが多く、その日に用意されたものから選ぶスタイルです。例えばボローニャの「オステリア・デル・オルサ」では「タリアテッレ・アル・ラグー」(ボロネーゼソースのパスタ)が、ローマの「オステリア・ダ・フォルトゥナータ」では「カチョ・エ・ペペ」などが人気です。
まとめ
イタリアの文化を知ることで、「生活を楽しむ」という哲学に触れることができます。食事を大切にし、家族や友人との時間を重視し、美しいものを愛でる感性は、現代の忙しい生活の中でも大切にしたい価値観です。
特に印象的なのは、「効率」や「便利さ」よりも「質」と「喜び」を優先する姿勢です。マルカートで新鮮な食材を選ぶ時間、家族と過ごす長い食事の時間、パッセジャータで友人と交流する時間…これらは決して「無駄な時間」ではなく、生活を豊かにする大切な要素と考えられています。
また、地域ごとに異なる文化や伝統、料理を大切にする多様性も学ぶべき点です。グローバル化が進む現代において、地域のアイデンティティを保持しながらも開かれた姿勢を持つイタリアの文化は、私たちにバランスの取れた生き方を示してくれているのかもしれません。
イタリアへの留学や旅行の際には、有名な観光地だけでなく、地元の人々が集まる市場やトラットリア、小さな村のお祭りなどにも足を運んでみてください。そこで出会う人々との交流や、地元の食べ物、何気ない日常の風景の中に、イタリア文化の真髄が隠れているかもしれません。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。