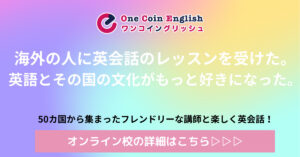【日本在住インドネシア人に聞いた!】知っておきたいインドネシアの文化 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

インドネシアってどんな国? 日本からのイメージ
インドネシアは東南アジアの島国で、17,000以上の島々からなる世界最大の群島国家です。人口は約2億7000万人で、300以上の民族グループと700以上の言語があります。多様性に富んだ国であり、「多様性の中の統一」をモットーにしています。
日本人からは「バリ島のリゾート」「おいしいナシゴレン」「親切で笑顔の素敵な人々」などのイメージが強いようですが、実はもっと奥深く多様な文化や生活があります。今回は日本で暮らすインドネシア人の方に、母国の文化について語っていただきました。
インドネシアで暮らす/インドネシアに行くメリットについて
インドネシアを訪れる、あるいは暮らすメリットは大きく分けて3つあります。まず、文化的な多様性を体験できること。次に、温かい人間関係や地域コミュニティの絆を感じられること。そして、美しい自然や世界遺産、多彩な食文化を楽しめることです。
また、近年は経済成長も著しく、ビジネスチャンスを求めて訪れる人も増えています。インドネシアの魅力についてさらに詳しく聞いていきましょう。
① 知っておきたいインドネシアの文化(歴史)
――インドネシアの歴史で日本人があまり知らないけど重要なことってある?
実はインドネシアには数世紀にわたる王国の歴史があるんだ。スリウィジャヤ王国やマジャパヒト王国は、東南アジア地域で大きな影響力を持ってたんだよ。特にマジャパヒト王国は14世紀に今のインドネシア全域とマレーシア、シンガポールの一部まで支配していた大帝国だったんだ。
もう一つ意外と知られてないのは、オランダによる植民地時代が約350年も続いたこと。これはアジアで最も長い植民地時代の一つなんだ。だから今でも法律や行政システムにオランダの影響がたくさん残ってるよ。
――インドネシアの独立について教えて!
独立は1945年8月17日に宣言されたんだけど、それから1949年まで独立戦争が続いたんだ。この独立宣言の日は今でも国の最も重要な祝日になってるよ。
面白いのは、日本の降伏後の混乱期を利用して、スカルノとハッタという二人の独立運動家が独立宣言を出したこと。実は彼らは最初、日本の占領時代に協力していたこともあって、その経験を独立のために利用したんだよ。この歴史は複雑だから、インドネシア人も色々な見方をしてるんだ。
② 知っておきたいインドネシアの文化(コミュニケーション)
――インドネシア人のコミュニケーションスタイルの特徴ってどんなの?
インドネシア人は直接的な対立を避ける傾向があるよ。「ノー」とはっきり言うより、「インシャーアッラー」(神のご意志があれば)とか「後で考えます」みたいに柔らかく断ることが多いんだ。これは相手の気持ちを大切にする「ムルー」(面子)の文化から来てるんだよ。
あと、初対面では必ず「どこから来たの?」「結婚してる?」「子どもは?」って聞くんだけど、これは日本だと個人的すぎる質問かもしれないね。でも、インドネシアでは相手に興味を持ってるっていう証拠なんだ。悪気はないから、気にしないでね。
――インドネシア語にしかない面白い表現はある?
「ジャム・カレット」っていう言葉があるんだけど、直訳すると「ゴムの時間」っていう意味なんだ。約束の時間が伸び縮みするってことで、時間にルーズなことを表す表現なんだよ。「7時に会おう」って言われても、実際は7時半か8時になることも珍しくないんだ。
それから「サバル」っていう言葉も大事。これは「忍耐」とか「我慢」って意味だけど、インドネシア人の生活哲学を表す重要な概念なんだ。何か困難があっても「サバル」と言って、穏やかに受け入れる姿勢を大切にしてるよ。
③ 知っておきたいインドネシアの文化(プレゼント)
――インドネシアでプレゼントを渡すときのマナーってどんなの?
プレゼントは必ず両手で渡すのがマナーだよ。片手だけ、特に左手だけで渡すのは失礼になるんだ。左手は不浄な手とされてるからね。
あと、プレゼントをもらったらその場ですぐに開けないことが多いかな。後で一人のときに開けるんだ。これはプレゼントの内容に関わらず喜びを表現するためで、もし期待と違っても失礼にならないようにっていう配慮なんだよ。
――どんなプレゼントが喜ばれる?逆にNGなものは?
食べ物のプレゼントはいつでも喜ばれるよ!特に日本のお菓子とか地方の特産品は人気があるんだ。あとは実用的なものも喜ばれるかな。
NGなプレゼントは、まずナイフなどの鋭利なもの。これは「関係を切る」という意味に取られることがあるんだ。あとイスラム教徒が多いから、お酒や豚肉製品(ゼラチンを含む食品なども)は避けた方がいいね。あと、緑色の帽子も避けた方がいいよ。これは不貞を意味するから、特に男性には絶対NGなんだ。
――お土産の文化について教えて!
インドネシアでは「オレオレ」っていうお土産の文化がすごく重要なんだ。旅行に行ったら、家族、友達、同僚、ご近所さんまで、みんなにお土産を買ってくるのが当たり前なんだよ。
面白いのは、お土産をもらった人は空の箱や袋を返すことが多いこと。これは「ありがとう、おいしくいただきました」っていう意味と、次にその人が何か買うときに使えるようにっていう実用的な意味もあるんだ。
④ 知っておきたいインドネシアの文化(食文化)
――インドネシアの食事のマナーで特徴的なことは?
右手で食べるっていうのが基本的なマナーだね。特に手で食べる料理のときは絶対に右手を使うんだ。左手は不浄とされてるからね。
あと、食事の前に「シラーカン・マカン」(どうぞ食べてください)と言われたら、すぐに食べ始めるのがマナー。「いただきます」みたいに言ってから食べ始める習慣はないんだ。でも最近は「ビスミッラー」(神の名において)と言ってから食べるイスラム教徒も多いね。
――インドネシア料理で絶対に試すべきものってどれ?
定番のナシゴレンやミーゴレン以外だと、ブブル・アヤム(鶏肉入りおかゆ)を朝食に食べるのはどう?日本のおかゆより具だくさんで、スパイシーなんだ。
それから各地方の名物料理も試してみて欲しいな。例えばパダン料理のランダン(スパイシーな牛肉の煮込み)や、マナド料理のティヌットワン(極辛スープ)、ジョグジャカルタのグドゥグ(ジャックフルーツのカレー)なんかはそれぞれ全然違う味わいだよ。
――インドネシア料理の秘密のスパイスは?
サンバル!これはチリソースの一種なんだけど、家庭や地域によって配合が全然違うんだ。基本はトウガラシ、トマト、玉ねぎ、にんにくだけど、ここにカンダイ(ガランガル)、クンチット(ウコン)、アサムジャワ(タマリンド)など、いろんなスパイスを加えるんだよ。
あとはテラシっていう発酵エビのペーストも独特な風味を出すのに欠かせないよ。最初は香りが強くて驚くかもしれないけど、これがインドネシア料理の奥深い味の秘密なんだ。
⑤ 知っておきたいインドネシアの文化(その他)
――インドネシアの伝統衣装について教えて!
バティックは有名だけど、実はインドネシアの各地域にそれぞれ独自の伝統衣装があるんだよ。例えばジャワのケバヤ(刺繍入りのブラウス)とバティックの巻きスカート、スマトラのソンケット(金糸で織られた布)、バリのウドゥン(頭に巻く布)など、色も柄も全然違うんだ。
興味深いのは、これらの衣装には意味があって、例えばバティックの柄は着る人の社会的地位を示したり、特別な儀式用だったりするんだよ。今でも結婚式などの特別な機会には、みんな伝統衣装を着るね。
――インドネシアの若者文化は今どんな感じ?
インドネシアの若者はSNSにすごくはまってるよ!インスタグラムやTikTokの利用率は世界でもトップクラスなんだ。「インフルエンサー」になるのが夢の若者も多いね。
あと、カフェ文化も盛んで、おしゃれなカフェで写真を撮って投稿するのが定番になってるよ。インドネシア風ミルクティー「エス・テー・スス」や、コーヒーの一種「コピ・スス」を飲みながら何時間も友達とおしゃべりするのが一般的かな。
K-POPも大人気で、韓国のアイドルグループのファンクラブに入ってる若者も多いんだよ。
――インドネシアで人気のSNSハッシュタグやミームはある?
「#OOTD」(Outfit Of The Day)はインドネシアでもめちゃくちゃ人気!若者たちは自分のファッションを投稿するのが大好きなんだ。
あとはインドネシア独自のものだと「#GakBersubsidi」(補助金なし)というハッシュタグがあって、高級品や贅沢な体験をシェアするときに使われるよ。自分で働いて稼いだお金で買ったことを誇りに思うっていう意味があるんだ。
ミームでは「サラ・ジュンパ・サラ・チンタ」(出会えば恋に落ちる)が流行ってて、思いがけない場所で素敵な人や物に出会うシチュエーションを表すよ。インドネシア人はロマンチックな話が大好きなんだ。
まとめ
インドネシアは多様な文化や伝統、温かい人間関係を大切にする魅力的な国です。コミュニケーションでは相手を尊重する姿勢が重視され、食文化では地域ごとの多彩な味わいが楽しめます。
伝統と現代が融合するインドネシアでは、バティックのような伝統工芸から最新のSNSトレンドまで、様々な文化的体験ができるでしょう。インドネシアを訪れる際は、ぜひ現地の人々と交流しながら、この国の豊かな多様性を感じてみてください。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。