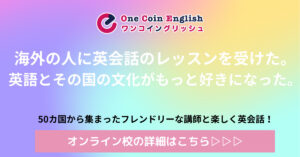【インドの文化を学ぶ!】インドの食文化の日本との違い5選 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

インドってどんな国? 日本からのイメージ
インドは南アジアに位置する人口約14億人の大国で、29の州と7つの連邦直轄地から成り立っています。多様な言語、宗教、文化が共存し、公用語はヒンディー語と英語ですが、22の言語が憲法で認められています。
日本人からは「カレーの国」「ヨガの発祥地」「IT大国」「カースト制度」などのイメージが強いようですが、実際のインドはそのイメージをはるかに超える複雑で多彩な文化を持つ国です。特に食文化においては、地域ごとに全く異なる料理や食習慣があり、まさに「多様性の国」と言えるでしょう。
インドで暮らす/インドに行くメリットについて
インドを訪れる、あるいは暮らす最大のメリットは、豊かな食文化を体験できることです。北インドのクリーミーな料理、南インドの辛くてスパイシーな料理、東インドの魚料理、西インドの甘い料理など、地域によって味わいが全く異なります。
また、日本では体験できない多様なスパイス使いや調理法、食事マナーなど、食を通じて異文化理解を深められるのも大きな魅力です。さらに、都市部では世界各国の料理も楽しめる一方で、地方では昔ながらの伝統料理が今も受け継がれているという、古きと新しきが共存する食文化も体験できます。
① インドの食文化の日本との違い(食事)
――インドと日本の食事で一番違うと感じることってなに?
まず手で食べる文化が大きな違いだね。特に南インドでは今でも右手の指を使って食べるのが一般的なんだ。日本では箸を使うけど、インドでは手で食べることで食べ物の温度や食感を直接感じることが大切にされてるよ。初めは抵抗あるかもしれないけど、実際にやってみると面白い体験になると思うよ。
それからスパイスの使い方も全然違うね。日本料理は素材の味を活かすのが特徴だけど、インド料理はスパイスの組み合わせで複雑な味わいを作るんだ。例えばマサラダバと呼ばれるスパイスボックスには、ターメリック、クミン、コリアンダー、ガラムマサラなど7〜8種類のスパイスが入っていて、料理ごとに違う組み合わせで使うんだよ。
――インドの一般的な食事ってどんな感じ?日本と違う?
インドでは「ターリー」というスタイルの食事が一般的で、これは日本の定食に似てるけど、全部が一度に出されるところが違うかな。大きな皿や葉っぱの上に、主食のご飯やロティ(平たいパン)を中心に、何種類ものカレーやおかず、ヨーグルト、漬物などを一緒に出すんだ。
面白いのは、インドでは日本みたいに「朝食」「昼食」「夕食」で全然違うものを食べる習慣があまりないこと。朝からガッツリとスパイシーな料理を食べることも多いし、基本的に一日を通して似たような種類の料理を食べるんだよ。日本みたいに「朝はおかゆや納豆」みたいな区別はあまりないんだ。
――インドの食べ方やマナーで日本人が知っておくべきことってある?
まず右手で食べるのが基本。左手は不浄とされてるから、食事に関することは全部右手でするのがマナーなんだ。もしスプーンを使うなら、それも右手で持つようにしてね。
それから食事の前に手を洗うのはマスト!レストランでもテーブルの近くに手洗い場があることが多いし、ない場合は「フィンガーボウル」という小さな水の入った器が用意されることもあるよ。
あと、シェアする文化も強いね。大皿から取り分けて食べるのが一般的で、特に家庭での食事ではみんなで同じ料理を囲むことが多いんだ。ただし、誰かの皿から直接食べ物を取ったり、すでに口をつけた食器で取り分けたりするのはNGだよ。
② インドの食文化の日本との違い(会話)
――インドでは食事中にどんな会話をするの?日本と違うことある?
日本では「食事中のおしゃべりは控えめに」って教わることもあるけど、インドは全然逆!食事中は会話が盛り上がるのが普通で、家族の近況や社会の出来事、映画の話など、いろんな話題で盛り上がるんだ。
面白いのは、インドでは食事中に次の料理の話をすることが多いこと。「このカレーおいしいね、でも明日はもっとスパイシーなのを作ろうか」みたいな感じで、今食べてる最中に次の食事の計画を立てたりするんだよ。食べることへの情熱が強いからかな。
――食事のときのあいさつは日本と違う?
日本では「いただきます」「ごちそうさま」って言うけど、インドにはそういう決まった挨拶はないんだ。でも宗教によって違いがあって、イスラム教徒は「ビスミッラー」(神の名において)と言ってから食べ始めることが多いし、ヒンドゥー教徒は最初の一口を神様に捧げる意味で少し待つこともあるよ。
日本と違うのは「おいしい」の表現方法かな。インドでは「ワー、バフット・アッチャー!」(とても良い!)って大げさに言ったり、「マザー・ダール」(おいしい!)って何度も繰り返したりするのが普通なんだ。日本人は控えめに「おいしい」って言うことが多いけど、インドではもっと感情を表に出す方が喜ばれるよ。
――レストランでの注文の仕方や会計の方法で日本と違うところは?
インドのレストランでは、注文するときにウェイターを呼ぶのに遠慮する必要はないよ。「ボーイ!」とか「ウェイター!」って大きな声で呼んでも全然問題ないんだ。これが日本だと失礼になるけどね。
会計方法も面白くて、特に友達同士だと誰か一人が全額払って、「次は君が払ってね」みたいな感じにすることが多いんだ。日本みたいに細かく割り勘にすることはあまりなくて、長い目で見て平等になればOKっていう考え方なんだよ。
もう一つ注意したいのは、インドの多くの高級レストランでは「サービス料」が自動的に加算されることが多いってこと。だからチップを別に払う必要はないんだけど、特別良いサービスだったら少し多めに払うのは歓迎されるよ。
③ インドの食文化の日本との違い(記念日/祝日)
――インドの祝日や記念日の食事は特別なものがあるの?
ディワリ(光の祭り)はインドの大きなお祭りで、この時には特別なスイーツをたくさん作るんだ。「ラドゥー」(ひよこ豆の粉で作った丸いお菓子)や「バルフィ」(練乳から作ったスイーツ)、「ジャレビ」(シロップに浸した渦巻き状の揚げ菓子)なんかが定番だよ。日本のお正月におせち料理を食べるのに少し似てるかな。
ホーリー(色の祭り)の時には「グジヤ」っていう甘い詰め物入りの半月型のお菓子や、「タンダイ」っていうナッツとスパイスで風味付けした特別なミルクドリンクを飲むんだ。これはホーリーの熱気を冷ますためと言われてるよ。
結婚式では「ビリヤニ」(スパイスで炊き込んだご飯と肉料理)が必ず出されるし、出産祝いでは「パンジリ」という栄養価の高い甘いお菓子を作るんだよ。
――日本のお節句みたいな、季節の行事食はあるの?
マカル・サンクランティという収穫祭があって、1月14日頃に行われるんだけど、この時には「ティル・ラドゥー」(ゴマのお菓子)や「ラワン・ラドゥー」(ひよこ豆と砂糖で作ったお菓子)を食べるよ。冬に体を温めるためにゴマやナッツをたくさん使うんだ。
雨季の始まりを祝うテイージ祭では、女性が一日断食した後に「ゲワル」という特別なデザートを食べるんだよ。これは蜂の巣のような見た目をしていて、とても甘くてジューシーなんだ。
面白いのは、インドでは地域によって祝日に食べるものが全然違うこと。例えば南インドのポンガルでは「ポンガル・ライス」(甘いミルクご飯)を食べるし、ベンガルのドゥルガ・プジャでは「パヤシュ」(ライスプディング)を食べるんだ。インドの多様性がここにも表れてるね。
――インドのウェディングフードって日本の結婚式と違う?
インドの結婚式の料理は本当に豪華で、少なくとも20種類以上の料理が出ることも珍しくないんだよ。「パンチョバン・ダール」(5種類の豆のカレー)、「パニール・バター・マサラ」(チーズのトマトクリームカレー)、「ナーン」(窯で焼いたパン)、「ビリヤニ」(スパイス炊き込みご飯)などなど…。日本のコース料理とは違って、全部が一度に並べられることが多いんだ。
特徴的なのは甘いものと辛いものを交互に食べる文化があることかな。例えば「グラブ・ジャムン」(ミルクの揚げ菓子をシロップに浸したもの)を食べた後に辛いカレーを食べるみたいな。日本だと甘いものはデザートとして最後に食べることが多いけど、インドでは食事の途中でも甘いものを食べるんだよ。
それから結婚式では「パーン」というビンロウの葉っぱに様々なスパイスやナッツを包んだ口直しも出されるよ。これは食後に食べて口の中をリフレッシュするためのもので、日本のガムに似た役割かな。
④ インドの食文化の日本との違い(おふくろの味)
――インドのお袋の味って日本と比べてどう違うの?
インドの「お袋の味」は地域によって全然違うんだよ。北インドなら「ダール」(豆のカレー)と「ロティ」(平たいパン)の組み合わせが定番で、南インドだと「サンバル」(豆と野菜のスープ)と「イドリ」(蒸した米と豆のケーキ)や「ドーサ」(米と豆の薄焼きクレープ)が家庭料理の基本だね。
でも面白いのは、インドでも日本と同じように「うちのお母さんの料理が一番」って思うところ。特に「ダール」は家庭ごとに味が全然違って、「ママのダールが恋しい」っていうのはインド人留学生あるあるなんだよ。
日本のお袋の味と違うのは、インドの場合はスパイスの組み合わせが複雑なこと。ママから教わったスパイスの配合やタイミングが家庭ごとの味の決め手になるんだ。だから同じカレーでも家庭によって全然違う味になるよ。
――インドの家庭料理ではどんな調理器具を使うの?日本と違うものってある?
まず「タワ」という平たい鉄板があって、これでロティやパラタを焼くんだ。日本のフライパンより厚くて重いものだよ。あとは「カダイ」という中華鍋みたいな形の深い鍋や、「プレッシャークッカー」(圧力鍋)も欠かせないアイテム。インドでは豆や肉を柔らかく煮込むのに圧力鍋が大活躍なんだよ。
「シルバタ」という石の臼と杵もよく使われるよ。これでスパイスを挽いたり、チャツネを作ったりするんだ。最近は電動ミキサーも普及してきてるけど、年配の人は「シルバタで作った方が風味が良い」って言うことが多いね。
あと面白いのは「イドリ・スタンド」と呼ばれる蒸し器。これはイドリを作るための専用器具で、日本の蒸し器とは全然違う形をしてるんだ。小さな丸いくぼみがいくつもある金属製の容器で、そこに生地を入れて蒸すんだよ。
――インドの家庭ではどうやってレシピを受け継いでるの?
インドでは料理のレシピはほとんど口伝えで、母から娘へと受け継がれていくんだ。面白いのは具体的な分量を言わないこと。「少しのターメリック」「一つかみのコリアンダーパウダー」みたいにあいまいな表現で教えることが多くて、実際の量は見て覚えるんだよ。
特に伝統的な家庭では、結婚前に花嫁が義母から料理を教わる期間があることも。これは新しい家庭に入ったときに夫や義父が慣れ親しんだ味を作れるようにするためなんだ。日本の「お婿さんの好物を覚える」みたいなことに近いかも。
最近はYouTubeやクックパッドみたいなサイトも人気で、若い世代はそういうところから料理を学ぶことも増えてきたよ。でも「ママの味」は特別で、どんなレシピサイトよりも価値があるって思われてるんだ。
⑤ インドの食文化の日本との違い(その他)
――インドの屋台文化について教えて!日本の屋台と違う?
インドの屋台文化はすごく豊かで、「チャート」と総称される軽食の種類が豊富なんだ。「パニプリ」(中が空洞の揚げパンにスパイシーな水を入れて一口で食べるもの)や「パヴ・バージ」(野菜のカレーとパン)、「ヴァダ・パヴ」(ポテトコロッケのサンドイッチ)なんかが人気だよ。
日本の屋台と違うのは、インドの屋台は朝から深夜まで営業していることが多いってこと。朝食、おやつ、夕食、夜食と、一日中いつでも屋台フードを楽しむことができるんだ。あと、屋台ごとに専門の料理があって、「あのお店のパニプリが一番」みたいな地元の人のお気に入りがあるのも特徴だね。
衛生面は正直言って日本より気を使わない部分もあるけど、地元の人が多く集まる屋台は味が良くて安全なことが多いよ。観光客向けじゃなくて地元の人で賑わってる屋台を選ぶのがコツだね。
――インドのお茶文化について教えて!日本と違うところは?
インドの「チャイ」(ミルクティー)文化は生活に深く根付いてて、一日に何度もチャイを飲むのが普通なんだ。日本のお茶は基本的に水だけで淹れるけど、インドのチャイはミルク、砂糖、カルダモン、シナモン、ジンジャーなどのスパイスを入れて煮出すから、味も香りも全然違うよ。
「チャイワラ」と呼ばれるチャイ専門の屋台が街角にたくさんあって、小さな土の器(クラド)でチャイを提供してくれるんだ。この器は使い捨てで、飲み終わったら地面に投げて割るっていう環境に優しい方法なんだよ。最近はガラスやプラスチックのカップも増えてきたけどね。
あと面白いのは「チャイ・タイム」という習慣。午後3時〜4時頃になると仕事を中断してチャイを飲む時間があって、これは社交の場としても重要なんだ。日本の「お茶の時間」に似てるかもしれないけど、もっと日常的でカジュアルな感じだよ。
――インドのベジタリアン文化って日本と違う?
インドのベジタリアン文化は宗教的な背景が強くて、特にヒンドゥー教やジャイナ教の「アヒムサー」(非暴力)の教えから来ているんだ。日本では健康や環境のために選ぶ人が多いベジタリアンだけど、インドでは宗教的、文化的な理由が大きいね。
面白いのは、インドのベジタリアンは卵も食べない人が多いってこと。「純ベジ」と呼ばれる人たちは、卵、肉、魚を一切食べないんだよ。レストランでも「ピュア・ベジ」(緑のマーク)と「ノン・ベジ」(赤のマーク)がはっきり分けられてて、メニューにもマークがついてるから、ベジタリアンでも安心して食事ができるんだ。
あと、日本ではベジタリアン向けのレストランが限られてるけど、インドではどこのレストランでもベジタリアンメニューが充実してるよ。だからベジタリアンでも食事に困ることはほとんどないんだ。これはインドを訪れる日本のベジタリアンにとって大きなメリットだと思うよ。
まとめ
インドの食文化は、日本とは大きく異なる点が多くあります。手で食べる習慣、スパイスを使った複雑な調理法、食事を囲んでの活発な会話、そして地域ごとに異なる多様な味わいが特徴的です。
日本の繊細で素材を活かした料理文化とは対照的に、インドでは香辛料の複雑な組み合わせと大胆な味付けが魅力となっています。また、食事を通じたコミュニケーションや家族の絆を重視する文化は、食が単なる栄養摂取以上の意味を持つことを教えてくれます。
インドを訪れる際は、ぜひ勇気を出して地元の食文化に飛び込んでみてください。最初は戸惑うかもしれませんが、その豊かな味わいと食文化に触れることで、きっと新しい発見や感動があるでしょう。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。