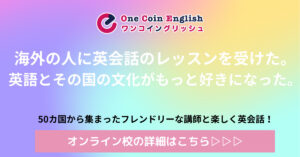【エジプトの文化を学ぶ!】エジプトの食文化の日本との違い5選 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~

エジプトってどんな国? 日本からのイメージ
多くの日本人にとって、エジプトといえば「ピラミッド」「スフィンクス」「ツタンカーメン」「ナイル川」といった古代文明のイメージが強いのではないでしょうか。5000年以上の歴史を持つ古代エジプト文明は、世界史の授業や歴史ドキュメンタリーでおなじみです。
しかし、現代のエジプトは古代遺跡だけの国ではありません。約1億人の人口を擁するアラブ世界最大の国であり、中東・北アフリカ地域における文化・政治の中心地でもあります。首都カイロは「千のミナレット(モスクの塔)の街」とも呼ばれ、イスラム建築の美しさと近代的な都市機能が共存する活気あふれる大都市です。
エジプトはアフリカ大陸の北東部に位置し、ナイル川が南北に流れています。古くから「エジプトはナイルの賜物」と言われるように、ナイル川流域の肥沃な土地が農業と食文化の発展を支えてきました。砂漠気候が広がる中で、ナイル川の恵みを最大限に活用した独自の食文化が形成されてきたのです。
現代エジプトはイスラム教を主要宗教とするアラブの国ですが、コプト・キリスト教などの少数派も共存しています。この宗教的背景は食文化にも大きな影響を与えており、イスラム教の教えに基づく食の禁忌や習慣が日常生活に根付いています。
エジプトで暮らす/エジプトに行くメリットについて
豊かな食文化体験
エジプトに滞在する最大の魅力の一つは、その豊かな食文化を体験できることです。地中海料理とアフリカ・中東料理が融合したエジプト料理は、新鮮な食材と独特のスパイスを使った健康的で美味しい料理が特徴です。特に「コシャリ」「フル・メダメス」といった庶民的な料理から、「ムルーハ」「マハシ」などの伝統料理まで、様々な味わいを楽しむことができます。
新鮮で安価な食材
エジプトでは特に野菜や果物が新鮮で安価です。ナイル川流域で栽培される農産物は豊富で、マンゴー、グアバ、イチジク、ザクロといった果物や、様々な種類の野菜が季節ごとに市場に並びます。日本では高価な果物も、エジプトでは驚くほどリーズナブルに楽しめます。
社交としての食事文化
エジプトでは食事が単なる栄養摂取ではなく、家族や友人との絆を深める重要な社交の場となっています。「一緒に食べる」ことを通じて人間関係が築かれる文化であり、食卓を囲む時間は会話と交流に満ちています。この温かい食事の場に参加することで、現地の人々と親しくなるチャンスも広がります。
多様な料理文化
エジプトはその地理的位置から、地中海、中東、アフリカなど様々な食文化の影響を受けています。そのため、一つの国にいながら多様な料理を楽しむことができます。また、近年は国際的な料理も広がっており、イタリアン、レバニーズ、トルコ料理なども容易に見つけることができます。
カフェ文化の楽しみ
エジプトでは「アフワ(カフェ)」文化が根付いており、特に紅茶「シャーイ」を楽しむ習慣があります。地元のカフェで甘いエジプト紅茶を飲みながら、ゆったりと時間を過ごすのはエジプト生活の醍醐味の一つです。
① エジプトの食文化の日本との違い(食事)
エジプトと日本の食事スタイルには、いくつかの興味深い違いがあります。
食事の基本構成と提供方法
日本の食事は「一汁三菜」を基本とし、個人ごとに器が用意され、各自が自分の前に置かれた料理を食べるスタイルが一般的です。一方、エジプトでは大皿に盛られた料理を、みんなで分け合って食べる「共有型」の食事スタイルが主流です。特に家庭や友人との食事では、テーブルの中央に様々な料理が並び、それぞれがパンを使って取り分けます。
また、日本では主食(ご飯)と副菜の区別が明確ですが、エジプトではそのような区別が曖昧で、全ての料理が同等に扱われることが多いです。特に「アイシュ・バラディ」と呼ばれる平たいパンは食事に欠かせない存在で、料理をすくったり包んだりするための「道具」として機能します。
味付けと調味料
日本料理が「引き算の美学」とも言われるように素材の味を活かした繊細な味付けを好むのに対し、エジプト料理はスパイスやハーブを積極的に使った「足し算の料理」が特徴です。クミン、コリアンダー、シナモン、ニンニク、タマネギなどが基本的な調味料となり、これらが料理に深い風味を与えています。
また、日本では醤油、味噌、だしが基本調味料ですが、エジプトでは「タヒナ」(ゴマペースト)、「ドゥッカ」(ナッツとスパイスのミックス)、レモン汁などが多用されます。これらの調味料の違いが、料理の味わいに大きな差を生み出しています。
食事の時間帯とリズム
日本では朝食・昼食・夕食がほぼ同じようなスタイルで、時間も比較的規則的です。一方エジプトでは、朝食「フトゥール」は軽めで、昼食「ガダー」が一日の中で最も重要かつ豪華な食事とされることが多いです。昼食後には短い昼寝「アイルーラ」を取る習慣もあります。夕食「アシャー」は日本より遅く、20時から22時頃に取ることが一般的です。
また、イスラム教徒が多いエジプトでは、ラマダン(断食月)の期間中は日の出から日没まで断食し、日没後に「イフタール」と呼ばれる食事を家族や友人と共にします。この一ヶ月間は、通常の食事リズムが大きく変わる特別な期間となります。
食材と主要な栄養源
日本では魚介類や大豆製品が重要なタンパク源ですが、エジプトでは豆類(特にそら豆)と肉類(鶏肉、牛肉、羊肉)がタンパク源の中心です。「フル・メダメス」に代表されるそら豆料理は、古代エジプト時代から続く伝統的な栄養源として重要な位置を占めています。
また、日本では米が主食ですが、エジプトではパンが最も重要な炭水化物源です。エジプトのパンである「アイシュ・バラディ」は日本のご飯のように、全ての食事に欠かせない存在です。
② エジプトの食文化の日本との違い(会話)
食事の場での会話について、エジプトと日本には顕著な違いがあります。
食事中の会話量と内容
日本では「食事中はあまりおしゃべりしない」「口に食べ物を入れているときは話さない」という文化がありますが、エジプトでは食事の時間は社交の重要な機会とみなされており、活発な会話が交わされます。特に家族の食事は、一日の出来事を共有し、意見を交換する大切な場となっています。
エジプトの食卓では、政治、社会問題、家族の事柄など、様々なトピックが議論されます。日本では避けられがちな政治や宗教の話題も、エジプトでは珍しくありません。声が大きくなったり身振り手振りが増えたりしても、それは議論が白熱している証拠であり、決して怒っているわけではないことが多いです。
食事への賛辞と感謝
日本では「いただきます」「ごちそうさま」という挨拶で感謝を表しますが、エジプトでは食事中に頻繁に「アルハムドゥリッラー(Alhamdulillah:神に感謝)」や「ビスミッラー(Bismillah:神の名において)」という言葉を使います。また、料理が美味しいときには「タイエブ・アウィ(Tayyib awi:とても美味しい)」と声に出して称えるのが一般的です。
特に家庭料理に対しては、「テスラム・イーダーキ(Teslam idaki:あなたの手に祝福を)」という表現で料理人(多くの場合は母親や妻)の腕前を褒めます。これは単なる儀礼ではなく、心からの感謝と称賛を表す重要な習慣です。
もてなしと勧め方
エジプト人は「カラム(Karam:寛大さ、もてなし)」を大切にする文化があり、食事の場でもこれが表れます。ホストは常にゲストに対して「イトファッダル(Itfaddal:どうぞ)」と言って料理を勧め、十分に食べるよう気を配ります。日本では「遠慮」が美徳とされることもありますが、エジプトでは遠慮せずに提供されたものを楽しむことがホストへの敬意となります。
また、ホストは自分が一番最後に食べ始めることも多く、ゲストが十分に満足するまで自分の食事は二の次にするという習慣があります。これは「もてなし」を最優先する文化の表れです。
カフェでの社交会話
エジプトでは「アフワ(カフェ)」が重要な社交の場となっており、友人と数時間にわたって紅茶を飲みながら会話を楽しみます。特に男性は「トーキー(Tawla:バックギャモンに似たボードゲーム)」や「ドミノ」をしながら談笑し、女性は友人宅やモダンなカフェで集まることが多いです。
日本のカフェが比較的静かで個人的な空間となることが多いのに対し、エジプトのカフェは賑やかで活気に満ちた社交の場となっています。また、カフェでの会話は食事の場同様、政治や時事問題など幅広いトピックに及びます。
③ エジプトの食文化の日本との違い(記念日/祝日)
エジプトと日本では、祝日や記念日に食べる料理にも興味深い違いがあります。
宗教的祝日と食
エジプトでは、イスラム教の主要な祝日に特別な料理が用意されます。特に重要なのは「イード・アル=フィトル」(ラマダン明けの祭り)と「イード・アル=アドハー」(犠牲祭)です。
ラマダン月中は日没後の「イフタール」の食事が特別なものとなり、伝統的にはデーツ(なつめやし)で断食を解き、その後スープや様々な前菜、メインディッシュと続きます。特に「カタイエフ」というパンケーキにナッツとシロップを入れたデザートや、「クナーファ」というチーズの甘い焼き菓子が人気です。
一方、日本の正月におせち料理を食べる習慣や、ひな祭りにちらし寿司を食べる文化のように、一つ一つの料理に縁起の良い意味が込められるという考え方はエジプトではあまり見られません。むしろ「特別な日だからこそ豪華な料理を」という考え方が強いです。
季節の行事と食
日本では四季に応じた行事食(春の山菜、夏のそうめん、秋の松茸、冬の鍋など)がはっきりしていますが、エジプトでも季節に応じた食習慣があります。
特に興味深いのは「シャム・エル・ネシーム(Sham El Nessim)」という春分の日の祭りで、これは古代エジプト時代からの伝統が続く季節の祭りです。この日には「フェシーフ(Feseekh)」という塩漬けの魚、「ターメイヤ」(エジプト風ファラフェル)、ゆで卵、ねぎ、レタスなどを食べながら、公園や川辺でピクニックを楽しみます。
また、夏には「ブルム(Balah)」というデーツの新鮮な実や、様々な夏の果物(マンゴー、グアバなど)が食べられ、冬には「モロヘイヤ」というスープ状の煮込み料理や「コサリ」などの温かい料理が増えます。
個人的な記念日と食
誕生日や結婚記念日などの個人的な記念日では、エジプトも日本と同様にケーキを食べる習慣がありますが、その形式には違いがあります。エジプトの誕生日ケーキは西洋的なスタイルで、クリームやフルーツをふんだんに使った豪華なものが好まれます。
また、特別な日には家族や友人と外食することも多く、この場合は「モルーク(Molokheya)」や「ファッターハ(Fattah)」などの伝統的な料理、または国際料理のレストランが選ばれることが多いです。
④ エジプトの食文化の日本との違い(おふくろの味)
「おふくろの味」や家庭料理の概念にも、エジプトと日本では興味深い違いがあります。
家庭料理の位置づけ
日本では「おふくろの味」は母親から受け継いだ伝統的なレシピや、家族の好みに合わせた独自のアレンジが加えられた料理を指すことが多いです。エジプトでも「アクル・ベイティ(Akl beiti:家庭料理)」という概念があり、家庭料理は非常に重要視されています。
しかし、エジプトの家庭料理は地域性よりも宗教や家族の伝統に基づくことが多く、レシピは母から娘へと口頭で伝えられます。また、日本の家庭料理が素材の味を活かした繊細なものが多いのに対し、エジプトの家庭料理はスパイスやハーブを効かせた濃厚な味わいが特徴です。
代表的な家庭料理
日本の家庭料理が味噌汁、煮物、焼き魚などを中心とするのに対し、エジプトの家庭料理は以下のようなものが代表的です:
- モロヘイヤ(Molokhia):緑色の葉野菜を使ったドロドロしたスープ状の料理
- マハシ(Mahshi):野菜に米と挽肉を詰めて煮込んだ料理
- コシャリ(Koshari):マカロニ、レンズ豆、米、揚げタマネギなどを重ねた料理
- ファッターハ(Fattah):パンの上に米と肉を重ね、ニンニクとお酢のソースをかけた料理
これらの料理は各家庭によって調理法や味付けが微妙に異なり、「母の味」として大切にされています。
料理の伝承方法
日本では料理のレシピが書籍やメディアを通じて伝えられることも多いですが、エジプトではより直接的な「見て学ぶ」方式が一般的です。若い女性は母親や祖母の料理を手伝いながら、目分量や触感、味などを体で覚えていきます。
特に「モルーク(Molokheya)」という料理は、葉の刻み方や調理の手順が非常に重要で、これを正確に伝えるには実際に見て学ぶことが必要とされます。
また、エジプトでは「家族の秘伝」として特別なレシピが代々伝えられることもあり、これらは家族のアイデンティティの一部となっています。
食材の扱いと保存食
日本では旬の食材を大切にし、保存食も季節の味を閉じ込めるという考え方がありますが、エジプトでは乾燥した気候を活かした保存食文化が発達しています。
例えば「アイシュ・シャムシ(Aish Shamsi)」という太陽で乾燥させたパンや、「ジャミード(Jameed)」という乾燥ヨーグルト、様々なドライフルーツや乾燥豆類が重要な保存食となっています。これらは必要に応じて水で戻して使われます。
また、日本の漬物文化に似た「トルシ(Torshi)」という野菜の酢漬けも、エジプトの家庭料理に欠かせない存在です。にんじん、きゅうり、唐辛子、カリフラワーなどを酢とスパイスで漬け込んだものが、メインディッシュの付け合わせとして食べられます。
⑤ エジプトの食文化の日本との違い(その他)
上記以外にも、エジプトと日本の食文化にはいくつかの興味深い違いがあります。
飲み物の文化
日本では食事と共にお茶(緑茶)を飲むことが一般的ですが、エジプトでは食事中の飲み物として水が基本です。「シャーイ(紅茶)」は食事の後に飲まれることが多く、砂糖をたっぷり入れた甘い味わいが特徴です。
また、イスラム教の教えでアルコールが禁じられていることもあり、多くのエジプト人はアルコール飲料を飲みません。その代わり、フレッシュジュースの文化が発達しており、季節の果物を使った「アスィール(Asir:ジュース)」が人気です。サトウキビジュース「アサブ(Asab)」やハイビスカスティー「カルカディー(Karkadeh)」などもエジプト独自の飲み物です。
食事のマナーと習慣
日本では「箸」を使う独自の食文化がありますが、エジプトではナイフとフォークを使う西洋式の食事方法と、手で直接食べる伝統的な方法が併存しています。特に家庭やカジュアルな場面では、右手を使って食べるのが一般的です(左手は不浄とされるため)。
また、日本では「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶があり、食事中の音を立てることを避けますが、エジプトではイスラム教の影響から「ビスミッラー(神の名において)」と言って食事を始め、「アルハムドゥリッラー(神に感謝)」と言って終えることが一般的です。食事中の音に関しては比較的寛容で、むしろ食事を楽しんでいる表現として受け止められることもあります。
パンの重要性
日本では「米」が主食ですが、エジプトでは「パン」が最も重要な食べ物です。特に「アイシュ・バラディ」と呼ばれるピタパンのような平たいパンは、食事に欠かせません。エジプト語で「アイシュ」は「パン」と「生命」の両方を意味し、その重要性を表しています。
パンは料理をすくったり、包んだりする道具としても使われ、食事の最後まで大切にされます。パンを粗末に扱ったり、捨てたりすることは避けるべきとされています。
食と宗教の関係
日本では宗教と食の関連は現代では比較的薄れていますが、エジプトではイスラム教の影響で「ハラール(許された)」食品の概念が重要です。豚肉は禁じられており、肉は特定の方法で屠畜されたものを選びます。
また、前述のようにラマダン月の断食は、一年の中で食習慣が最も大きく変わる期間です。この月には日の出から日没まで飲食を断ち、日没後の「イフタール」と夜明け前の「スフール(Suhoor)」の食事が特別な意味を持ちます。
まとめ
エジプトと日本の食文化は、それぞれの歴史、地理、宗教的背景を反映した独自の発展を遂げています。エジプト料理は地中海と中東、アフリカの影響を受けた多彩な味わいがあり、共有と社交を重視する食事スタイルが特徴です。日本料理が個人的で繊細な味わいを大切にするのに対し、エジプト料理はよりボリューム感があり、スパイスを効かせた濃厚な味わいを持ちます。
食事の場での会話においても、エジプトでは活発なコミュニケーションが重視され、料理への賞賛を声に出して表現する文化があります。また、「もてなし」の精神は食を通じて表現され、ゲストに対する心からの歓迎の気持ちが食事の提供に表れます。
祝日や記念日の食事も、それぞれの文化的背景を反映しており、エジプトではイスラム教の祝日や古代からの季節の祭りに特別な料理が用意されます。「おふくろの味」もそれぞれの文化で大切にされていますが、エジプトではより口承による伝承が重視され、家族のアイデンティティの一部として料理のレシピが受け継がれています。
エジプトを訪れる際には、ぜひこうした食文化の違いを意識しながら、現地の人々と食事を共にする機会を作ってみてください。言葉が通じなくても、美味しい料理を一緒に楽しむことで、心の距離はグッと縮まることでしょう。エジプトの陽気で温かい人々との食卓は、きっと忘れられない思い出になるはずです。
ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。