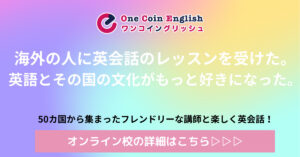【オーストラリアってどんな国?】オーストラリアの食文化の日本との違い5選 ~留学、長期滞在、移住、短期滞在・旅行の参考に~
11か月 ago ONECOSMOPOLITAN編集部
オーストラリアってどんな国? 日本からのイメージ
オーストラリアと聞くと、多くの日本人は広大な自然、カンガルーやコアラなどの特徴的な動物、美しいビーチ、そして陽気でフレンドリーな人々を思い浮かべるのではないでしょうか。また、留学先としても人気が高く、ワーキングホリデーやバックパッカーの行き先としても知られています。 しかし、オーストラリアの食文化については、あまり具体的なイメージを持っていない方も多いかもしれません。「バーベキューが人気」「ステーキやラム肉をよく食べる」「ベジマイトというスプレッドがある」といった断片的な情報は知っていても、オーストラリアの食文化の全体像や日本との違いについては、あまり知られていないことが多いです。 実際、オーストラリアは多文化社会であり、その食文化もイギリスの伝統的な影響をベースとしながら、地中海やアジアなど世界各地からの移民によってもたらされた多様な料理が融合した、独自の発展を遂げています。この記事では、そんなオーストラリアの食文化と日本の食文化の違いについて探っていきましょう。オーストラリアで暮らす/オーストラリアに行くメリットについて
オーストラリアに滞在するメリットは数多くありますが、食に関連したメリットもいくつか挙げられます。まず、多文化社会であるオーストラリアでは、世界各国の料理を本格的に楽しむことができます。特に大都市では、イタリアン、ギリシャ、レバノン、タイ、ベトナム、中国、インド、そして日本料理まで、あらゆる国の料理のレストランがあります。 また、新鮮な食材の質が高いのも魅力です。肉類、特に牛肉やラム肉は世界的にも評価が高く、シーフードも沿岸部では新鮮で美味しいものが手に入ります。またワインも国際的に評価の高い産地があり、リーズナブルな価格で良質なワインを楽しめます。 カフェ文化も発達しており、特にメルボルンは「世界のカフェ文化の中心地」とも称されます。質の高いコーヒーと共に、朝食やブランチを楽しむ文化は、新たな食の体験となるでしょう。 食の安全性という点でも、オーストラリアは厳格な基準を持っており、食品添加物の使用も比較的制限されています。また、ベジタリアンやビーガン、グルテンフリーなどの食事制限に対応したメニューも豊富で、特別な食のニーズがある方にも対応しやすい環境です。 さらに、自然豊かな環境で育った有機食品や、先住民アボリジニの伝統的な食材「ブッシュタッカー」などの独自の食文化に触れる機会もあります。これらの食体験は、日本では得られない貴重なものとなるでしょう。
① オーストラリアの食文化の日本との違い(食事)
オーストラリアと日本の食事スタイルには、いくつかの興味深い違いがあります。まず、食事の時間帯が異なります。オーストラリアでは朝食は7時〜9時頃、昼食は12時〜2時頃、夕食は6時〜8時頃が一般的です。特に夕食の時間が日本より早いのが特徴で、レストランも8時以降は閉店し始めるところが多いです。 食事の構成も大きく異なります。日本では「一汁三菜」のように、主食、汁物、おかずというバランスを重視しますが、オーストラリアでは一皿完結型の料理が多いです。例えば、肉や魚のメインディッシュに、付け合わせの野菜やポテトが添えられるというスタイルが一般的です。 また、食事量の違いも顕著です。オーストラリアの食事は全体的に量が多く、特に肉類の一人前の量は日本の2〜3倍ということも珍しくありません。レストランで出される一人前のステーキが300g以上あることも一般的で、日本人にとっては驚くほどの量かもしれません。 食器や食べ方にも違いがあります。オーストラリアでは、欧米スタイルのナイフとフォークが主流で、箸を使う機会はほとんどありません(アジア料理のレストランを除く)。また、食事中の音の捉え方も異なり、日本では「音を立てずに食べる」ことが礼儀とされますが、オーストラリアではそのような概念はなく、むしろ「美味しい」という感想を声に出して伝えることが好まれます。 飲み物についても違いがあります。日本では食事と一緒にお茶を飲むことが多いですが、オーストラリアでは水、ソフトドリンク、ビール、ワインなどが一般的です。特に食事と一緒にアルコールを楽しむ文化が根付いており、レストランでは食事と一緒にビールやワインを注文するのが普通です。 最後に、外食と家庭での食事のバランスも異なります。オーストラリアでは外食の頻度が日本より高い傾向があり、特に朝食やブランチをカフェで食べる習慣が一般的です。一方、夕食は家族で自宅で食べることも多く、特に週末には家族や友人を招いてのバーベキューが人気です。② オーストラリアの食文化の日本との違い(会話)
オーストラリアと日本では、食事中の会話のスタイルや重要性にも大きな違いがあります。日本では「食事中は静かに」という文化がある一方、オーストラリアでは食事の場はコミュニケーションの重要な機会とされ、活発な会話が交わされます。 まず、テーブルでの会話のトピックに違いがあります。オーストラリアでは、食事中に政治や宗教などの深刻な話題も含め、幅広い話題について議論することが一般的です。一方、日本では食事の場では争いを避け、軽い話題で和やかな雰囲気を保つことが多いでしょう。 また、食事への感想の表現方法も異なります。オーストラリア人は食事に対する感想を直接的に伝えることが多く、「This is delicious!」(これは美味しい!)と声に出して感想を述べたり、逆に期待通りでなければ率直に意見を言うこともあります。日本では控えめな表現が好まれ、特に否定的な感想は遠回しに伝えることが多いでしょう。 食事の際の音の捉え方も異なります。日本では麺類をすすったり、汁物を飲む際に音を立てることが許容される場面もありますが、オーストラリアでは食事中の音は一般的にマナー違反とされます。逆に、日本では食事中に大きな声で話すことはあまり好まれませんが、オーストラリアでは活気ある会話が食事の楽しみの一部となっています。 食事を共にする相手との関係性の表現も違います。日本では目上の人に対して「先にどうぞ」と促したり、お酒を注いだりする「おもてなし」の文化がありますが、オーストラリアではより平等な関係性が重視され、「Help yourself」(自分で取ってください)というスタイルが一般的です。 食事の場でのスマートフォンの使用についても違いがあります。日本では状況によってはスマートフォンを使うことも許容されますが、オーストラリアでは特に家族や友人との食事の場では、スマートフォンを使わないことがマナーとされることが多いです。 最後に、食事の終わり方も異なります。日本では「ごちそうさま」と挨拶をして食事の終了を明示しますが、オーストラリアではそのような明確な区切りはなく、食べ終わったら自然に立ち上がったり、「I’m finished, thanks」(食べ終わりました、ありがとう)と伝えるだけです。
③ オーストラリアの食文化の日本との違い(記念日/祝日)
オーストラリアと日本では、特別な日に食べる料理や食事の習慣にも大きな違いがあります。まず、両国で最も重要な祝日の一つであるクリスマスの食事を比較してみましょう。 オーストラリアのクリスマスは夏の時期(12月)に当たるため、伝統的なローストターキーやハムなどの温かい料理に加え、シーフードやコールドミートなど、暑い気候に合った軽めの料理も人気です。特にプロンや海老などのシーフードは「オージー・クリスマス」の定番となっています。デザートには「パブロバ」というメレンゲをベースにしたケーキや、イギリスから伝わる「クリスマスプディング」が楽しまれます。一方、日本のクリスマスではケーキとフライドチキンが定番となり、宗教的祝日というよりも恋人や家族と過ごす特別な日としての性格が強いです。 イースター(復活祭)もオーストラリアでは重要な祝日で、チョコレートの卵や「ホットクロスバン」と呼ばれるスパイスの効いた甘いパンを食べる習慣があります。日本ではイースターは一般的な祝日ではなく、特別な食事の習慣もあまりありません。 オーストラリアデー(1月26日)には、バーベキューが国民的行事となっています。公園や浜辺で家族や友人とバーベキューを楽しみ、ラム肉やソーセージ、ビーフバーガーなどを食べるのが一般的です。日本では建国記念日に特別な食事の習慣はあまり見られません。 アンザックデー(4月25日)は、戦没者を追悼する重要な日で、「アンザッククッキー」というオーツ麦とココナッツを使ったクッキーを食べる習慣があります。これは第一次世界大戦中に戦場にいたオーストラリアとニュージーランドの兵士たちに送られていたクッキーに由来しています。 オーストラリアの新年(1月1日)の食事は比較的カジュアルで、バーベキューや軽食が中心です。一方、日本のお正月は最も重要な祝日の一つで、おせち料理や雑煮など、伝統的で意味のある特別な料理を楽しむという大きな違いがあります。 誕生日のお祝いも異なります。オーストラリアでは「バースデーケーキ」にろうそくを立て、歌を歌った後で本人がろうそくを吹き消す習慣があります。日本でも同様の習慣がありますが、オーストラリアではケーキに加えて、家族や友人と一緒にレストランでの外食を楽しむことが多いです。④ オーストラリアの食文化の日本との違い(おふくろの味)
オーストラリアと日本では、「おふくろの味」や家庭料理の概念にも興味深い違いがあります。日本の「おふくろの味」は、母親から受け継いだ伝統的なレシピや、家族それぞれの好みに合わせた独自のアレンジが加えられた料理を指すことが多いです。一方、オーストラリアの家庭料理は歴史的な背景もあり、より多様で折衷的な特徴を持っています。 オーストラリアの伝統的な家庭料理は、イギリスの影響を強く受けています。「ミートパイ」(挽肉やステーキ肉を具材としたパイ)、「バンガーズ・アンド・マッシュ」(ソーセージとマッシュポテト)、「ローストディナー」(ローストミートと野菜)などが典型的です。ただし、これらの料理も各家庭によってレシピが異なり、イタリア系やギリシャ系、アジア系など、家族のルーツによってはまったく異なる「おふくろの味」を持つ家庭も多いです。 調理法にも違いがあります。日本の家庭料理は繊細な味付けと見た目の美しさを重視する傾向がありますが、オーストラリアの家庭料理はボリュームと満足感を重視し、一皿で栄養バランスが取れるような実用的な料理が多いです。例えば、キャセロール(肉と野菜の煮込み料理)やパイ、シチューなどが人気で、これらは長時間煮込んだり焼いたりするため、忙しい家庭でも準備しやすいという利点があります。 また、日本の家庭料理は季節感を大切にし、旬の食材を使うことが重視されますが、オーストラリアでは一年を通して同じような料理が食べられることが多いです。ただし、近年は「ファームトゥテーブル」の概念が広まり、地元の季節の食材を使った料理に価値を見出す傾向も強まっています。 食材の使い方にも違いがあります。日本の家庭料理では魚や野菜、豆腐などの植物性たんぱく質が多く使われますが、オーストラリアの家庭料理は肉中心で、特に牛肉、ラム肉、鶏肉が主役となることが多いです。また、オーストラリアでは「レフトオーバー」(残り物)を翌日の料理に活用することが一般的で、例えば日曜日のローストチキンが月曜日のサンドイッチやサラダの具材になるといった工夫がされています。 世代による違いも興味深いです。オーストラリアでは若い世代を中心に、世界各国の料理の影響を受けた折衷的な家庭料理が増えています。タイカレーやパスタ、スティーフライなどが現代のオーストラリアの「おふくろの味」として定着しつつあります。一方、日本でも洋食や中華などの影響を受けた家庭料理はありますが、伝統的な和食をベースにした料理が多い傾向があります。⑤ オーストラリアの食文化の日本との違い(その他)
オーストラリアと日本の食文化には、上記以外にもいくつかの興味深い違いがあります。まず、食事のペースが異なります。オーストラリアでは食事をゆっくり楽しむ文化があり、特にディナーは1〜2時間かけて会話を楽しみながら食べることが一般的です。一方、日本では特に平日のランチなどは効率良く食べることも多く、「食事は15分で済ませる」というスタイルも珍しくありません。 食事に対する価値観も異なります。オーストラリアでは「食は楽しむもの」という考え方が強く、週末には友人や家族と一緒に長時間をかけて料理したり食事を楽しんだりします。特にバーベキューは単なる調理法ではなく、人々が集まって交流する社交の場としての意味合いが強いです。日本でも食事を楽しむ文化はありますが、栄養バランスや健康面を重視する傾向がより強いと言えるでしょう。 食材の入手方法や買い物の習慣にも違いがあります。オーストラリアでは週に1〜2回まとめ買いをする家庭が多く、大型スーパーでの購入が一般的です。また、週末に開かれるファーマーズマーケットで直接生産者から新鮮な食材を買う文化も広がっています。一方、日本では毎日の買い物を大切にする傾向があり、鮮度にこだわって近所のスーパーや専門店で少量ずつ購入することが多いです。 食品のパッケージや保存方法も異なります。オーストラリアでは大容量パッケージが一般的で、食材を冷凍保存することも多いです。一方、日本では少量パッケージが主流で、できるだけ新鮮な状態で消費することが好まれます。 ファストフードの位置づけも違います。オーストラリアではファストフードは「便利だけど健康的ではない」という認識が強く、特別な機会以外はあまり頻繁に食べない家庭も多いです。一方、日本ではファストフード店でも比較的健康に配慮したメニューが提供されており、日常的な食事の選択肢の一つとなっています。 食事のシェアリングの文化も異なります。オーストラリアでは大皿に盛られた料理をシェアするスタイルが一般的で、特にカジュアルなレストランやパブでは「シェアプレート」というメニューが提供されることも多いです。日本でも居酒屋などでは料理をシェアする文化がありますが、一人一人に料理が提供される「一人前文化」も根強いです。 最後に、食事と健康の関連付けについての違いも興味深いです。日本では「医食同源」という考え方があり、食事と健康が密接に結びついています。一方、オーストラリアでは近年健康志向が高まっているものの、「楽しむための食事」と「健康のための食事」を分けて考える傾向があります。例えば、週末は好きなものを楽しみ、平日は健康に気をつけるといったスタイルが一般的です。まとめ
オーストラリアと日本の食文化には、歴史的背景や地理的条件、そして文化的価値観の違いから生まれた多くの相違点があります。オーストラリアの食文化は多文化社会を反映した多様性が特徴で、イギリスの伝統的な影響を基盤としながらも、世界各国の料理が融合した「モダン・オーストラリアン」として独自の発展を遂げています。 食事のスタイルでは、オーストラリアは肉中心で量が多く、一皿完結型の料理が一般的である一方、日本は魚や野菜を多く取り入れ、複数の小皿で構成されるバランスの取れた食事が特徴です。食事中の会話も、オーストラリアでは活発なコミュニケーションの場として重視されますが、日本ではより静かに食事に集中する傾向があります。 祝日や記念日の食事は、それぞれの国の文化や気候を反映しており、オーストラリアの夏のクリスマスでは軽やかなシーフードが人気である一方、日本のお正月には意味のこもった伝統的なおせち料理が楽しまれます。「おふくろの味」も、オーストラリアではより多様でボリューム感のある実用的な料理が多く、日本では繊細な味わいと季節感を大切にした料理が一般的です。 これらの違いを理解することで、オーストラリアを訪れた際や、オーストラリア人と交流する際に、より深く食文化を楽しむことができるでしょう。また、違いを知ることは自国の食文化を客観的に見つめ直す良い機会にもなります。 食は文化の重要な部分を占めており、その国の歴史や価値観を色濃く反映しています。オーストラリアと日本の食文化の違いを尊重しながら、互いの良さを学び合うことで、より豊かな食体験が生まれるのではないでしょうか。 ワンコイングリッシュでは、英語だけでなく文化などについても教えてくれます。他の先生や生徒とコミュニケーションが取れるイベントも盛りだくさんで、海外の文化を知ろうとしている方におすすめの英会話学校です。体験レッスンも受付中ですので、是非活用をご検討ください。